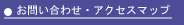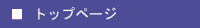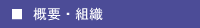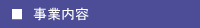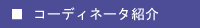過去の記事
C第16話「小僧寿し」
最後は“小僧寿し”のお話です。“小僧寿し”と言えば、「鉢巻太助(はちまきたすけ)」をキャラクターとする持ち帰り寿司チェーンの代表格、全国に500を超える店舗を展開するジャスダック上場の有名企業です。
その“小僧寿し”がなんと、「抜本的な経営改革を行い、早期黒字化を目指し、安定的な収益を計上できるスリムで筋肉質な経営体質に転換するために、社内外から広く意見を募集」という目的で、8月一杯、株主、客、FC加盟店、取引先、従業員など「全ての方」から経営方針の提案を求めているのです。
これには、多くの方から「開いた口がふさがらない」と反響続出。反面、話題集めには格好のネタという評価もあるようです。
それはそうでしょう、なにせ経営に携わってもおらず、経営に携わった経験もなく、小僧寿しを知っているだけという人も含めて、なんでもよいので知恵を貸してください、と言っているようなもの。「経営幹部が『もうどうしたらいいかわからん』って言っているのと同じ」という声にもうなずきたくなります。
さて、ここで“小僧寿し”のここ数年の迷走を振り返ってみたいと思います。そこに、今回の珍騒動の背景が隠されていると思うからです。
“小僧寿し”は1964年に創業、その後、フランチャイズで全国へ展開し、2004年にはジャスダックへ上場、ここまでは順調な成長軌道を辿ってきたと言えるでしょう。
その後、外食業界の競争激化の中、すかいらーくの傘下に入りましたが、すかいらーく自体が経営不振に悩む中、2012年にイコールパートナーズというファンドに買収されることになったのです。
このイコールパートナーズというファンドは、一括請求サービスというITビジネスで急成長したベンチャー企業経営者が立ち上げたものでした。
いわば、持ち帰り寿司という業態とはまったく無関係なファンドが経営権を握ることになったのです。
しかし、この異業種からの参入は惨惨たる結果をもたらしました。わずか1年半の経営の中で「日本経済の再生に貢献したい」というキャッチフレーズで商品の1円値下げを行い、さらにおせちセットの販売など、いくつかの新規サービスに取り組みましたが、そのほとんどが人目を引くだけの効果しかなく、経営の立て直しには貢献できませんでした。
そうしましたら、こんどは三菱商事出身、海外で弁護士活動をしてきた方が経営権を握ることになりました。
これも持ち帰り寿司という業態とはあまり関係のない経営者です。
やはり、することは同じです。こんどは寿司屋でピザを扱うという新機軸です。「寿司専門店」+「ピザ専門店」+「どんぶり専門店」の新たな三業態複合テイクアウト店という挑戦ですが、これもまた人目は引いたものの、経営の立て直しにはほとんど寄与しませんでした。
二代にわたる異業種からの経営者は“小僧寿し”の経営再建には機能しなかったのです。機能しなかっただけであればまだしもです。今度の経営者はなんと社外への不適切な支出(資金の持ち出し)という理由で退任することになりました。
そして、いよいよ建設関係の企業家が経営者に登場することになりました。IT業界⇒弁護士⇒建設業界と三代続いて、持ち帰り寿司という業態とはあまり関係のない経営者となったのです。
もちろん、業態経験のあるなしが経営者にとって決定的な要素とは言えません。日本航空の経営再建は京セラの創業者が成し遂げたものです。そうした事例は枚挙に暇がありません。
しかし、経営再建に成功した経営者にはやはりきちんとしたビジョンがありました。
1円引きサービスとか宅配ピザとかは、いわゆる思い付きの範疇でしかありません。経営理念であるとか、企業の存在意義であるとか、あるべき企業の姿であるとか、そうしたビジョンに欠かせない首尾一貫したメッセージ性はかけらも感じられないのです。要は新味があって、目立てばよい、あるいは売れればよい、というだけのものではないかと思われて仕方ありません。
そうした観点で考えてみますと、今回の経営方針の募集も同じ臭いがしないでしょうか。たしかに耳目は集めるでしょう。しかし、なぜ募集するのか、という理念がそこにあるでしょうか。
もちろん、新しい経営者のもとに“小僧寿し”の経営再建は進められるでしょうし、その成否を今論じる必要もありません。
皆さんはビジョンとは何か、ビジョンが経営に何をもたらすのか、という観点から“小僧寿し”の今後の経営に注目していただきたいと思います。
C第15話「三越」
次の問題は、コミュニケーションです。すこし話は古いですが、有名な三越事件を取り上げてみたいと思います。
“三越”と言えば、三井財閥発祥である呉服の越後屋をルーツとする小売業の名門中の名門、「贈り物は、やっぱり三越」というキャッチコピーに見られるように百貨店業界の中でも特別のステータスを誇っていました。
その三井グループの旗頭のような名門企業が大激震に襲われたのが1982年、今から30年ほど前になります。
俗に三越事件と言われるこの大騒動の影響は、その後も長く“三越”を苛み、とうとう2011年には新興の伊勢丹に吸収される形で独立企業としての歴史に幕を閉じることになったのです。
さて、1982年、この年の6月、“三越”はその優越的な地位を使って、納入業者に対する商品や映画前売券の押し付け販売、協賛金や社員派遣の要請、種々の催し物への費用負担などの不公正な取引方法を行ったと、公正取引委員会から指摘されたのです。実は、こうした“三越”の横暴さが今のクロネコマヤトを産んだという皮肉な出来事もありました(“三越”との取引停止から宅急便へ本格進出)。
また、8月には“三越”で開催された「古代ペルシャ秘宝展」の出展物の大半が贋作であることが判明。
さらに、当時の代表取締役の取り巻きとの不明朗な取引が告発されるなど、収集のつかない状態に陥ったのです。
そして、運命の日がやってきました。1982年9月22日、“三越”の取締役会で代表取締役解任の動議が出され、とうとう事件の主人公である代表取締役はその座を追われたのです。このとき、彼が発した「なぜだ!」という悲痛な叫びはその年の流行語にも選ばれたほど、実にショッキングな事件でした。なにせ、社長でも解任されることが衆目に晒されたのですから。
さて、“三越”のような名門企業に何が起こったのか、です。
それは、ごく簡単に言いますと、会社という「組織」の中ではコミュニケーションがまったく成立しなかった、ということです。
コミュニケーションとは相互に意味と感情をやり取りする行為ですが、当時の“三越”では代表取締役から下へ発せられるメッセージが唯一の意味と情報であり、代表取締役とコミュニケーションする立場にない社員にはその上位者から代表取締役のメッセージを受け取ることだけが会社の伝える唯一の意味と情報になってしまっていたのです。
その背景には、代表取締役は〇〇天皇と呼ばれるほど、社内で強烈なワンマン体制を確立し(大株主でもないサラリーマン社長としては希有のことですが)、周辺にはイエスマンだけを残し、すべてのライバルを社外へ追い出し、ほとんどすべてを自らの独断で進めていた、ということがあります。
そうした代表取締役の暴走を許す大企業というのも不思議な話ではあるのですが、10年間の社長時代にそういうワンマン体制が確立されたのは事実のようです。
いずれにせよ、こうして“三越”という「組織」ではコミュニケーションが成立しない、極端な上意下達の状態に陥っていたのです。
こうなりますと、「組織」に“関係性”や感情がはびこるのは皆さん既におわかりのはずです。
要は、代表取締役、あるいはその取り巻きのイエスマンとの“関係性”に最大の意味があり、彼らにマイナスの感情を与えないように振る舞うことが最善の選択となるのです。
この三越事件は当時の日本に大きな衝撃を与えましたので、高杉良の「王国の崩壊」、大下英治の「小説三越・十三人のユダ」といった優れた経済小説を産み出しています。
皆さんもいずれかの機会に一読されると、企業というもののある意味での実相が見えてくるかもしれません。
さて、これで“雪国まいたけ”の信賞必罰、“三越”のコミュニケーションとお伝えしてきましたので、いよいよ次回はビジョンです。
ビジョン、それは経営理念で規定された経営姿勢や存在意義に基づき、こうなっていたいと考える到達点、目指すべき中期的なイメージを投資家や従業員や社会全体に示したもの、この大切さに触れてみたいと思います。
C第14話「雪国まいたけ」
ここまで、「組織」が“関係性”や感情に流されないあり方として、①信賞必罰、②コミュニケーション、③ビジョンを取り上げてきました。今回からは、それを失ったとき「組織」はどうなるのかを、具体的な企業を題材に調べてみたいと思います。
最初は、“雪国まいたけ”です。
新潟県南魚沼市に本社があり、東証2部に上場されている株式会社、1972年創業と歴史は新しいですが、まいたけ、エリンギ、エノキタケなど、キノコの栽培では業界トップを争っています。売上も年商300億円近く、従業員も1,000名規模ですので、これは立派な大企業と言ってもよいでしょう。
この大企業が有価証券報告書の虚偽記載、わかりやすく言いますと、一種の不正経理を行って架空の黒字を計上した、という大事件で揺れたのが昨年の秋でした。
その内容は、ライバルとの競争で企業経営が悪化する中、①損失計上すべきだった土地関連費用を資産へ計上、②一部事業用資産の減損処理を回避、③広告宣伝費を次年度へ計上、の3項目で総額14億円の不正な処理を行ったことでした。
そして、問題はこうした不正経理が内部告発で明らかになり、それを暗黙裡に主導したのが創業者であり、大株主でもある代表取締役だった、ということです。
その間の事情を報道ではこのように伝えています。
「創業者の強すぎたリーダーシップによる暗黙の重圧があった」、「幹部や社員が創業者の思いを忖度(そんたく)した結果の行動だった」、「背景には経営トップによる業績維持の圧力が幹部や担当者まで及んでいた」など。
さて、ここまでで事件が終わるとすれば、それは一企業におけるガバナンス(企業統治)の未熟で済んだことでした。
しかし、事態はさらに迷走します。
それは、不正経理の責任を取って創業者は代表取締役を辞任し、代わりに当時取締役でかつてイオン執行役員を務めた方が代表取締役へ就任。さらに、「創業家兼大株主の影響を受けないようにするため、適度な出資割合まで引き下げていく方向で交渉を行っていきます」とした改善報告書を東京証券取引所へ提出し、創業者も今年春には顧問を退き、いよいよ経営再建だ、と世の中は受け止めたのです。
しかし、今年6月に開かれた定時株主総会で、会社提案の取締役人事案に対し、創業者一族から異なる人選での取締役選出の動議が出されました。会社提案では代表取締役らの再任でしたが、創業者一族の動議はすべての取締役を入れ替えるもので、これが賛成多数で可決され(大株主は創業者一族ですから)、代表取締役らは取締役を退任。代わって元ホンダ専務取締役の方が代表取締役へ就任したのです。
要するに、創業者一族は自分たちの跡を継ぎ、経営再建へ乗り出した経営陣にノーを突きつけ、その首をすげ替えた、ということです。
この先、“雪国まいたけ”がどういった経営再建を進めるのかはわかりません。
しかし、ここで問題にしたいのは信賞必罰という観点から見てどうなのか、です。
信賞必罰の大前提は、たとえ経営者であってもその対象からは免れない、ということです。
仮に組織の上位者が信賞必罰から逃れられるとするならば、誰が信賞必罰を信用するでしょうか。信賞必罰の重要な前提は、ルールが明らかであり、例外のないことなのです。
その意味からすれば、創業者が代表取締役を辞任したのは立派に信賞必罰を守った行為でした。
しかし、今回の経営陣交代はどうでしょうか。
仮にそれが創業者一族の影響力を“雪国まいたけ”で維持し、創業者一族が経営をコントロールするためのものであるならば、これは明らかに信賞必罰ではありません。
むしろ、“雪国まいたけ”という「組織」の中で、創業者との“関係性”を温存助長する行為だ、と言ってもよいでしょう。
ちなみに、“雪国まいたけ”が不正経理に走った背景には、ライバルである長野市のホクト株式会社との熾烈なシェア争いがあったと言われています。
そういう意味では、新潟と長野のキノコ戦争がとんだところまで飛び火したものです。
皆さんも地元の企業に関係のある“雪国まいたけ”の経営が今後どのように展開されるのか、「組織」における“関係性”や感情という観点から注目していただきたいと思います。
C第13話「ビジョン」
「組織」が“関係性”や感情に流されないあり方はどういうものなのかを考えようと、信賞必罰(賞すべき功績のある者には必ず賞を与え、罪を犯し、罰すべき者は必ず罰するという意味とに他なりません)、コミュニケーション(何を話してもよい、上司は部下からの批判にも耳を貸す、お互いに言いづらいことも言う、背景に安心感があり、それに支えられて、まわりへの関心が芽生え、そして行動が起こる)という二つの仕組みをお伝えしました。最後はビジョン(経営理念で規定された経営姿勢や存在意義に基づき、こうなっていたいと考える到達点、目指すべき中期的なイメージを投資家や従業員や社会全体に示したもの)です。
人は自分の乗っている船がどこへ行こうとしているのか、それがわからないときに不安になります。先が見えないときには安心もできません。
こうした疑心暗鬼の状態は、人に強く“関係性”や感情を想起させます。誰かに頼りたい、頼もしそうな人に寄り添いたい、重要人物に嫌われたくないということです。
こうなりますと、「組織」はどんどん“関係性”や感情に引きずられてゆきます。
従って、「組織」は進むべき道筋、将来の目標をビジョンとして発信する必要があります。
たとえ今は辛くても、ここを乗り切れば先は明るいと思えれば、人はけっこうタフに振る舞えるものです。逆に先が見えないと、人は本来の能力やエネルギーをフルに発揮できないものです。
ここにビジョンの重要性があります。
ジェームズ・C・コリンズというドラッカーの教え子がいます。スタンフォードで長年教鞭を取ってきた経営コンサルタントですが、彼の名著に「ビジョナリー・カンパニー」4部作があります。
卓越した業績を上げてきた企業を分析し、その中から普遍的に通用するあり方を探るもので、1と2では成功した企業の理由を、3では成功した企業が衰退した原因を、4では不安定な環境においても躍進した企業を、それぞれ取り上げています。
例えば、1926年から90年までの65年間、ビジョナリー・カンパニーの株式の累積総合利回りは市場平均の15倍に達しているそうですので、長期にわたって成長を続けている企業だ、ということがわかります。
そこで強調されることは、その会社がどこへ進もうとしているのかが、社員はもとより、お客さまにもきちんと伝わっている、ということです。
もちろん、GEやIBMのような世界規模の優良企業とごく普通の中小企業を一緒に考えることはできないかもしれません。
しかし、たとえどんな小さな中小企業であったとしても、自分たちがどこへ進もうとしているのかが明らかになっていなければ、日々は疑心暗鬼、出たとこ勝負の連続になってしまいます。
ですので、どんな「組織」であってもビジョンは欠かせないとお考えください。
ただし、そういったビジョンがどのように形作られたのか、というプロセルにも注意が必要です。
信賞必罰の話の中でも、単に上から押し付けられる「基準」よりは、自分自身が参加して決めた「基準」の方がそれを遵守する意識は高まる、とお伝えしました。
これはビジョンでも同様です。
仮にそうしたプロセスを取ることが難しい場合は、ビジョンの背景や根拠が明らかになっていることが重要になります。
これも筆者の体験談ですが、ある会社のコンサルタントをしている際に驚いたのですが、ビジョンはどういったものかと経営者から聞き取りをしていましたら、〇〇%の利益率、という回答が返ってきました。ただし、どうして〇〇%なのかを確認したところ、業界水準(根拠は不明でしたが)ということでした。
これがはたしてビジョンとして「組織」内で共有できるものかどうか、当然おわかりのように、これは上から押し付けられる「基準」であって、ビジョンと言えるものではありません。
もちろん企業ですので利益は重要です。しかし、利益を上げるのは何のためか、です。
例えば、クライアントから契約を切られた際の備えにしよう、でもかまわないのです。給与水準を改善しよう、でもかまわないのです。第二の営業拠点を設ける原資にしよう、でもかまわないのです。
少なくとも達成すべき何かがあって(組織メンバーが納得できる)、それを実現するために〇〇%だ、というのであれば、まだしも救われます。
ビジョナリー・カンパニーでは面白い表現をしています。
ビジョナリー・カンパニーは確固たる基本理念を持ち合わせている、利益の追求はこうした基本理念追求の手段である、ということです。
例えば、ある企業の基本理念は「顧客へのサービスを何よりも大切にする」だそうです。
こうした基本理念(ビジョン)と比べて見ますと、〇〇%の利益率という表現がいかにみすぼらしいか、です。
いずれにせよ、組織メンバーが納得できるビジョンを明らかにすることによって、「組織」が“関係性”や感情に流される危険性はかなり少なくなるのではないでしょうか。
どうか皆さんも、ご自分の属する「組織」ではどうなのか、信賞必罰、コミュニケーション、ビジョンという三つのあり方をよく観察していただきたいと思います。
C第12話「コミュニケーション」
世の中の企業では皆さんが考えるよりはるかに多く、経営再建という問題が発生しています。日本航空のようにわかりやすい経営破綻になれば当然のこと、そこまでは至らなくても経営不振を抜け出すために経営再建に取り組むことが多いのです。
ところが、そうした事例をよく分析しますと、かなりの確率で経営再建に取り組む経営者は「現場との会話」をはじめます。
全国のすべての支店や営業所を廻って声を聴く、課長級以上のすべての社員と面談する、あらゆる工場を視察して対話を重ねる、こういった行動が多く取られるのです。
これは、逆に考えますと、それまでは「現場との会話」を重視していなかった、ということになります。
経営者が現場と話さなくて、どうやってお客さまの声や職場の問題点を把握できるのだろうかと思うのですが、皆さんが想像するよりはるかに経営者は現場を知らない場合が多いのです。
経営者と現場の距離が遠くなると何が起こるでしょうか。
「経営者に生の情報が入らない」、そのとおりです。
ですが、それ以上に怖いのが「経営者には耳触りのよい情報しか上がってこなくなる」ということです。
かつて、徳川幕府では側用人と称する権力者が横行しました。将軍が神格化し、家臣が将軍に直接話すことができなくなってきますと、誰かが将軍と家臣の間をつなぐ役割を果たすようになります。いわゆる取次(とりつぎ)ということですが、家臣はまずこの取次に情報を上げるしかありません。そうなりますと、取次はそういった情報の中から選んで情報を将軍に伝えることができます。いわゆる情報の恣意的な操作がはじまるのです。
取次がどんなに善人で、将軍への忠誠心が強かったとしても、いやそうであればあるほど、取次は将軍が喜ばない情報を伝えることを躊躇します。
こうして、いつしか将軍には耳触りのよい情報しか届かなくなります。
この仕組みでは、将軍と取次の“関係性”、取次と家臣の“関係性”という二重の“関係性”が強く働いているとも言えます。
これは明らかに「組織」の中でコミュニケーションが途絶えていると言えます。
開かれたコミュニケーションが無ければ、「組織」は必ず“関係性”の世界へと導かれます。権力者との“関係性”がもっとも重要になる、ということです。
従って、「組織」において重要なポイントの一つは、「組織」の中で開かれたコミュニケーションが存在するかどうか、なのです。
しかし、急にコミュニケーションを、と言っても、それを実現するにはそれなりの工夫が必要です。
まずもって、「組織」における上位者は下のものからの情報を聞く、下のものと会話する、というメッセージが「組織」全体で共有されていなければいけません。
この前提が無ければ、下のものが上位者へ情報を伝える、意見を言う、会話するというのは難しいものです。「組織」における上下関係には必ず心理的障壁が付きまわるのです。
ですので、上位者がそうした心理的障壁を取り除く態度やメッセージを常に発信していなければならないのです。経営再建のような、誰にでもわかる緊急事態であればまだよいのですが、日常では心理的障壁は消えにくいものだからです。
逆の言い方をしますと、下のものからの情報や意見を尊重する、という態度やメッセージを上位者は常に発信すべきなのです。
筆者の体験談で言いますと、毎月定例的に幹部社員を集めて会議をする会社がありました。
これ自体は当然評価されるべき取組みです。
しかし、その定例会議は常に経営者の独演会に終始します。
経営者が声高に持論を展開するたびに、幹部社員は委縮して下を向き、ひたすら経営者のご高説を承るだけです。
これでは、仏作って魂入れず、せっかくの仕組みが生きていません。いや、かえって心理的障壁を高くするマイナス効果しか発揮していないのです。
第6話の「質問する力」で、自分のための質問ではなく、相手のための質問をしましょう、とお伝えしました。
この経営者は最低でも持論を展開する前に、質問する力を発揮すべきです。
それよりも、リスニング・スキル(「聴く」力)を磨くべきでしょう。
人は心を開いて話せた相手を信頼するそうです。相手に心地よく安心感を持って話してもらうためには、少なくとも全身で「聴いている」ことを相手に伝えなければいけません。
ここまでコミュニケーションに欠ける会社は珍しいですが、少なくてもコミュニケーションの土台(コミュニケーション・インフラ)を醸成することはどんな「組織」であっても重要なことです。
即ち、「組織」内のコミュニケーションを活性化する目に見えないインフラ(慣習など)を普及させることです。
例えば、何を話してもよい。どんな提案も受け付けられる。上司は部下からの批判にも耳を貸す。お互いに言いづらいことも言う。知らないことを簡単に聞くことができる。
背景に安心感があり、それに支えられて、まわりへの関心が芽生え、そして行動が起こる。
こうしたコミュニケ―ション・インフラがあって、はじめて効果的で、生産的なコミュニケーションが交わされるのではないでしょうか。
そして、開かれたコミュニケーションによって、「組織」が“関係性”や感情に流される危険性はかなり少なくなるのではないでしょうか。
どうか皆さんも、ご自分の属する「組織」ではどうなのか、よく観察していただきたいと思います。
C第11話「信賞必罰」
戦国時代の末、今から2,300年ほど前になりますが、韓非子という思想家が中国で産まれました。法に基づく支配体制を唱えたことから、韓非子をはじめとする一群の人たちを「法家」と呼んでいます。
今日のような現代社会とは大きく異なる当時の社会での考え方ですので、そのまま通用する訳はありませんが、その考え方の中には今でもなるほどと思える内容もたくさん含まれています。
そのうちの一つに「二柄(にへい)」という考え方があります。
それは、国を治めるに際して重要な権力には、「刑」と「徳」の二つがある、というもので、それを道具としての柄(え)に例えたものです。
「刑」は言うまでもなく罰すること。
「徳」は同じように褒めること、です。
韓非子は次のように伝えています。
「明君と呼ばれる人達は、たった2本の柄(権力)で臣下を統率するものである。その2本の柄とは、刑と徳というものです。刑と徳が何かと説明しますと、刑とは犯罪に対する罰のことであり、徳とは功績に対する賞のことです。臣下達は、刑罰を受けるのを畏れて、恩賞を得るのを喜ぶものです。ですから人の上に立つ者は、自らその刑と徳を用いなければなりません。そうすれば、臣下達は皆、その権威を畏れ、その恩に従うようになるからです。ところが、世にはびこる奸臣達は、主君からその権限を盗み取って、嫌いな者には罰を、好きな者には恩賞を与えようとするのです。ですから、君主たる者は、賞罰の権限を他人に委譲してはなりません。もし、重臣の一人にその権限を委譲したのなら、国中の人々は皆その重臣を畏れるようになり、君主を軽んじることになります。人心は、君主から去り、その重臣に帰することになるのです。これが、君主がこの2つの権力を失ったことに対する災禍なのです。」
さて、これを現代の「組織」に置き換えますと、要は信賞必罰(賞すべき功績のある者には必ず賞を与え、罪を犯し、罰すべき者は必ず罰するという意味とに他なりません)です。
前回、“関係性の罠”という表現で、「組織」で“関係性”や感情が幅を利かせる危険性をお伝えしました。
そして、「組織」が“関係性”や感情に流されないあり方はどういうものなのかを考えますと、その最初のヒントがここにあります。
仮に「組織」が功績を上げたものを賞せず、罪を犯したものを罰しなければどうなるでしょうか。仮に功績を上げていなくても自分と関係が近いことを理由にして賞し、罪を犯しても自分と関係が近いことを理由にして罰しなければどうなるでしょうか。
一つの参考に産経新聞が取り上げた事例をご紹介しましょう。
「~優しい教師による友達感覚の学級運営が瓦解を招く~
年度当初、保護者は自分の子供は受けいれられていると感じ、教師との信頼関係が築かれる。だが、内実は先生と個々の子供の関係ばかりが大切にされ、集団としてのまとまりに欠けている。教師は友達口調で子供に接し、子供に善悪を理解させず、曖昧(あいまい)な態度を取ることが多い。学級のルールが守れなくても、今日は仕方がないなどと特例を設け、私語を許すなどルール作りがおろそかになり、子供側にはルールは先生の気分次第という空気が生まれる。やがて教室内には、教師の気を引く言動が無秩序に生まれ、あの子がほめられて面白くない、先生は私と仲良くしてくれないなどの不満が噴出。告げ口が横行し、学級の統制が取れなくなる。」
こうした学級崩壊のパターンを「なれ合い型学級崩壊」と呼ぶそうですが、実際の学級崩壊の多くはこうしてはじまるそうです。
「組織」が崩壊することはなかなか起こりませんが、「組織」が無秩序に、あるいは非効率的に陥ることは少なくありません。
その原因の一つがここにあります。
罰すると褒めるが両方存在していないと(信賞必罰を行わないと)、どうしても「組織」は“関係性”や感情に流されがちになります。
これでは、「組織」の未来は見えてきません。
しかし、信賞必罰はその前提となる「基準」が示されていなければ何の価値もありません。
何をしたらよいのか、何をしたらいけないのか、そうしたルールが明らかになっている。
これがなければ、信賞必罰の根拠が見えませんので、誰もが疑心暗鬼になる、ふたたび「組織」は“関係性”や感情に流されてしまいます。
こうした「基準」を定めること、これが最初の一歩なのでしょう。
よく聞くのは、事務のデスクワークなので「基準」を決めるのが難しい、ということがあります。
もちろん、生産工場のように成果を可視化しやすい職場では「基準」は簡単に決められるでしょう。
しかし、どんな仕事であったとしても、それが何らかの成果を上げるために行われるものであれば、そうした成果をベースとした「基準」を決めることはできるはずです。
また、「基準」を決める際にどういった参加形態を取るべきか、という点にも注意が必要です。
単に上から押し付けられる「基準」よりは、自分自身が参加して決めた「基準」の方がそれを遵守する意識は高まるものです。
そう考えてみますと、まずはできるだけ多くの参加を求めながら職場で「基準」を決める、その上で「基準」に沿った信賞必罰が行われる、これが「組織」が“関係性”や感情に流されないあり方の第一ステップなのではないでしょうか。
どうか皆さんも、ご自分の属する「組織」ではどうなのか、よく観察していただきたいと思います。
C第10話「関係性の罠」
私たちが「組織」を考える際に(ここで言う組織とは自分の属する集団とお考えください)、もっとも注意しなければならないのが“関係性”です。“関係性”は、相互の関わりのことを指すのが一般的ですが、ここでは「組織」を前提としますので、その中における関わり、特に「組織」のシニアメンバー(有力者)との関わりを意味しています。
私たちがもっとも最初に属する「組織」は家族です。
家族は、それを構成するメンバー相互の関わりが極めて重要な意味を持ちます。特に、家族を率いる家長との関わりは決定的な意味を持つ場合が多いものです。
具体的には、父であり、母でありますが、そのどちらが重要かは家族ごとに違いますので、ここでは親と考えてよろしいでしょう。
親との関わりが家族におけるほとんどすべてと言ってもよいほど、家族では“関係性”が重要になります。仮に親との関わりが希薄であれば、その家族は崩壊へと陥るでしょう。
相互の関わり、親との関わりが密であればあるほど、その家族は結束し、助け合い、強固なものとなります。素晴らしい話です。
しかし、私たちが一般的に属する「組織」ではそうとは言えません。
相互の関わりの浅さ、深さの如何を問わず、私たちは「組織」へ属することになるからです。家族が生まれもっての関わりだとすれば、こうした「組織」は後天的な関わりに過ぎません。
従って、家族が本来持っているような帰属意識はありませんし、事の是非を問わない家族の賛同も期待できません。
さまざまな事件を見るたびに、家族を思う親の気持ちにはついつい涙を誘われるものです。
では、一般的な「組織」において“関係性”は、どういった役割を持つでしょうか。
それは、「まるで家族のように居心地がよい」という「組織」は本当によいのか、ということでもあります。
ここで考えていただきたいのは、人と人とのコミュニケーションにおいて、相互にやり取りするものは感情と情報である、ということです。
“関係性”が重視される「組織」では、情報よりも感情が重要性を発揮します。
やりとりされる情報ではなく、やりとりされる感情に人は注意を払うのです。
例えば、家族におけるコミュニケーションを考えてみましょう。そこでは感情のやりとりが一番大切になります。その人が好きか嫌いか、その人と近しいか遠いか、それが重要なのです。
ですので、たとえたいした情報が含まれていなくても(時には無言のそぶりであったりもしますが)、それが相手へのプラスの感情を示すものであれば歓迎されます。しかし、どんなに重要な情報が含まれていたとしても、それが相手へのマイナスの感情を示すものであれば歓迎されません。
子どもがどんなに悪さをしても、その中に親への甘えのようなプラスの感情が含まれているとき、親はそれを受け入れ、子どもへの感情をさらにプラスへ、より強い愛情へと高めることになります。
そうして家族において人は相手との感情に支配され、あるいは相手との距離感に左右されるようになります。
これが「組織」だったらどうでしょう。
相手が好むような情報しか伝えない、相手に好まれないような情報は伝えないようにしよう、そうなったら「組織」はおしまいです。
伝える情報が相手にどういった感情を呼び覚ますものであっても、伝えなければならない情報は伝えなければなりません。
また、相手と近しいからコミュニケーションできる、相手と近しくないからコミュニケーションできない、というのでは「組織」は動かなくなります。
相手との距離感の如何を問わず、必要な情報は必要なタイミングで「組織」が共有することが必要です。
このように、家族のように“関係性”が重要視される「組織」と、私たちが社会で属する「組織」では、そもそも運営されるルールが違う、と考えた方がよいでしょう。
しかし、人はどうしても“関係性”を大切にしますし、感情を尊重します。
それは、人という生き物が社会的な存在である以上、切り離せないプリミティブな(生まれもっての、あるいは原初的な)性格なのです。
従って、そうした本質的なものを無理やり捨てる必要はありません。
要は、人というものが“関係性”や感情に流されがちな側面を持っているという自覚のもとに、それのもたらすマイナス作用をできるだけ少なくしようというバランス感覚が重要だ、とお伝えしたいのです。
これは、皆さんがどちらかと言うと家族の延長線上にある学生生活から、いわゆる世の中へ出て、一般的な「組織」に属するとき、「ここは家族とは違うんだ」という踏ん切りを持って欲しいということです。
それが持てずに“関係性”と感情に流されれば、必要なコミュニケーションをすることが大変になり、ひいては「組織」の中で求められる役割を果たすことも難しくなるでしょう。
また、皆さんが属する「組織」で、“関係性”や感情が幅を利かせているとするならば、その「組織」には何かしらの欠陥があると気づいて欲しいのです。
今回は、皆さん自身が気をつけるという観点から“関係性”のお話を差し上げましたが、次回からは「組織」が気をつけるという観点から“関係性”に流されないあり方はどういうものなのかを考えてみたいと思います。
C第9話「六日の菖蒲」
「六日の菖蒲(あやめ)、十日の菊」という諺があります。五月五日は端午の節句、菖蒲を飾って男子の健やかな成長を祈る風習があります。
九月九日は重陽の節句、菊を飾って長寿と健康を祈る風習があります。
では、そうした菖蒲が五月六日にあったらどうでしょうか。そうした菊が九月十日にあったらどうでしょうか。
まるで母の日の翌日のカーネーションのようなもので、時機に遅れては役に立ちませんし、その価値もほとんど認められません。
ですので、「機会」を逃してはいけない、ということの喩です。
しかし、世の中には機会を逃す事例がたくさん存在しています。いや、機会を逃さない事例こそ稀であり、ほとんどの場合、機会は逃されるために存在している、とさえ言えるかもしれません。
では、どうして機会が逃されるのでしょうか。
それは、人はほとんどの場合、機会に目を向けず、問題に目を向けてしまうからです。
やはり目の前で問題が発生すれば、それを何とか解決しようと頑張るのが人の性(さが)なのでしょう。
とはいえ、そうした問題にかかりきりになっている間に状況はどんどん変化してゆきます。そうしますと、問題解決に大きな意味が無くなってしまう状況が生まれてしまうのです。そうなりますと、問題解決の価値はどんどん失われ、「何を今さら」というところまで追い込まれてしまうでしょう。こうなると、成功はまったく期待できません。
もちろん、問題を解決しようとすることは大切ですが、それにのみエネルギーを向けると機会を見失ってしまうのです。
例えば、筆者の周辺でこうした事件が起きました。
舞台はコールセンターです。クライアントから顧客リストを提供され、お客さまに電話をかけて注文を取り付ける、という業務です。
クリアすべき条件は、一定の日限までに顧客リストのすべてに架電し、一定の割合で注文を取り付けることです。
電話をかけるオペレーターの数と質が確保できれば、架電も受注もクリアできます。しかし、オペレーターの数と質が確保できないと条件はクリアできません。
ところが、見ず知らずのお客さまに電話をかけて注文を取り付けるのはなかなか難しいこと、特に精神面のタフさがないとできないものです。ですから、オペレーターのなり手がなかなか現れず、いつも期限ぎりぎりにようやく条件をクリアするのが日常です。しかも、下請けの下請けですから、そうそうオペレーターの処遇を上げることはできません。苦労は多く、報われることは少ない仕事なのです。
それでも、かつてはそこそこの売上が確保でき、他の業務とのかねあいで会社経営上もそれなりの位置を占めていましたから、何とか条件をクリアするために(問題を解決するために)、その職場のマネージャーは寝る間も惜しんで働いていたのです。
しかし、月日が流れるうちにこの職場を取り巻く環境は変わりました。相乗効果をもたらす業務から徐々に撤退したので、会社経営上の位置がどんどん低下してしまいました。
こうなりますと、重要なことは条件をなんとかクリアして業務を続けることではなく、この業務の先行きを考え、撤退することも視野に入れて経営上の決断をすることに変わってきたのです。
まさしく、問題ではなく機会に目を向けないといけなくなった、と言えるでしょう。
そうしますと、ポイントはこの職場のマネージャー、そして会社の経営者が「機会」ときちんと向き合い、勇気のある決断をできるかどうかなのです。
ちなみに、第5話でご紹介したピーター・ファーディナンド・ドラッカー(Peter Ferdinand Drucker)は、こうした「機会」をいくつか上げて、そこへ注意を集中することが経営者には欠かせないと論じています。
第一は、「予期せぬ成功と予期せぬ失敗」です。それは、皆さんを取り巻く状況が変化していることを示しているからです。状況が変化するから予期できない訳です。
第二は、「ギャップ」です。理想や予測と現実とのギャップに状況の変化やその原因が隠されています。
第三は、「ニーズ」です。ニーズは重要ですが、予期せぬ成功や予期せぬ失敗、あるいはギャップと比べて表面にはなかなか出てきません。そこで見つける(顕在化する)作業が欠かせないのです。
第四は、「市場構造の変化」です。言うまでもなく、重要な機会です。
第五は、「人口構造の変化」です。これも同様に重要な機会です。子どもが減って、年寄りが増えれば、社会は大きく変化します。
第六は、「認識の変化」です。世の中の人々の考え方が変わってくれば、当然ですが皆さんを取り巻く常用は変化します。
第七は、「知識や技術の変化」です。例えば、人工頭脳と人工音声がビジネス化されれば、そもそもオペレーターの必要性が消えます。
こうした「機会」という視点から、どう行動すればよいかを考えることが、問題よりも機会を重視する姿勢につながるのです。
皆さんも、問題を重視するあまり機会を失うと、二度とそうした機会に恵まれることがない、という現実を直視していただきたいと思います。
とかく、人は自意識の強さや自己防衛に囚われるあまり、問題解決、しかもミスのない解決を望み過ぎるものなのですから。そして、機会は人の前を通り過ぎてしまうのです。