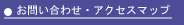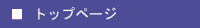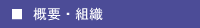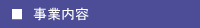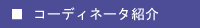過去の記事
D第8話「1億人クラブ」
去年も第12話で「人口第10位」という形でお伝えいたしましたが、日本は世界で10番目に人口の多い国であり、1億人クラブの一員なのです。しかし、1億人クラブもあの時点での11ヶ国から1年過ぎて12ヶ国へと増えました。
中国13億、インド12億、アメリカ3億、インドネシア2.5億、ブラジル2億、パキスタン1.8億、ナイジェリア1.7億、バングラディシュ1.6億、ロシア1.4億、日本1.3億、メキシコ1.2億に続いて、フィリピンが1億人に達したのです。
そのあとは、ベトナム0.9億、エチオピア0.9億、エジプト0.8億ときて、ようやくドイツが0.8億と顔を出します。そして、イラン、コンゴ、トルコ、タイ、ミャンマーと6千万人以上の国が続くのです。
いかがでしょうか、いかにアジア、アフリカにおける人口増加が著しいか、一目でおわかりいただけると思います。
そして、実は1億人クラブの中で唯一日本だけが人口減少に陥っており、2048年には1億人を割りこむということが予測されています(国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」)。
こうした数字が物語ることは二つあります。
第一は、日本の人口が減り、それに応じて市場規模が小さくなるのであれば、海外の市場を開拓する必要がある、ということです。
この文脈からすれば、当然ですが海外=アジア・アフリカ優先となるでしょう。
そうしますと、皆さんはこうした海外市場の開拓に貢献できる人材かどうか、ということがキーポイントになります。
とりわけ、大企業中心であった海外進出が今や中小企業にも求められている中、皆さんがグローバル人材となりうるかどうかは、大変重要になっていると言えるでしょう。
そのためには、多文化受容性(異なる価値観や習慣に興味を持ち、それを受け入れ、コミュニケートできる能力)が欠かせません。自分と違うからと言って、異なる価値観や習慣を否定したり、無視したり、遠ざけたりするのでは話にならないのです。どん欲なまでの好奇心を持って、異なる世界の扉を開ける勇気が大切です。
また、多言語を理解し、使う能力も欠かせません。それは必ずしも上手に、ということを意味しません。コミュニケートできることが重要なのであって、完璧に会話することが重要なのではないのです。多くの日本人は「とにかく話してみる」「自分の想いを何とか伝える」のが苦手で、恰好よく外国語を操らなければ話してはいけないと勘違いする傾向にあります。そうではなく、下手くそでも何でもとにかく相手に自分を伝える、質より量という態度でトライアンドエラーする気持ちが大切なのです。
第二は、人口が減り、労働力が減り、社会が円滑に機能しなくなるのであれば、それを改善する方向にビジネスチャンスがある、ということです。
牛丼チェーンすき家の店舗でアルバイトが確保できず、休業や営業時間の短縮が大量発生したことからも明らかなように、既に首都圏を中心として人手不足が深刻化していますが、少し国内景気がよくなり、企業が人員増へ動くと、すぐにこうした現象が現われるほど、実は日本の人口減少、労働力減少は深刻な段階に入りつつあります。
地方では景気回復の足取りが遅いので、現実味は今のところ乏しいでしょうが、これが地方にまで景気回復が行きわたるようになると、もともと人口減少の度合いがはるかに大きいのですから、より深刻に人手不足が発生し、特に4Kに代表される労働環境が苛酷な職業では手の付けられないほどの人手不足が起こっても不思議ではありません。
そうしますと、人口を増やすような仕事、労働力を増やすような仕事、省力化を図るような仕事には大きな需要が見込まれます。
例えば、子育ての支援、女性や高齢者への職業訓練や職業紹介、外国人労働者の受け入れ、業務のシステム化や情報化などは容易に思いつくことです。
皆さんもこうした観点から自分の働き場所を考えることも有効ではないでしょうか。
最後に、人口減少が原因となり、「消滅する市町村523〜壊死する地方都市〜」という予測です。これは元総務相の増田寛也氏と日本創世会議・人口問題検討分科会が発表したもので、出生の約95%を占める20歳〜39歳の女性人口に着目し、現状の出生率と社会的移動を前提とした場合に、2040年時点で人口が1万人を切る自治体が523自治体にのぼると試算し、若者、特に若い女性をつなぎ止めることができない地域は、人口が減少し、自治体が維持できないレベルに追い込まれると警鐘を鳴らしています。
事の真贋は別として、これからの日本は地域によってかなりのバラツキが生じ、人口、労働力、経済規模のいずれにおいても悲惨な状況に追い込まれる地域が出かねない、ということは確かなようです。
そうなりますと、ここでも困った人がいるとビジネスは成立する、という原則が通用しますので、そうした地域をどう再生するか、というビジネスへ挑戦する価値も高まると言えます。
もちろん、その方法はさまざまにあり得るでしょう。農林業の再生、ものづくり、特産品やブランド化、観光、福祉や教育、私たちの生活のほぼすべての領域で再生のチャンスがありそうです。
こうした視点に立って、皆さんの可能性を探ることも興味深い選択になるのではないでしょうか。特に、故郷やアイデンティティに価値を見出す人であればなおさらです。
F第7話「メッセージ性」
前回は“質問する力”のお話を差し上げました。「言葉で表現された」中から他者を理解する能力、ということです。それには、「中途採用者の選考に当たり重視している能力に関する調査」結果で、もっとも重視されているのが、「どのような仕事であっても、社内外を問わず、相手の言わんとすることや、言葉の裏にある本当のニーズ、相手の要求を理解する」能力だという背景があります。これは、相手を理解するために必要な能力と言うことができるでしょう。
一方、コミュニケーションがお互いの情報や感情のやり取りだとすれば、相手から引き出す働きだけではなく、自分から相手に伝える働きも必要になります。
そうしてはじめて双方向性(インタラクティブ、interactive)が確保できます。
いわば、コミュニケーションの表と裏のような関係にあるのが、“質問する力”と“メッセージ性”だと言うことができるでしょう。
それでは、自分から相手に伝える“メッセージ性”を高める工夫はあるのでしょうか。
そう言いますと、何か目立てばよいのか、と思われるかもしれませんが、このコラムでは目立つという危険性も高い方法ではなく、自分を円滑に伝える方法を考えてみたいと思います。
ここで注目したいのがメラビアンの法則です。
これは、人の第一印象を心理学の手法から解き明かしたもので、多くの人は他人を瞬間的に判断しているというものです。
そして、瞬間的に判断する際の根拠は、外見(Visual)が55パーセント、話し方(Vocal)が38パーセントで、話の内容(Verbal)は7パーセントにすぎないことが実験から証明されています。
これは実に怖い話で、中身がどうであれ、人は他人を見た目で判断しているのです。そして、見た目を構成するのは表情や髪型、服装などであり、態度なのです。
仮に皆さんがどれほど優秀で人間性が豊かであったとしても、この最初の障壁でマイナスの印象を与えてしまえば、それはなかなか覆せないのです。
ですから、少なくても相手に見た目での不快感を与えない工夫が必要になります。汚らしい恰好、不遜な態度は禁句だと心得てください。
もちろん、だからといって、当節流行のリクルートスタイルがすべてよいと言っているのではありません。自分らしさや個性を表現することも大切ですが、それが許容範囲を超えないというのが重要なのです。
筆者がかつてマネージャーを務めていた職場でよく伝えていたのが、髪の毛は少々長くてもよいが清潔感を出すこと、原色を着てもよいがアウトサイダーには見えないようにすること、ピアスやタトゥー(刺青)は拒否反応を示す人が多いことを自覚すること、そういった話でした。
そうして考えますと、“メッセージ性”で注意すべき点は、他人にマイナスの感情を植え付けてしまうようなことを避けるということで、自分らしさや個性はその前提に立って考えた方がよろしいと言えます。
次に考えていただきたいのは、メラビアンの法則で言うところの話し方であり、話の内容です。
コミュニケーションは、互いの存在を認めなければ成り立ちません。そうしますと、話し方や話の内容では自分自身を主張することももちろんですが、その前提として相手の存在を認めていることを相手に伝えることが必要になります。
相手の存在を認めている、というメッセージを皆さんは発信しないといけないのです。
この行動をコーチング・スキルではアクノリッジメント(acknowledge、承認する)と表現しています。
要するに、「あなたの存在を私は認めていますよ、あなたがそこにいることを私は気にかけていますよ」というメッセージです。
その背景には、「人間は、他人に認められるのが一番嬉しいんですよ。お金を儲けたり、偉くなったりするのもいいかもしれないですけどね。人の役に立っている。認められているっていうのが一番気持ちいいことなんですよ(中鉢良治ソニー元社長)」という人間に共通する心理状態があります。
そして、それは大脳の働きを分析しますと、お金のような「もの」をもらったときに活性化する場所と、言葉や態度で褒められたときに活性化する場所は同じだ、という医学的データからもうなずける話です。
こうした人間の心理状態に着目すれば、相手の存在を認めていると相手に気付かせる話し方や話の内容がどれほど重要かおわかりいただけるでしょう。
問題はそれを具体的にどうするか、です。
これはいくつかの段階に分かれますが、少なくとも次のような皆さんの行動は相手の存在を認めていると相手に気付かせる一歩になるでしょう。
その第一は、挨拶です。
挨拶する、ということは、何を置いても相手の存在を認めている証明です。逆に、挨拶しないということは相手を無視していることの現われです。
ですので、子どもたちが学校で最初に教えられるルールは挨拶なのですが、どういう訳か人間は年齢を重ねるたびにこの単純なルールを忘れてしまうようです。特に、「どうも苦手だ」という相手に素直に元気で明るい挨拶をするのが億劫になったりします。これではいけません。苦手な人に対してほど元気で明るい挨拶を心がけると思わぬ成果が待っていたりするものです。
次に注意していただきたいことは、会話や素振りの中に相手への配慮を加えることです。お辞儀する角度、気遣う言葉、そうしたものを表現することは、挨拶の次の段階にあるアクノリッジメントと言えるでしょう。
例えば、「おはようございます」に加えて「昨日は遅くまで企画書で大変でしたね、できた企画書を見せてもらえますか」とか、「お疲れさまです」に加えて「今日のお客様との受け答えは丁寧で、とても感じがよかったよ」とか、そうしたほんの少しの気遣いを加えるだけで、アクノリッジメントは格段に深いものになるでしょう。
このように“メッセージ性”は、まずマイナスのメッセージにならないこと、相手の存在を認めることからはじまると言えるでしょう。
その意味で、前回のコラムにおける“質問する力”で言い忘れたことがあります。それは、相手の話を聞く際には(質問すれば答えが返ってきますので)、態度も含めて全身で「聴く」ということです。これができませんと、どんなに上手に質問されても真面目に答える気持ちにはなれないものです。
F第6話「質問する力」
皆さんが社会で活躍するに際し、とりわけ中小企業のような比較的小さな組織で活躍する場合は、他者を理解することが大変重要になってきます。組織が小さいほど他者と接触する機会が多く、より深いところで他者を理解することが組織と皆さんのプラスに働くからです。
コンピテンシー(行動特性)では、“対人理解力”というものがありまして、「言葉で表現されなくても、相手の思考や感情を察知する」という行動パターンを指しています。インテリジェンスが運営する転職サービスDODAが中途採用担当者を対象に実施した「中途採用者の選考に当たり重視している能力に関する調査」結果で、もっとも重視されている能力です。言い換えれば、「どのような仕事であっても、社内外を問わず、相手の言わんとすることや、言葉の裏にある本当のニーズ、相手の要求を理解する」能力を意味します。
しかし、こうしたコンピテンシーは「言葉で表現されなくても」という位、かなり奥深い能力ですので、一朝一夕に身に付くものではありません。
常にそういう意識を持って、他者を観察するところからはじめるしかないので、今の今で役に立つとは限りません。
そこでお勧めなのが、「言葉で表現された」中から他者を理解する能力、即ち“質問する力”です。
これは言葉という道具がありますから、何と言っても手掛かりは多いと言えます。しかし、実際に質問するとなると、多くの場合ではうまくいかないのです。
その理由は、まず第一に自分のための質問でしかなく、相手のための質問になっていないことが上げられます。
例えば、顧客との契約を任せている部下にその状況を確認しようとしましょう。自分のための質問は「契約は取れそうなのか」というものでしょう。これに対して相手のための質問は「確実に取るために僕からサポートできることはあるか」というものでしょう。
単に事実の確認をする、あるいは会社の(自分の)プラスになるように圧力をかけるための質問と、相手のサポートになれるような質問では、随分と答え方も変わってきます。
もう一つやってみますと、「なぜ今まで何もしなかったんだ」と問い詰めるよりは、「これから何をしていけばいいと思う」と促す方がはるかにプラスの影響を与えることができます。同じように「どうして相談に来なかったんだ」よりは、「何か手伝えることはないか」の方がよいに決まっています。
このように、自分のための質問から相手の質問へ変えることで、相手を理解する幅や深さは格段に大きくなると言えます。相手から自分自身を語りはじめるきっかけになる、という言い方もできるでしょう。
もう一つのこつが、段階を踏んだ質問です。
多くの場合、相手は自分自身が陥っている現状をきちんと理解しているとは限りません。むしろ、それが理解できていないがために、さまざまな困難や問題に直面していると言えるでしょう。
そうしますと、質問はまず相手に現状をきちんと理解できるようなものである必要があり、そこから順々に解決への道筋を辿るように構成することが望まれます。
これを順番で言えば、最初は状況質問です。相手の置かれている状況を確認し、それを通じて相手に自分自身の置かれている現状を認識していただくことになります。
ついで問題質問です。何が問題なのかを気付いていただくための誘導とでも言えるでしょう。
ここまで来ると、相手は「どうやら自分はまずい状況なんだ」と気付けます。
そうしたら、次はその現状から抜け出せる道筋を示唆する必要があります。「こうしたらどうなるでしょうね」という示唆質問です。
そして、最後はこうしたら解決できるという相互理解に至るための解決質問を用意すべきです。
このように、状況⇒問題⇒示唆⇒解決と段階を踏むことによって、相手に気付かせるという相互理解に欠かせないハードルを越えることができるのです。
このように、「質問する」というと簡単なようですが、整理をしてみますと、有効な質問を行うためには、何よりも相手のことを考える、そして段階を辿って相手に気付かせるというスキルが強く求められることになります。
そして、その基盤には「相手のことをより深く知りたい」「知ることによってより良好な関係が築ける」という価値観が重要になります。
どうか、皆さんも日常の中でこうした“質問する力”を養っていただければ、必ず社会に出て、中小企業で活躍する際に大きな武器になるでしょう。
そして、そのためには質より量、とにかく数をこなすことです。どんどんと周りに質問を、です。
また、以下のような最悪の質問を頭に置き、「あれよりはましだ」と思ってください。
上司A:「君に任せておいたあの仕事はどうなっているのか?」
部下B:「すみません、私も相手に働きかけてはいるのですが、なかなかよい返事がいただけなくて」
上司A:「それでどうするつもりなのか?」
部下B:「今日も訪問してみますが、昨日も訪問したばかりなので、嫌がられるとまずいのですが」
上司A「そんなあやふやなことでよいと思っているのか!」
C第5話「ドラッカーの成果をあげる習慣」
ピーター・ファーディナンド・ドラッカー(Peter Ferdinand Drucker)という経営学者がいます。社会生態学者を自称し、未来学者(フューチャリスト)とも呼ばれ、マネジメントという概念の発明者であり、20世紀の数多くの経営者に大きな影響を与えた“経営の神様”と言ってよい存在です。
ナチスの迫害を避けて、母国ドイツからイギリス、アメリカへと移住し、ゼネラルモーターズの経営を分析した「企業とは何か」を1946年に発表して以来、企業や組織の分析に止まらず、個人のプロフェッショナル成長に至るまで、まさに現代社会とその行く先を巨視的に透察した“知の巨人”と言えます。
特に日本では「もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら」が出版されるなど多くの支持を受け、著書の日本での売り上げはダイヤモンド社刊行分だけで累計400万部余りというほどです。
前回のコラムで「ピーター・ドラッカーの名言の一つに、『なされるべきことを考えることが成功の秘訣である。何をしたいかではないことに留意してほしい。』というのがあります。」とお伝えしました。
これは、彼の名著「経営者の条件」にある一説です。
経営者が成果を上げるには何をすべきなのかを、わかりやすい表現で伝えるものですが、同時に経営者に限らず、皆さんのようにこれから社会へ出てゆく、中小企業のように経営者との距離の近い組織に属する、そうした方々にも価値のあるセンテンスをいくつかご紹介したいと思います。
その最初は、「なされるべきことを考えることである、ドラッカーはくどいくらいに念を押す、なされるべきことである、なしたいことではない。」ということです。
成功するには自分のしたいことをするのではなく、求められている行動を起こしなさい、ということでもあります。
次は、「組織のことを考えることである。株主、従業員、取引先、経営者はいずれも大事である。しかし彼らのことを考える前に、社会の公器としての組織のことを考えなければならない。」ということです。
自分、そして自分のまわりのさまざまな利害関係者のことではなく、自分の属する組織、社会における存在としての組織が何をすべきかを考えることです。
これは実に示唆に富んだことで、身内に振り回されてはいけない、という警句でもあります。身内優先のインナー的な判断を避けなさい、という助言でもあります。
次は、「緻密なアクションプランを作ることである。経営者とは行動すべき者である。そのためには、計画しなければならない。しかし、状況が変化すれば、ただちに変更していく。こうして、日常から事業の展開について、シミュレーションを行っておく。」ということです。
どう行動するのかを、5W1Hに基づいて計画しておく、そして状況の変化にあわせて計画は変更され、さらに日々この先の展開を予想しなければならない、と書きますと面倒くさそうですが、実はビジネスに集中しているとできるものなのです。ただし、思い込みを排する客観性は欠かせません。
次は、「意思決定を行うことである。もちろん、意思決定は定期的に見直していく必要がある。」ということです。
いわゆるデシジョンメーキング(decision making、意思を決める)ですが、人の多くは自分の見たい未来しか見ないという傾向を考えますと、当然ですが多くの人に嫌われる決断をする勇気や思い切りもその中には含まれます。そして、こうした決断のほとんどは孤独な中で行われます。自分の人生は自分で決めるしかない、というようにも言えるかもしれません。
次は、「コミュニケーションを行うことである。特にアクションプランについて、コミュニケーションを行わなければならない。」ということです。
意思決定に基づくアクションプランは、関係者に共有されていなければ何の意味もありません。組織の全員が理解し、共有されることがポイントです。そのためには、コミュニケーションが不可欠になります。ここに優れた経営者の多くが現場で働く人たちとの出会いを大切にする所以(ゆえん)があります。
次は、「機会に焦点を合わせることである。問題の処理が成果をもたらすわけではない。成果は機会がもたらす。」ということです。
これはちょっとややこしいかもしれませんが、要はタイミングが重要なのです。六日の菖蒲、十日の菊では役に立ちません(菖蒲の節句が終わったら菖蒲は不要、菊の節句が終わったら菊は不要なのです)。レスポンスが大切なようにタイミングも大切で、幸運の女神には前髪しかないのです(チャンスは後からでは掴めない)。
次は、「会議の生産性を上げることである。会議に出ているか、仕事をしているかである。会議に出ていたのでは仕事はできない。」ということです。
会議は基本的にノンプロフィット(直接の利益を産まない)ですので、会議がそうしたものであればあるほど生産的に運営されないと無駄が増幅します。時には会議のための会議が横行するのです(何の行動につながるかではなく、単に打ち合わせた、というアリバイを作るための会議)。
次は、「『私は』ではなく『われわれは』を考えることである。」ということです。
当然のことですが、組織は独りでは成立しませんし、組織としての行動でなければ成果につながりません。
そして、何よりもドラッカーはこうした行動を突然大胆にするのではなく、日々の習慣として行うよう推奨しています。
「成果をあげるには、性格、強み、弱み、価値観、信条はいかようであってもよい。なされるべきことをなすだけでよい。成果をあげることは、習慣である。したがって、他の習慣と同じように身につけることのできるものである。そして身につけなければならないものである。」
いかがでしょうか、これは経営者へ送るドラッカーの遺言のようなものですが(94歳の時)、皆さんが社会を生きてゆくに際し、中小企業のように経営者との距離が近い組織で生きてゆくに際し、いろいろな示唆を与えてくれるのではないでしょうか。
C第4話「コア・コンピタンス②」
第2回目に“コア・コンピタンス(Core competence)”のお話を差し上げました。競合他社を圧倒的に上まわるレベルの能力、あるいは競合他社に真似できない核となる能力というような意味です。そして、ベネッセの顧客情報流出という事件から、ベネッセは「通信教育の中身」というコア・コンピタンスは重視したが、もう一つの「顧客管理」の方をおろそかにしていたのではないか、という疑問を呈しました。
先日、酷い悲劇が起きてしまいました。ロシアとEUが政治的、経済的な綱引きを続けているウクライナ、その上空でマレーシア航空の旅客機がミサイルで撃墜される、という航空史上最悪の事件です。
このコラムは、その犯人が誰かを問うものではありません。
問題にしたいのは、マレーシア航空が何故この悲劇を回避できなかったのか、にあります。
特に飛行禁止区域に指定されていない限り(指定されていれば飛行できない)、こうした紛争地域の上空を飛行するのは、その安全性を航空会社が認識しているからだと言えます。
今回の場合は、国際民間航空機関(ICAO)がウクライナ南部を回避するように求めていましたが、事故現場のウクライナ東部はそこには入っていませんでした。また、ウクライナ政府が高度9354メートル以下の飛行を禁止していたそうですが、事故機は高度1万メートルを飛行していました。低高度ではありましたが、ウクライナ空軍の輸送機が撃墜される事件も数日前に起こったばかりです。
この辺は何とも言いにくいことですが、明らかに「危険」とは断定できないが、「安全」と太鼓判を押せるような状況にはなかったと言えます。実際、アジア太平洋地域の航空各社は安全を懸念して数か月前からウクライナ上空の飛行を避けていたのです。
そうしますと、禁止ではないものの安全とも言いにくいウクライナ東部上空をマレーシア航空のみが飛行を続けていたことになります。
これが「何故か」なのです。
ここで、航空会社のコア・コンピテンシーを考えてみましょう。
会社ごとに格安運賃であったり、高品質であったり、接客マナーであったり、定時運行であったり、利便性であったりするでしょう。
しかし、もっとも基本となるものが「安全」であることは言うまでもありません。
「安全」が担保されない飛行機に乗るのはかなり勇気のいることでしょう。
ですので、世界の航空会社の多くは無事故、あるいは事故の起きにくさを重要視しているのです。ちなみに、国際航空運送協会(IATA)によると、2008年の100万飛行あたりの死亡事故の発生率は世界の平均で0.81。しかし、日本が1986年以降ゼロを続け、欧米や南アジアが0.5前後なのに対し、アフリカは2.12、中南米は2.55、旧ソ連諸国は6.43にものぼり、地域ごと、あるいは航空会社ごとにばらつきがあるのが実情です。でも、事故率の高い航空会社を選ぶのは、「それに乗るしかない」という場合がほとんどであって、選択が可能であれば誰でも安全を選ぶでしょう。
では、どうしてマレーシア航空というナショナル・フラッグ(国を代表する航空会社)が「安全」というコア・コンピテンシーを毀損しかねない飛行をしたのか、です。
そこにはLCC(格安航空会社)との競争に敗れ、過去の栄光にしがみ続けるだけの旧態然とした国営企業の末路があります。
このマレーシア航空、赤字路線は4割にものぼり、昨年の赤字が400億円弱、ここ3年間の累積赤字は1,300億円に達しています。経営の立て直しを図るには余剰人員や人件費水準の削減が欠かせませんが、国営企業特有の労働組合の政治力でそれも難しいとのこと。コストカットを図ろうにも縁故(コネ)が幅を利かせているので、資材の調達も合理化できないありさまです。
加えて、マレーシア航空が地盤とする東南アジアの路線にはLCCの旗頭エアアジアが圧倒的な低コストを武器に台頭していますから、まさに内憂外患。今年の3月には239人乗りの北京行き航空機が行方不明になる事件まで起こったのですから、大株主であるマレーシア政府のナジブ首相が「もう救えない状況だ」と嘆いたほどです。
さて、ここで本題に戻りましょう。禁止ではないものの安全とも言いにくいウクライナ東部上空をマレーシア航空のみが飛行を続けていたのは何故か、です。
端的に言いますと、「今回の現場上空はヨーロッパからマレーシアに向けて、最も効率的に燃費も少なくて、飛行時間も短いと。そういう、経済的に優れたルート。」ということなのです。要するに、マレーシア航空は燃費を節約し、コストを抑えるために、ウクライナ東部の上空を飛行したのです、
ここにどうしようもない悲劇があると言えるでしょう。
本来、経営を立て直すためには、余剰人員であるとか、人件費水準であるとか、調達資材のコスト削減であるとか、身を切る努力をしなければなりません。
しかし、マレーシア航空はそうした努力をする代わりに、「安全」というコア・コンピテンシーを毀損してまで燃費を節約したのです。
ピーター・ドラッカーの名言の一つに、「なされるべきことを考えることが成功の秘訣である。何をしたいかではないことに留意してほしい。」というのがあります。
成功するには自分のしたいことをするのではなく、求められている行動を起こしなさい、ということです。
同じような意味で、身内の事情を優先すれば失敗は目の先です。優先すべきは顧客であり、身内ではないのですから。まさに、顧客から求められている行動を起こすことが優先されなければなりません。
皆さんも何が皆さんに求められているのかをよく自問し、その答えを行動へ移してみてください。そして、自分や身内の事情を優先するのはできるだけ慎まれることをお薦めします。
F第3話「評判は大切です」
中国でよく使われる表現の一つに、“飲水不忘掘井人(水を飲むときには井戸を掘った人を忘れない)”というのがあります。新しくものをはじめること、先鞭をつけることは難しく、それに続くことは容易なのですが、ついつい私たちはそうした先人を忘れがちになる、という自戒を込めた諺(ことわざ)と言えます。
では、そうした先人の苦労をすっかり忘れ、その苦労の上に成り立っている今日の繁栄や成果を貪っている人たちのことはどう言われるのでしょうか。
そこはさすが中国、漢字の国です。ちゃんと用意されているのがたまりませんね。
それは、“忘八蛋(ワンパータン)”と言いまして、中国では最大級の侮蔑を現わすものです。
“忘八”とはスッポンのことで、人が守るべき八つの道徳規範を忘れた奴、という意味です。“蛋”はピータンのタンですから、二つつなげると忘八蛋(ワンパータン)。
人でなし、恩知らずといった感じでしょうかね。
さて、人の評価はなかなか難しいもので、ピタッと真価を見定めることは至難の業です。
とはいえ、人はさまざまに評価され、その評価は世の中に流布されます。
ここが怖いところなのです。
人の口に戸は立てられぬ、とは実にうまい表現です。
例えば、信州大学生は長野県では極めて高い評価を得ています。その中の誰がどうだ、ではなく、信州大学生という一括りで評価されるのです。
それは、長い間、おそらく松本高校(旧制)、上田蚕糸専門学校、長野師範学校など、信州大学の母体となった各校の時代から、営々と積み重ねられてきた信州大学生という一種のブランドが背景にあるのだと思うのです。
そう考えてみますと、一人一人の大学生、あるいは大学院生が自分自身の評価を得る、というのはなかなか難しいと言えます。
まず、時間がありません。大学生活はたかだか4年、修士まで進んでも6年、この短い時間の中で評価されるだけの実績を残すのは大変です。
次に、信州大学生という括りの中のワンオブゼムから抜け出すのも容易ではありません。信州大学の〇〇さん、という表現の中で〇〇さんにウェイトがかかるのは稀であり、信州大学にウェイトがかかるのが通常です。そこからどう抜け出して、自分自身を評価していただくか、という難しさがあります。
しかし、そうは言っても自分の評価を上げることは大変重要です。
そのためにコア・コンピタンスを磨かないといけませんよ、と前回お伝えしたところです。競争関係にある他者との比較において、他者には真似が難しく、特定の企業に限らない汎用性があって、企業へ利益をもたらす自分自身の能力とはいったい何だろうか、と自問するところからはじめていただけるとよろしいと思います。
また、昨年度のコラムの中で、5月17日~19日の動機シリーズ、6月15日~18日のコンピテンシーシリーズ、7月15日~8月20日のスキルシリーズは、そうした能力を考える上での基礎的な理解に役立つと思います。
ぜひ、自分自身の能力を自問自答し、そして、その能力を伸ばすように頑張っていただきたいと願います。
もう一つ重要なことが「評判」です。
世の中に流布される評価と考えてください。同時にそれは、評価は難しいという現実を考えれば、評判が正しい評価とは限らないのも事実です。時としては、実体とかけ離れた評価が独り歩きする危険性すら存在します。ですから、怖いのです。
仮に評判が真の評価とは異なるが、世の中に広まってゆく情報だと考えるならば、やはりよい評判を得ることが大切になります。
その際、少なくともこれをしておくとプラスに働くであろうと思われる行動があります。
その一つは、レスポンスを速くすることです。
あの湾岸戦争の際、日本は1兆5千億円の支援を行いましたが、そのタイミングが時機を逸していて、トゥー・スモール(少なすぎ)トゥー・レイト(遅すぎ)という批判を受けたのは記憶に新しいところです。支援の是非はさておき、そのレスポンスの遅さは致命傷となったのです。
これとまったく同じことで、遅いレスポンスは評判を傷つけます。仮に、回答を出すのが難しいことであっても、まずはレスポンスを速くして「今検討しているところです」とでもメッセージを送ることが重要です。音信不通ほど評判を落とすものはありません。
もう一つは、御礼を忘れないことです。
冒頭の“飲水不忘掘井人(水を飲むときには井戸を掘った人を忘れない)”のとおりで、
お世話になった人への御礼は欠かさない、これが重要です。
また、お世話になったことを周りの人たちにも伝えることです。
御礼という直接のメッセージ、周りの人たちへ伝える間接のメッセージ、このどちらも相手にとっては気分のよくなる話です。
逆にお世話になってもなしのつぶてでは、恩知らず=忘八蛋(ワンパータン)と言われても致し方ありません。
レスポンスを速く、御礼を忘れずに、そうすれば皆さんの評判は少なくとも悪くなることはないのです。
ぜひ、機会を捉えて行動へ移してみてください。
C第2話「コア・コンピタンス」
“コア・コンピタンス”という経営用語があります。Core competence、競合他社を圧倒的に上まわるレベルの能力、あるいは競合他社に真似できない核となる能力と定義されます。そこにおいては、①顧客に利益をもたらす能力、②競合相手に真似されにくい能力、③複数の商品や市場に推進できる能力という条件をクリアすることが求められます。要するに、競争関係にある他者との比較において、他者には真似が難しく、特定のクライアントに限らない汎用性があって、クライアントへ利益をもたらす自分自身の能力、とでも言い換えることができるでしょう。
企業活動においては、こうしたコア・コンピタンスを見極め、それをさらに伸ばし、強い競争力を築くことが極めて重要です。
例えば、トヨタ自動車では「カイゼン」を軸にした、低コストで高品質の自動車を作れる、というコア・コンピタンスがあります。
例えば、ホンダでは芝刈り機から除雪機、オートバイから自動車まで幅広く、高性能のエンジンを作れる、というコア・コンピタンスがあります。
同じ自動車メーカーと言っても、それぞれ異なるコア・コンピタンスを磨いて競争していることになります。リーズナブルで故障が少なく信頼性が高いトヨタの車、高回転のエンジンでスピード感のある個性的なホンダの車、みたいな競争です。
トヨタとホンダのどちらが最終勝利をつかむのかはわかりませんが、少なくともこの50年近い世界の自動車市場の中で、お互いにコア・コンピタンスを磨きながら、ここまでの成長を成し遂げてきたツワモノと言えるでしょう。
さて、今回、現代日本の情報化社会を震撼させる事件が起こりました。最大で2,000万件を超える個人情報が流出した可能性がある、ベネッセ個人情報流出事件です。
事件は、6月に入って、ベネッセの顧客に対し、別の通信教育を行う会社からのダイレクトメールが届くようになり、そこではベネッセのみに登録した個人情報(お子さんの情報)が使われていたことから、ベネッセから個人情報が漏洩しているのではないかという問い合わせが急増したことにより発覚したものです。
こうした個人情報の流出はこれまでも数多く発生してきましたが、今回の事件はその数の多さ、流出したのが主に子どもの情報であったことから、経済産業省は今回の事件を重く見て、ベネッセコーポレーションに対し「個人情報保護法に基づき、本件に係る事実関係などについての詳細を書面にて提出するよう」報告を指示するという異例な対応を迫られることになりました(ベネッセの対応はhttp://www.benesse.co.jp/bcinfo/)。
情報化社会の進展とともに、個人情報の利用価値は著しく肥大化し、それに伴ってこうした流出という危険をどう抑えるか、という問題は今や一企業の信用云々を超えて、社会問題にまで至っていると言えるかもしれません。
しかし、事件の構造は実にお粗末なものでした。
ベネッセの顧客情報の管理を子会社に請け負わせ、その子会社が管理業務を外部企業へ再委託し、再委託先では派遣社員を使い、そこから情報が流出した、ということです。
そうしますと、ベネッセの顧客情報の管理はベネッセ⇒子会社⇒外部企業⇒派遣という四段重ねの下請け構造だったのです。
顧客を囲い込むというビズネスモデルで最も重要視すべきこと、それは顧客の利益をいかに守るか、です。
その利益の中に顧客情報が入ることは言うまでもありません。
でありながら、ベネッセはそれを子会社に委ね、子会社は外部企業へ委ね、外部企業は派遣社員へ委ねていたのです。
しかし、「こういう構造でアイデンティティが働く」でしょうか。
一般的にモラルはアイデンティティと比例関係にあると言われます。組織へのアイデンティティが強ければ強いほど、組織が定めるモラルは守られます。今回の事件では、アイデンティティの希薄さがモラルの欠如を産んだ、と言ってもよいでしょう。
この種の勘違いは、とかく本業と位置付けている部門と、本業外と位置付けている部門との間に越えられない格差を設けているとよく起こることです。
こういった格差は、必ずより低価格へと誘導されます。
本業以外だからコストダウンが至上命題となり、いつしかアイデンティティやモラルは二の次になってしまうのです。例えば、データセンターしかり、ヘルプデスクしかりです。
本来は顧客と直に向き合う、極めて重要な部門であるにも関わらず、昔からの本業ではない、というだけの経過でいつしか周辺化され、越えられない格差を産んでしまう。
そこにこうした事件の陥穽があると言えます。
言い方を変えれば、ベネッセという日本有数の通信教育企業にとって、何がコア・コンピタンスだったのか、ということです。
もちろん、通信教育の中身である教材の品質、教え方の品質が重要な位置を占めることは当然です。しかし、同時に通信教育というビジネスモデルにおいては顧客管理が極めて重要であり、顧客管理の基盤である個人情報が根っ子になると言えます。
そうして考えますと、ベネッセにとってのコア・コンピタンスは「通信教育の中身」であり、「顧客管理」であると規定してよろしいでしょう。
しかし、ベネッセは昔からの本業(通信教育の中身)だけを中心化し、顧客管理というもう一つのコア・コンピタンスを周辺化し、四段重ねのアイデンティティやモラルが希薄となりがちな下請け構造に任せっぱなしにしていたのです。
その意味では、ベネッセの旧経営陣は経営者失格と断罪されても致し方ないと言えるでしょう(実際に副会長と最高情報責任者が引責辞任)。
さて、こうしたコア・コンピタンスは皆さん自身にも通用することです。皆さんがこれから社会に出てゆく際に、いわば企業というクライアントへ皆さん自身をセールスしなければならない訳ですが、その際に自分自身のコア・コンピタンスとは何なのか、ここにぜひ想いを致していただければと思います。
競争関係にある他者との比較において、他者には真似が難しく、特定の企業に限らない汎用性があって、企業へ利益をもたらす自分自身の能力とはいったい何なんだろうか、と自問するところから、皆さんの社会参加のレースがはじまるとも言えるのですから。
F第1話「はじめに~挑戦する心~」
このコラムは、昨年度に引き続き、「地域中小企業の人材確保・定着支援事業」の一環としてお届けするものです。この事業は、中小企業や小規模事業者が地域で学んだ大学生などを地域において円滑に採用でき、かつ定着させるための自立的な仕組みを整備することを目的としています。そして、そうした若手人材を継続的に確保し、中核人材として育成することで、中小企業や小規模事業者の経営力強化を進めようとしています。
このため、このコラムでは①これから社会に参加する皆さんに「働く」、あるいは「ビジネス」ということがどういったものなのかを知っていただく、②中小企業や小規模事業者で働くために重要な知識やスキル、あるいは“社会人基礎力”や一般常識を身につけていただく、③中小企業や小規模事業者の海外進出や市場開拓において必要とされるさまざまな国や地域の情報や文化風土などの基盤的な知見を知っていただく、そしてこれからの日本を背負う皆さんに求められるリベラル・アーツを身に付けていただくことを大きな目的としています。また、このコラムを書くに際して、日本経済新聞とウィキペディア(Wikipedia、ウィキメディア財団が運営しているインターネット百科事典)から多くの情報を得ていることをあらかじめお伝えいたします。
なお、このコラムへの問い合わせや質問、意見、感想を歓迎します。必ず、コラムの日付やタイトルをお示しいただき、フルネームで<yoshida@nojuan.com>までメール送信をお願いします。さほど時間をおかずにご回答差し上げますが、わかること、できることと、わからないこと、できないことがありますので、その点はあらかじめお許しください。
それでは、第1話として「挑戦する心」の話からはじめることとしましょう。
鈴木敏文さんという経営者がいます。イトーヨーカ堂の、セブンイレブンの経営者です。「単品管理」という商品管理の概念を普及させ(情報化された今では当たり前ですが)、コンビニエンスストアという業態を日本へ導入した小売業のレジェンドです。
その彼がこんな発言をしています。
「新しいことをやるときに経験者なんていない。潜在能力を引き出せばいい。」
これはすごく名言だと思うのです。
新しいことをやるときには、既にそれを経験した人なんているはずがありません。何せ新しいのですから。
これまでの経験を活かすことはできません。何せ新しいのですから。
彼はこうした考え方を大切にして、次々と新しいビジネスを開拓し続けてきました。皆さんがご存知のものだけでも、24時間営業、コンビニ銀行、オムニチャネル(ネットと実店舗の融合サービス)、実に枚挙に暇がありません。
そして、筆者が凄いと思うのは、これほどの成功を積み重ねてきても、決して成功体験に縛られない姿勢なのです。例えば、情報管理では先んじてシステム化を成し遂げているにもかかわらず、時として「データを見るな」という指示が出されると言います。それは、「データ」に頼り過ぎずに、実際の現場で自分の肌で感じることを忘れず、よりプリミティブ(根源的)なところで顧客の動きを感じろ、という彼なりのメッセージなのでしょう。
そうして見ますと、これから社会に出る皆さんはそもそもまったくの未経験者です。若干、インターンシップやアルバイトでその業界の入り口を探ったことはあるかもしれませんが、他人さまに「これが私の経験です」と言えるほどの経験値や成功体験があるはずもありません。まさに「新しいことへ挑戦する」しかないのです。
そのとき求められるものは、薄っぺらな経験や若干の専門知識を振り回すことではなく、もっと自分の根っ子のところでビジネス、あるいは仕事の現場と素直に向き合い、自分の持っている潜在能力を振り絞ることではないかと思うのです。
そして、潜在能力を振り絞るには「どうにかやりこなそう(やりすごそう)」というHow to型の行動ではなく、「それが求められる原因は何か」を探るWhy型の思索と、「解答が見つかるまであきらめずに試みる」トライ&エラー型(trial and error)の粘りが必要ではないかとも思うのです。
昨年度も5月10日付けの第10話で「挑戦する」をお伝えしました。そのとき、「こうした冒険家たちの旅を考えますと、私たちが挑戦しようとする冒険などは、ほんのささやかなものだと思うのです」と、皆さんの旅立ちをオーストロネシアの人々の大海原への挑戦になぞらえてみました。今年度のシリーズも、皆さんの社会への挑戦という極めて身近で具体的なテーマから取り上げてみました。
さて、新しいことへの挑戦、即ち皆さんが社会に出る、という際に、もう一つお送りしておく言葉があります。
それは、「怯えず怖れよ」ということです。
怯えは立ちすくむことです。
怖れは未知のものへの畏敬です。
これは根本的に違う意味と言えます。
皆さんが未知の世界を怖れることは当然で、怖れないようであればそれは無謀と言えます。未知であることへの畏敬の念(怖れ敬い、慎みを持つこと)が無ければ、かなりの確率で失敗しそうです。行動の前に十分なリサーチを、みたいな感じでしょうか。
しかし、かと言って、怯えて立ちすくんでいては何ごともはじまりません。それは単なるビビリでしかありません。
怖れることによって、より深い層まで知ろうとする、これをある人は「怖れとは、意識のドアをノックするメッセンジャーである」と表現していますが、なかなか上手い言い方です。まさに、怖れることによって、私たちの思索がはじまるとも言えるからです。
これに対して、怯えは思索を閉ざすメッセンジャーのようなものとも言えるでしょう。
どうか、皆さんも「怯えずに怖れて」いただければと願っています。