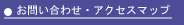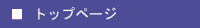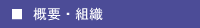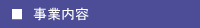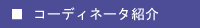過去の記事
B-D番外編「パレスチナとヨルダン」
番外編の第10話でお伝えしたイスラエル、その建国と同時に生まれた双生児がパレスチナです。このパレスチナはシリアの南部にあたり、古くは“カナン”と呼ばれ、旧約聖書では神がユダヤ人へ与えた約束の地でもありました。しかし、ローマ帝国によりユダヤ人がディアスポラで世界各地へと離散する時代に入り、パレスチナは2,000年近くもアラブ人の住む土地、イスラムの土地へと変わっていたのです。
そうしたパレスチナが1917年のイギリスのバルフォア宣言によりユダヤ人のナショナルホーム(居住地)として認められてから、世界中からユダヤ人が移住をはじめ、とうとう1948年にイスラエル建国を迎えました。
事態を危ぶんだ国連の仲裁で、パレスチナはユダヤ人居住地とアラブ人居住地、そして国連の管轄するエルサレムに分割されることになっていましたが、アラブ社会とイスラエルの四度にわたる戦争でイスラエルが勝利を収めたこともあり、イスラエルはパレスチナのほとんどを自らの支配下に置き、アラブ人には内陸部のヨルダン川西岸地区と海岸部のガザ地区、イスラエルの領土の30%に満たない土地と330万人ほどの人口が残されたに過ぎません。しかも、ヨルダン川西岸地区にはユダヤ人の入植地が数多く作られ、イスラエルの支配権が及ばない地域はそのうちのわずか40%に過ぎないのです。
こうした状況の中、パレスチナに住んでいたアラブ人の多くは約600万人もの難民となり、レバノンやヨルダンをはじめとする周辺のアラブ国家へと逃れていくことになりました。そして、過酷な難民生活やアラブ人居住地での厳しい生活は多くのアラブ人をイスラエルへの抵抗運動へ駆り立て、今でも続くテロの連鎖となりました。
現在はヨルダン川西岸地区とガザ地区をあわせてパレスチナ自治政府という組織が作られていますが、隣接するイスラエルからのさまざまな圧迫(経済封鎖や越境攻撃など)もあり、ガザ地区ではハマース(イスラム主義政党でイスラエルとの武力闘争を標榜しています)が、ヨルダン川西岸地区ではファタファ(世俗主義政党で穏健的)が、それぞれに支配権を握る分裂状態に陥っています。
現在、アメリカのケリー国務長官の手により、中東和平交渉が再開され、イスラエル側とパレスチナ側の接触がはじまっているようですが、シリアの内戦が激しさを増す中、どの程度の成果が生まれるか、行く先は予断を許さないようです。既にイスラエル建国から70年近くも経過し、パレスチナの土地で世代を重ねたユダヤ人、パレスチナの土地を離れて世代を重ねたアラブ人がかなりの数に達しており、それぞれの存在を否定できない以上、何らかの合意形成が望まれますが、同様に世代を重ねた殺戮と報復の繰り返しが大きな障害となっているのかもしれません。
そして、そのパレスチナの東に接するのがヨルダン、1946年に番外編の第13話でお伝えしたハンマドの血筋につながるアラビア半島のハシーム家を王座に抱く砂漠の王国です。
皆さんが「インディ・ジョーンズ/最後の聖戦」でご覧になったあの遺跡、聖杯が安置されている遺跡、あれはガザ地区の東にあるペトラ遺跡で、古くから砂漠を移動するキャラバン隊の中継基地として栄えたところです。
この遺跡からおわかりように、ヨルダンはアジアと地中海世界をつなぐ交易の要衝としての歴史を持っており、そうした周辺諸国との関わりは今でも続いており、イラク戦争、あるいはシリア内戦などの戦火が激しくなるたびに数多くの難民が流入し、また、国際支援のベースキャンプとしての役割を果たすなど、西アジアのハブのような機能も兼ね備えています。そういう意味では、ヨルダンの政情は周辺諸国の政情が直接影響するという意味では、ヨルダンは西アジアを構成する一つのパーツだと言えるでしょう。
B-D番外編「シリアとレバノン」
いったいどうなるのだろうか、と心配になるシリアの内戦、発生から既に3年を経過し、10万人を超える死者と200万人を超える難民を産み、今もアサド政権とそれに対抗する諸勢力の争いが続き、しかも反アサド勢力は欧米派から親イラン派、アル・カイーダの影響を受けるイスラム過激派などに四分五裂というありさまです。シリアはメソポタミアから分けられてフランスの支配下に置かれ、期待された「石油」資源には恵まれなかったことからフランスも手を引き、1946年の独立以降はソビエトロシアの陣営に属し、西アジアにおけるロシアの代理人として影響力を培うことになります。このロシアとの長いつながりは、国際的に孤立するアサド政権をロシアとイランが懸命に支えるという図式を描く要因となっています(イランは反米という立場からの支援)。
このようにシリアは「冷戦の申し子」とも言える素性を持ち、1948年のイスラエル建国からはその直接の隣国として常にイスラエルとの緊張状態が続き、国土の一部ゴラン高原は今もイスラエル軍が占領するという異常な政治状況の中にあります。
そして、メソポタミアの古い歴史がもたらす複雑な民族構成は、人口の70%を占めるスンナ派アラブ人をはじめ、シーア派から分かれたアラウィー派(アサド政権の母体)、同じくドゥルーズ派(レバノンで大きな力を持つ)、キリスト教ではローマ・カトリックやギリシア正教と別れた“オリエンタル・オーソドック”のシリア正教会、東方正教会(ギリシア正教)、ローマ・カトリックの教義を受け容れたマロン派、そこにイエス・キリストも話したであろうアラム語を今に伝えるアッシリア人、コーカサス系やチュルク系の人びとなど、まさに「民族の万華鏡」とも言える多様性を示しています。
こうしたロシアとの緊密な関係、イスラエルとの間断ない緊張状態、国内の複雑な民族構成は、軍事力を背景とする強権的な政治体制を招き、その頂点に登りつめたハーフィズ・アル=アサド(アラブの獅子と呼ばれた)は30年にわたる独裁政権を築き上げ、さらにその政権を次男のバッシャール・ハーフィズ・アル=アサドが2000年に引き継ぎましたが、2011年からは終わりの見えない内戦に突入しているということです。
こうしたシリアですが、古くから西アジア交易の要衝にあり、人口2,000万人を抱え、周辺の石油資源の製品化にも取り組んでいますが、いずれにせよ内戦が終わらないかぎり、手の施しようがないのが実情です。
そして、シリアからフランスの手で分けられたのが、地中海に面するレバノンです。
イラクやシリアも「人工」国家の側面を持ちますが、レバノンこそはまったくフランスの手により「人工」的に作られた積木細工のような国です。
国会議員は当時の人口比率からマロン派キリスト教徒34人、スンナ派イスラム教徒27人、シーア派イスラム教徒27人などと決められ、大統領はマロン派、首相はスンナ派、国会議長はシーア派に割り振り、しかもこの民族バランスをいじれば内戦を招くことから、人口の基礎となる国勢調査はそれ以降実施されないという現状です。
それに加えてイスラエルと隣接するため、大量のパレスチナ難民が流入し、この一大勢力が従来の民族バランスに影響を与え、1975年にはじまるレバノン内戦は、その後もイスラエルの侵攻、シリアの介入、イランの支援を受けたヒズボラ(シーア派武装組織、神の党という意味)の勢力拡大など、平穏な日々は一日も無いほどの動乱が今日も続いているのです。
しかし、こうした国家体制が無いにも等しいアナーキーな状況は、アンダーマネーの流入、宝飾品の加工、密輸などの「経済活性化」をもたらし、一時首都ベイルートは「中東のパリ」と呼ばれるほどの繁栄を謳歌したのです。また、こうした国内の不安定な状況は、多くのレバノン人の海外進出を招き、日産のカルロス・ゴーン、アメリカの消費者運動家ラルフ・ネーダー、甘い歌声で“ダイアナ”をヒットさせたポール・アンカ、名優キアヌ・リーブスなどが有名です。
いかがでしょうか、国際社会のさまざまな思惑の中で生まれた「人工」の国家、シリアとレバノン、彼らがその成り立ちの由縁を今でも背負い、苦悩を続けていることを認識していただきたいと思います。
B-D番外編「オマーンとイエメン」
サウジアラビア、ペルシア湾と続きましたので、ここでアラビア半島の南端に位置するオマーンとイエメンを紹介し、イスラム社会の南部を終わりたいと思います。つい先ごろ、安部首相が訪問したオマーン、私たちには馴染みの薄い国です。
人口は300万人弱、シーア派から分かれたイバード派が多くを占め、国王はムハンマドにつながる血筋を称しています。
ペルシア湾の出口にあって石油ルートの要衝ホルムズ海峡を領海に抱える地政学的な位置、豊富な石油資源による一人あたり25,000ドル近いGDP(韓国並み)という国力を誇ることから、近年、イスラム社会での存在価値を増している国です。
このオマーンは17世紀にはインド洋の支配権をポルトガルと争って勝利し、東はパキスタンの港を押さえ、西は東アフリカを支配下に置き、オマーン海洋帝国と呼ばれる強大な「海の王国」を築いたのです。この勢いは19世紀にまで続くこととなり、「海の王国」はタンザニアの貿易港ザンジバルを中心として、象牙・香辛料・奴隷の交易で繁栄を極め、東アフリカの共通言語となっているスワヒリ語は、土着のバンツー系言語と、オマーン商人がもたらしたアラビア語が混交してできあがったほどです。
オマーンの現状は、こうした「海の王国」からペルシア湾の要衝、インド洋交易から石油資源へと形を変えていますが、オイルマネーの国民への還元と「開かれた王制」を目指して統治体制の安定化を図り、国際的には親英米反イランの立ち位置にあります。
そのオマーンの西に位置するのが古い歴史を今に伝えるイエメンです。
ギリシア人には「幸福なアラビア(Arabia a Felix)」と呼ばれ、旧約聖書ではソロモン王を訪問するシバの女王の治めた地、“乳香”という砂漠の木々から採れる貴重な香料は多くの富をもたらし(今でもキリスト教の教会では香炉で乳香を焚きます)、当時はアラビア半島から海を隔てたエチオピアまで勢力下に置いていたほどです。
こうしたイエメンの過去の栄光は、世界遺産に登録されているサヌアの旧市街(世界最古の町、砂漠の摩天楼と呼ばれる)などに残されており、成人男性が身に付けるジャンビーア(半月形の短剣)に代表される古いイスラム社会の伝統はシャリーア(イスラム法)に基づく生活とあわせ、非常にエキゾチックな風土を醸し出しています。
近代に入ってからは、汎アラブ主義的な(周辺のイスラム社会との関係を重視する)北イエメンと、ソビエトロシアの影響下にある南イエメンに分かれて長い内戦を続けましたが、隣国サウジアラビアの後押しを受けた北イエメンが主導権を握る形で統一を果たしました。そして、サレーハ大統領が20年以上も権力を握ってきましたが、2011年の「アラブの春」で退陣し、現在もサウジアラビアの支援を受けた政権が成立しています。
経済的にもサウジアラビアへの出稼ぎが多くを占め、近年、南部で石油と天然ガスが発見され、新しい産業として期待されていますが、貧富の差や高い失業率は政治の不安定化を招いており、ウサマ・ビン・ラーデンの一族がイエメン出身という背景もあって「アラビア半島のアル・カーイダ」をはじめとする反政府勢力も活動を活発化しています。
いかがでしょうか、オマーンといい、イエメンといい、私たちからは遠い世界ですが、一つにはイスラム社会を構成する重要な国々であること、一つには日本の命運を握るペルシア湾やホルムズ海峡に影響を与える国々であること、一つには「モカ」で有名なコーヒーやナツメヤシの名産地であり、人類がアフリカを離れて世界中に拡がった際の重要な移動ルートであることなどから、皆さんの記憶の中に留めていただきたいと思うのです。
B-D番外編「ペルシア湾岸の国々」
西アジアには小さな国々が連なる地域があります。それがペルシア湾の西側、対岸にイラン、湾奥にイラク、背後にサウジアラビアと、西アジアの大国に囲まれた地域です。古くはメソポタミアと世界を結ぶ海上交通の要衝であり、近くは天然真珠の宝庫として知られ、御木本パール(日本の養殖真珠)に駆逐された1940年代以降は「石油」に依存する国々です。
一番奥からクウェート、バーレーン、カタール、そしてUAE(アラブ首長く連邦)と、まるで真珠の連なるように小さな国々が並んでいます。これらの国々は、いずれもアラブ系の首長が治める部族社会でしたが、ありあまる「石油」の富が社会を大きく変えています。
クウェートは人口300万人、世界第4位の原油埋蔵量を誇り、およそ8世帯に1世帯は100万ドル以上の資産を持つという超富裕国家でもあることから、かつてはイラクの宗主権(強い影響力)が及んでいたこともあってイラクのサダム・フセインの征服欲を誘うこととなり、1991年の湾岸戦争はイラクのクウェート侵攻からはじまったのです。
バーレーンは人口80万人、虎の子の「石油」があと20年ほどで枯渇することになりますが、隣国サウジアラビアが厳格なイスラム法により、実質的な鎖国状態にあることから、いわばサウジアラビアの「出島」のような役割を果たし、ドバイやカタールと並ぶ金融センターとしての機能を近年整備しています。
カタールは人口140万人、豊富なオイルマネーに恵まれ、富裕層の割合はクウェートと並ぶ勢いで、国民には所得税がかからず、医療費、電気代、電話代が無料、大学を卒業すると一定の土地を無償で借りることができ、しかも10年後には自分のものとなるという自国民優遇制度を進めています。また、将来の「石油」枯渇を見据え、ペルシア湾岸に今後10年間で1兆ドルを投資し、知識集約・技術集約型の産業を起こそうと努めています。
最後はUAE(アラブ首長国連邦)ですが、皆さんにはドバイとか、アブダビと言った方がわかりやすいかもしれません。UAEはドバイ、アブダビをはじめとする7つの首長国が作った連邦ですが、実質的にはドバイとアブダビの力が群を抜いているので、この二つの首長国を紹介しましょう。
アブダビはUAEのリーダーで、最大の「石油」資源とオイルマネーを抱えており、つい最近のドバイの経済危機を支えたのもアブダビのオイルマネーの力だと言われています。
一方、パートナーのドバイはアブダビほどの「石油」資源に恵まれていないことから、脱「石油」政策を進めており、中継貿易港や経済特区の整備、金融センターの機能拡充、世界一高いブルジュ・ハリーファ(160階建て、828mの高層ビル)、急成長するエミレーツ航空、世界のVIPが別荘を連ねるパーム・アイランド(人工島)、砂漠の人口スキー場スキー・ドバイなど、「派手で贅沢で最高級」という路線をひた走りに進んでいます。
こうして見ますと、実力のアブダビ、ルックスのドバイといったところですが、その巨額なオイルマネーは世界の注目するところで、一時期は世界中のビジネスマンがドバイ詣でに明け暮れたほどです。
さて、ペルシア湾の真珠のような国々、いずれも人口こそ少ないですが、その「石油」資源とオイルマネーは世界を席巻しており、とりわけ日本は原油の4割をこの地域から輸入しているという状況にありますので、決して無視できる地域ではないのです。
B-D番外編「イラク」
皆さんはイラクと聞くと、サダム・フセイン、あるいは1991年の湾岸戦争や2003年のイラク戦争を思い出すかもしれません。親子二代にわたるブッシュ大統領との確執をはじめ、大量破壊兵器が本当にあったのかどうかはさておき、近年、イラクは世界を騒がせてきました。イラク、それはメソポタミアの大地でもあります。6,000年前から古代文明が栄えたこの地域は、東にイラン高原、北にアナトリア(トルコ)からコーカサスの山脈地帯、南に広大なアラビア砂漠が拡がり、周辺からの侵攻に晒され続けた歴史を辿りました。また、数多くの民族の栄枯盛衰から、複雑な民族構成を持つ土地でもあります。
こうした背景から、メソポタミアは豊かではあるものの、地政学的に安定した統治体制の難しい環境にあったと言えるでしょう。そのメソポタミアはオスマントルコ帝国の崩壊後、地下に眠る莫大な「石油」資源を狙うイギリスとフランスの勢力下に置かれることとなり、イスラム社会の頭越しにメソポタミアの西はフランスの支配下からシリアとなり、東はイギリスの支配下からイラクとなったのです。
そして、イギリスはこうした複雑な地域の安定化を図るために、“アラビアのロレンス”で有名となった反オスマントルコのリーダーであり、ムハンマドの血筋につながるアラビア半島のハシーム家に人口3,000万人を擁するイラクの王座を与えることとなりました。しかし、その王座は三つの異なる勢力の上に置かれた極めて不安定なものでもありました。
その一つはシーア派で、人口の半数を占める多数派ですが、イスラム社会全体では少数派となることから、彼らをイラクの中心に据えることはできませんでした。
もう一つはクルド人で、イラク、トルコ、イランの国境地帯に住む“国家を持たない世界最大の民族”ですが、彼らが勢いを増せば、自ら独立しかねません。
最後がスンナ派で、人口の3分の1しか占めていませんが、イスラム社会全体では多数派に属するため、周辺のイスラム社会との兼ね合いもあり、イギリスは彼らに人口以上の力を与えることとなったのです。
こうして微妙な政治バランスの上に乗ったイラク王制は、イギリスに莫大な「石油」を与え続け、いわばイギリスの傀儡(かいらい)と見做されてイラクの人々の反感を買い、当初から先行きを危ぶまれていましたが、1958年の軍事クーデターでついに滅ぶこととなりました。その後は、軍をバックに政権が入れ替わることとなりますが、1979年、クルド人の反乱を制圧したサダム・フセインが政権を握り、2003年のブッシュ・ジュニアとの戦いに敗れたのは皆さんご承知のとおりです。
このようなイラクの辿った歴史は、世界第3位を誇る「石油」資源がもたらしたものでもあります。サウジアラビアが「石油」の超大国となる1950年代までは、イランとイラクが「石油」資源の要であり、それを押さえることがヨーロッパ諸国の最大の国家戦略となっていました。そして、イランが反米運動の先頭に立った1980年代以降は、相対的にイラクの存在価値が増すこととなり、それが2003年のイラク戦争の遠因となったとも言えるでしょう。
そして、2010年のアメリカ軍撤退以降は、シーア派を中心とする政権がイラクを統治していますが、三つの勢力、シーア派、クルド人、スンナ派は「石油」権益の分配を巡って激しい政治的綱引きを続けており、クルド人の住むイラク北部は半独立状態、首都バグダットでは宗派間の自爆テロがおさまる兆しすら見えません。
「石油」が作り上げた人工の国家とも言うべきイラクの行く先は、いまだ定かには見えてこないのです。
B-D番外編「サウジアラビア」
前回、「石油」と西アジア、そして日本の関係についてお伝えしました。今回は、その「石油」の超大国サウジアラビアです。
サウジアラビア、アラビア語による国名のアル=マムラカ・アル=アラビーヤ・アッ=スウーディーヤは「サウード家によるアラビアの王国」という意味になります。そうです、サウード家の国王による絶対王政の国がサウジアラビアなのです。
このサウジアラビアはアラビア半島のほとんどを占める広大な国ですが、イスラム教発祥の地であり、今もメッカ、メディナという聖地を抱えています。例えば、日本における出雲地方は、かつては日本列島に大きな影響力を及ぼしていたものの、今は出雲大社に代表される神話の国であって、もはや日本に占める位置はそう高いものではありません。それとまったく同じで、アラビア半島はイスラム教が生まれた土地としてイスラム社会の尊敬は集めても、経済的にも文化的にもイスラム社会の辺境とも言うべき状態に陥り、砂漠の中を遊牧民が暮らす不毛の大地という捉え方をされていたのです。
こうした状況に反旗を翻し、新しい王国を作り出したのがアラビア半島中部に勢力を伸ばしていたサウード家でした。そして、オスマントルコの強大な軍事力に対抗するため、ワッハーブ派というイスラム教の改革運動と手を組み、いわば聖俗がタッグを組む形で独立の戦いをはじめたのです。こうした経過から、今でもサウジアラビアはスンナ派の中でも最も厳格な宗教的解釈を行っています(番外編第7話「イスラムにおける宗教的解釈」参照)。
しかし、そのままですと依然として砂漠の王国に過ぎなかったサウジアラビアの未来を変えたのは、不毛な大地から湧き出す「石油」でした。当時、「石油」の多くはイギリスの勢力下にあるイラクやイランに埋蔵されていると信じられ、サウジアラビアには「石油」は望めないと考えられていました。このため、イギリスをはじめとするヨーロッパの国々に西アジアの石油資源を押さえられていたアメリカは、藁をもつかむ思いでサウジアラビアへ接近し、1933年、アメリカの国際石油資本スタンダード・オイル・オブ・カリフォルニア(現:シェブロン)の子会社がサウジアラビアのイブン・サウード国王との合意書に調印し、毎年5,000ポンドと石油が出た場合にその収入で返済する50,000ポンドの貸付で石油利権を獲得したのです。
そこからはサウジアラビアとアメリカの蜜月時代が訪れ、世界第一の埋蔵量を誇るサウジアラビアの「石油」は、アメリカを中心とする世界経済の血液として機能し続けることになり、それに伴ってイスラム社会におけるサウジアラビアの存在感は極めて高いものとなりました。
今でもサウジアラビアは、巨額な経済援助で西アジアの親サウジアラビア政権を支え続けています。例えば、政情不安の続くエジプトは外貨準備が枯渇しそうな経済状態に陥っていますが、それを支えているのは数千億円にものぼるサウジアラビアの経済支援です。
富と「石油」を握るサウジアラビアは、このようにイスラム社会の巨人となっていますが、その内情は必ずしも安泰とは言えないようです。
第一の問題はサウード家そのものです。サウード家は初代国王イブン・サウードのあとは、その十数人を超える子どもたち(第二世代)が順番に王位をつないでおり、現国王は90歳、その後継者である異母弟も80歳という高齢であり、その下の第三世代にどう王位をつなぐか、大きな政治問題となっています。
第二の問題はアメリカとの親密な関係と厳格な宗教的解釈との軋轢をどう解決してゆくか、ということです。以前、王族の若い女性マシャイル・ビント・ファハド・アル・サウードがイスラム法で重罪とされる婚外交渉を続け、さらに交際相手と駆け落ちを図って公開銃殺されたのですが、こういった厳格な宗教的解釈とアメリカ流の現代生活との矛盾はますます拡大することになるでしょう。そうした矛盾とどう向き合うかが問われていると言えます。
このようにあり余る「石油」と巨額のオイルマネーを手にしながら、厳格なイスラム社会とアメリカとの緊密な関係、西アジアの巨人サウジアラビアの行く先はなかなか見えにくいと言えるのかもしれません。
B-D番外編「石油と西アジア」
皆さんの中には複雑で不安定な西アジアなんて何で関心を持つ必要があるのか、と思う人もおられると思います。“シーア派”だとかスンナ派だとか、イランとイスラエルの対立だとか、いったい何の関係があるのか、と思う人も多いでしょう。しかし、どうしても日本は西アジアと無関係ではいられないのです。
それは「石油」です。
日本の原油輸入の国別比率を見てみますと、その多くを西アジアが占めていることがわかります。
①サウジアラビア 31.2%
②UAE(アラブ首長国連邦) 21,7%
③カタール 10.7%
④クウェート 7.3%
⑤イラン 5.2%
と、上位5ヶ国が西アジアで、その合計は76.1%という割合です。
日本が消費する石油(原油)の4分の3以上が西アジアからタンカーに載せられて、狭いマラッカ海峡を抜けて日本へ届けられるのです。
こうした西アジアからの石油が届かなくなれば、日本のエネルギーが枯渇する位の大変な量になります。
資源エネルギー庁のホームページによれば、日本はエネルギーの96%を海外から輸入していますが、その輸入エネルギーの半分は「石油」です。
私たちの今の生活がどれほど「石油」に依存しているか、ということになります。
この「石油」が輸入できなくなったのが、1973年の第一次オイルショック(四回目のイスラエルとイスラム社会との戦争の影響)で、私は当時大学生でしたが、恐ろしいほどの品不足が起こり、どの商店にも長い買い物客の行列ができたことを記憶しています。そして、日本政府は三木武夫副総理を西アジア諸国へ派遣して、日本への「石油」の輸出を停止しないように懇願したことも思い出します。
その後、日本は第一次オイルショック時代の77%から47%にまで「石油」への依存率を低下させましたが、そうは言ってもまだまだ半分は依存しているのです。
例えば、米1㎏を生産するには石油(原油換算)0.35ℓが必要です。
自動車1台を生産するには1,442ℓ、本1冊には0.55ℓの石油(原油換算)が使われているのです。
このように私たちの生活に欠かせない「石油」、その多くを西アジアへ依存している以上、日本は西アジアとの関わりを続けなければならない、ということになります。
こうしたエネルギー依存の問題は、お隣の中国も同様でして、今や世界最大のエネルギー消費国となった中国も年々海外依存度を高めており、「石油」については今や60%を輸入に頼る状況に陥っています。そこで中国は、アフリカや中南米、ロシア、ミャンマーなどからの多様な「石油」輸入を確保しようと積極的な外交を展開していると言えるでしょう。
さて、日本は西アジアからの「石油」を安定的に確保できるのかどうか、あるいは西アジア以外からの多様な輸入を実現できるのかどうか、いずれにしても当面は西アジアとの関わりを維持することが必要ですし、そのためには西アジアの複雑な社会環境により深い認識をすることが求められていると言えるのではないでしょうか。
B-D番外編「イスラエル」
「イスラム社会に刺さった棘」、と極端な言い方を前回はしましたが、イスラエルという「国」は極めて特殊な成り立ちを辿ってきました。それは、この「国」がユダヤ人(ユダヤ教徒)の国であり、神から授けられた旧約聖書によれば、神が定めた彼らの土地です。しかも、そのユダヤ人(ユダヤ教徒)は「ディアスポラ(撒き散らされたもの)」と呼ぶ2,000年近い世界各地への離散を余儀なくされ、その間、キリストを殺した民としてキリスト教徒から度重なる迫害を受けた過去があります。この迫害は、19世紀のロシアでの大規模な反ユダヤ運動、そしてナチスドイツによる広範なユダヤ人虐殺を招くことになります。こうしたヨーロッパ社会での様々な迫害は、ユダヤ人の間に自分たちの国を目指す運動(シオニズム)が拡がることになりました。そして、既にアメリカや西ヨーロッパで経済的な成功を収めていたユダヤ人の強力な支援を受けることになり、そうした中で「ユダヤ人国家をどこに作るべきか」という国際的な検討が進められることになりました。しかし、世界中のどの土地であれ、人の住んでいない土地はありません。そうした人たちを追い出すのか、あるいはそうした人たちと一緒に生きる道を選ばない限り、「新しい国」など簡単に作れるはずがありません。このため、例えばアフリカのウガンダであるとか、アルゼンチンであるとか、現在のパレスチナであるとか、さまざまな候補地が取り沙汰されましたが、最終的に1917年、イギリスの外務大臣がイギリスのユダヤ人コミュニティーのリーダーであるロスチャイルド家(巨大財閥)へパレスチナにおけるユダヤ人の居住地(ナショナルホーム)の建設に賛意を示し、その支援を約束しました。
それ以来、ユダヤ人はパレスチナへ続々と移民し、とうとう1948年にはイスラエルという国を独立させることになりました。
しかし、先ほども言いましたように、世界中のどんな土地であれ、人の住んでいない土地はありません。当然、パレスチナにもたくさんのイスラム教徒であるアラブ民族が住んでいました。そこにたくさんのユダヤ人が押し寄せてくるのですから、これは騒動になって当たり前、しかもイスラム教徒の頭越しに決められた移民ですから、とうとうイスラエルとそれを取り巻くイスラム社会(エジプト、シリア、イラク、レバノン、ヨルダン、サウジアラビアなど)は戦争をはじめることになりました。その後も1956年、1967年、1973年と同じような戦争が続くことになります。
このように、イスラム社会の頭越しに欧米の支援を受けて建国したイスラエルは、大量のパレスチナ難民を産み出すとともに、常に周辺のイスラム社会との緊張関係を招いています。この緊張関係は、ユダヤ人社会が大きな政治的、経済的影響を持つアメリカがイスラエルの支援をすることによって、イスラエル・アメリカ同盟とイスラム社会という新たな対立軸をもたらしています。加えて、武器は常に戦闘を重ねることで進化する、という必然性から、イスラエルは世界有数の軍事国家という側面を持ち、イスラム社会との戦いで不敗を誇り、それがさらなるイスラム社会の憎悪を産む、という悪循環さえ招いているのです。
そして、このイスラエルの突出した軍事力は、とうとうイランを核開発へと進ませることになりました。
いかがでしょうか、イスラエルはイスラム社会に刺さった棘、という意味がおわかりでしょうか。さて、そのイスラエルはユダヤ社会の高度な教育水準を背景として、ハイテク、情報通信などの分野で強い競争力を発揮しており、日本の企業もイスラエルのITベンチャーと業務提携する事例が数多くみられます。また、イスラエルの人口はわずか700万人に過ぎませんが、世界中の1,500万人のユダヤ人の母なる国として人口規模では測れない力を持っていると言えるでしょう。
また、イスラエルにはユダヤ人以外の人々も200万人ほど住んでおり、ユダヤ教中心の国家体制の中で少数派として位置付けられています。さらに、同じユダヤ人と言っても、世界中に2,000年近くも離散していた歴史から、言語、文化、経済力などで異なるいくつかの集団に分かれており、そうした内部問題も存在しています。
そうした意味では、イスラエルは外にも内にもいろいろな問題を抱えながらも、その特異なエネルギーで西アジアの一角を今も占めているのです。
B-D番外編「イラン」
西アジアについては、以前に第245話でアフガニスタンを紹介しましたが、今回は西アジアの大国、アフガニスタンの西に拡がるイランをお伝えいたします。イランというよりは“ペルシア”と呼んだ方が馴染みやすいのかもしれません。古くはペルシア帝国(アケメネス朝、ササン朝)を築き、西アジア全体に強大な勢力を誇りました。そのせいもあってか、第222話でご紹介したタジキスタンのタジク族、第239話でご紹介したアゼルバイジャンのアゼリー族(アゼルバイジャン人)と、イラン系の民族は西アジア一帯に拡がっています。また、イランは前回お伝えした“シーア派”が大多数を占めるため、スンナ派主流のイスラム社会では少数派に属しています。
さて、西アジアはオスマントルコの領土であったためにイギリスやフランスの支配下に置かれた過去を持つ国が多いのですが、イランは比較的独立性を保ってきたため、古代ペルシアの残光とあわせ、プライドが高い民族としても知られています。
そして、第一次世界大戦後、イギリスとソビエトロシアが互いにイランを影響下に置こうとうごめく混乱の中、軍を従えたレザー・パーレビが自ら王朝を開き、50年におよぶパーレビ朝(パフラヴィー朝)の歴史がはじまったのです。
パーレビ朝は西アジアの強国を目指してアメリカへ接近し、その援助を受けて王権を強めましたが、王族への富の集中とそれに伴う腐敗構造は多くの国民の憤慨を招き、とうとう1979年には“シーア派”聖職者であるホメイニ師を中心とするイラン革命が起こることになりました。この間のアメリカ大使館人質事件やカーター大統領による救出作戦の失敗はイランにおける反米感情を引き起こし、以来、30年以上にわたってイランとアメリカは対立を続けることになるのです。
こうした欧米との対立構造はイランをイスラム社会のリーダーへ進ませることになりますが、厳格な“シーア派”中心という国家体制はイランがイスラム社会での存在価値を高めれば高めるほど、それに対する反発を招くことになり、サウジアラビアやフセイン政権下でのイラクをはじめとする反イランのうねりを作り出すことにもなりました。
このイランを火種とする西アジアの不安定さは、欧米とイラン、スンナ派主流のイスラム社会と “シーア派”イランという二つの対立軸を今日にも抱えているのです。
そして、イスラム社会のリーダーを目指すイランは「核」の開発という段階にまで進み、さらなる不安定さを産み出しており、昨年11月には国連安保理常任理事国とドイツの6ヶ国が核開発の透明性を高める代わりに対イラン制裁の一部を緩和する「第1段階の措置」で合意したところです。
しかし、イランにおける「核」の開発は西アジアのみならずイスラム社会全体に刺さった棘となっているイスラエルを睨んだものであるため、イスラエルがイランによる核攻撃の懸念をぬぐいきれないかぎり、依然として大きな不安定要因となり続けることでしょう。
イスラエルがなぜイスラム社会の棘なのか、については次回、イスラエルをご紹介する中でお伝えしたいと思います。
このように、さまざまな不安定さの火種となっているイランですが、7,500万人を超える人口、世界第4位の豊富な原油埋蔵量、一人あたり7,000ドルを超える所得水準(マレーシアとタイの中間程度)を考えますと、やはり西アジアの大国としての存在価値を保ち続けると言えます。
A番外編「シーア派」
イスラム社会における宗教的解釈がコーランに忠実で厳格な人たちから、現実社会を許容する人たちまで、さまざまに分かれていることは前回お伝えしました。今回は、イスラム社会を理解するうえで、もう一つの大きな軸である“シーア派”という宗派の問題です。もともと“シーア”とは党派(セクト)という意味で、信徒はすべて等しく神と向き合うというイスラム社会ではなじみにくい概念なのです。このため、“シーア派”以外のイスラム社会では自称する名称は特になかったのですが、後年、“シーア派”が一定の社会的勢力を有するようになってからは、それとの対峙関係を明らかにする意味もあり“スンナ派(ムハンマドの時代から積み重ねられた慣行=スンナと正統なイスラム共同体に属する人々)”と言うようになりました。前回にお伝えしたスンナ(ムハンマドの言動が伝えられた慣行)をそのまま名称にしていることになります。
さて、ではどうしてイスラム社会ではなじみにくい「党派」が生まれたのか、それは預言者ムハンマドの死後に遡ります。イスラム教は、ムハンマドが神から与えられたコーランに基づく宗教運動で、神と会えるのはムハンマド一人に限られていますから、そのムハンマドの死は成立間もないイスラム教団にとって大変な出来事でした。
イスラム教団はアラビア半島西部に勢力を持つクライシュ族を中心として成立しましたが、そのクライシュ族の有力者が一堂に会し、ムハンマド亡き後の指導者を定めました。これをカリフ(アッラーの使徒ムハンマドの代理人)と呼び、初代のアブー・バクル、二代目のウマル、三代目のウスマーンと、いずれも教団内の有力者の合議で選ばれたのです。
しかし、こうしたクライシュ族の有力者がカリフを決めるやり方に不満を持ったのが、ムハンマドの従兄弟であり、娘婿でもあったアリーです。アリーは、ムハンマドの最初の弟子の一人とも伝えられ、血筋から言っても息子のいなかったムハンマドのもっとも近い親族でしたので、自分がカリフに選ばれるべきだと強く願っていました。しかし、年齢的に若かったことから初代から三代目までのカリフには選ばれなかったのです。
そして、ウスマーンが暗殺されたあとの四代目のカリフにアリーはようやく選ばれたのですが、クライシュ族の一大勢力であり、三代目ウスマーンの一族でもあるウマイヤ家が反旗を翻し、その戦いの中でアリーは暗殺され、アリー亡き後のカリフはウマイヤ家が世襲することになりました(ウマイヤ朝のはじまり)。
こうしたウマイヤ家によるカリフの独占は、アリーを旗頭とする集団(これをシーア・アリーと言い、それが“シーア派”になります)はアリーの子孫を担いでウマイヤ朝に強く抵抗することになります。このシーア・アリーの反ウマイヤ朝の運動は、衆寡敵せず、多くの殉教者を残して敗れることになります。しかし、アリーの血を引く子孫(イマーム)が生き残るのとあわせて“シーア派”も後世に伝わりました。
当然ですが、“シーア派”と対立するウマイヤ朝、あるいはそれを継いだアッパース朝は、アリーの子孫を根絶やしにしようと血眼になり、実際ほとんど滅んでしまうのですが、“シーア派”ではそれを「お隠れになる」と称し、やがて「お隠れになった」イマームは救世主(マフディー)となってこの世に再臨する、という独特のメシア思想を発達させることになるのです。
そして、イスラム社会の中心であるアラビア半島からメソポタミアから遠く、アラブ人中心の社会体制に反発する周辺地域で“シーア派”は勢いを持つことになります。また、アリーの子孫もいくつかに枝分かれしますので、どの子孫をイマームとして認めるかを巡って“シーア派”はさらに分裂することにもなるのです。
その結果、現代のイスラム社会では、12人のイマームを正統とする十二イマーム派、これが“シーア派”の最大勢力ですが、イラン、アゼルバイジャン、イラク、レバノンに多く、イランとアゼルバイジャンでは国民の大多数を占めています。
また、七代目のイマームの際に分かれたイスマイール派はシリアやレバノンで勢力を持ち、イスマイール派の分派であるシリアのアラウィー派は今のアサド政権の母体となり、同じ分派のドゥルーズ派はレバノンで政治的に大きな力を有しています。
さらに、先ごろ安倍首相が訪問したアラビア半島南部のオマーンでは、シーア・アリーの一員でありながら、アリーのウマイヤ家に対する妥協的な行動を嫌って分派したイバード派が多数派を占めています。
このように、“シーア派”はイスラム社会全体の10%から20%という少数派ですが、それでも2億人を超える信者を抱え、特定の地域では強い影響力を維持しています。
この宗派という問題と、前回お伝えした宗教的解釈の差という二つの軸を通じて、イスラム社会は複雑に織りあわされた様相を呈していると言えるでしょう。
こうしたイスラム社会の複雑さを念頭に、次回からの西アジアシリーズをご覧いただきたいと思います。
A番外編「イスラムにおける宗教的解釈」
西アジアを語る際に避けて通れないのがイスラム教です。そして、イスラム教と言うと、皆さんがイメージするのは「宗派間の争いが絶えない」ということでしょうが、その大きな要因となっているシーア派という宗派です。そこで、今回は簡単にイスラム教の概要とシーア派が生まれた由縁をお伝えしたいと思います。まずは、イスラム社会における宗教的解釈です。
まず、押さえなければいけないのは、イスラム教はアブラハムの宗教(第37話参照)ですから一神教であり(ユダヤ教やキリスト教と同じ)、この宗教カテゴリーが共有する価値観は強烈で、私たちの多神教の世界とは明らかに異なります。
第一は、神は唯一の神である、ということです。それ以外の神はいないのです。
第二は、神が預言者にメッセージを与える、ということです。ユダヤ教ではモーゼがシナイ山で十戒を授かり、キリスト教ではキリストが神の言葉を授かり、イスラム教ではムハンマドがコーランを授かり、それを聖典としたのです。
第三は、神が人間の生き方のルールを定める、ということです。神が与えたメッセージは人間が守らなければならないルールであり、それから外れることは神を裏切ることなのです。
第四は、世界は神が創造し、いずれ世界の滅亡があり、その際に神が裁きを下す、ということです。神の定めたルールを守った人は永遠の命が与えられ、神の定めたルールを破った人は地獄へ落ちる、ということになります。
しかし、神が預言者に与えたメッセージ(イスラム教ではコーラン)にすべてのルールが書き記されている訳ではありません。世の中は日々刻々と変化しますので、それらをすべて網羅することは不可能です。そうしますと、コーランに書いていない出来事が起こったらどうするか、ということになります。
そこで現実の問題を宗教的にどう解釈するかという事態が発生します。これがイスラム教を理解する入り口とお考えください。
イスラム社会ではコーラン(クルアーン、聖典)が一番権威を持ち、ついでムハンマドの言動を伝えたスンナ(慣行、文書にしたのがハディース、文章にしないで伝承している慣行もあります)、いずれでも判断のできないことはキャース(類推)と言って「神やムハンマドはどう指示するだろうか」と理性に従って考えること、そして判断に迷うことはイジュマー(合意)と言って宗教的な指導者が集まって議論を尽くすのです。
そうして見ますと、独断の入る余地の少ない合理的な判断システムを備えた宗教と考えてもよいでしょう。まずはコーランに基づき、ついでスンナを調べ、足らなければキャースで類推し、最終的に合意を目指すイジュマーに拠る、と段階的に解釈を尽くすのです。
ここで問題になるのは、キャースはさまざまに可能だという現実問題です。
例えば、コーランでは「酒を呑むと礼拝を忘れたりするので呑まないのがよい」とされていますが、これをどうキャース(類推)するかで、「礼拝を忘れない程度に酔うのはかまわない」から「礼拝を忘れることがあるから絶対に酒は呑んではいけない」まで、大きな差が生まれるのです。
このように宗教的解釈には差が生まれ、コーランを遵守して厳しく生活を律する考えもあり、緩やかにコーランと生活の融合を図る考えもある、ということになります。
このため、いわゆる法についても、コーランやスンナに沿ったシャリーア(イスラム法)を順守するのか(第63話参照)、あるいは国際的に一定共通している世俗法を受け容れるのか(第64話参照)、という問題が生まれるのは、そもそも宗教的解釈に差があることからはじまっていると言えます。
従って、イスラム社会を一律に見るのではなく、宗教的解釈が厳しい人たち(サウジアラビアやイランなど)、宗教的解釈が緩やかな人たち(トルコやエジプトなど)が存在することをよく理解する必要があります。
さらに、宗教的解釈に加え、次回お伝えするシーア派という宗派としての違いが重なりますので、その辺にも注意が必要でしょう。サウジアラビアとイランの社会はどちらも厳格な宗教的解釈を重んじますが、宗派的には真っ向から対立する、という具合です。
B-D番外編「西アジア俯瞰」
「アジアとの付き合い方」として日本の中小企業や小規模事業者にとって重要な位置を占めるアジアの国々を、過ぎる戦争の記憶から筆を起こし、東南アジア、東アジア、北アジア、中央アジア、南アジアと、ちょうど中国を取り巻く同心円状にお伝えしてきました。今回はいよいよ最後の西アジアの国々をお伝えしたいと思います(中国については改めてシリーズを起こします)。
西アジア、なんと遠いことでしょう。また、私たちの世界とは大きく異なるイスラムの土地です。ですので、日本人がアジアと言ったときに、ともすればアジアには入らない世界と思いがちですが、間違いなく彼らはアジアの一員です。
その中心は古代文明発祥の地、チグリス・ユーフラテスの交わる“メソポタミア”です。古く5,000年以上前に都市国家が作られ、両大河のもたらす肥沃な土壌と雪解け水は麦を中心とする農耕を生み、楔形文字やハンムラビ法典など、人類にとってはじめての「文明」が誕生したのです。
この“メソポタミア”を東西南北に取り巻いている地域があります。
まずは東です。東はインド亜大陸がユーラシア大陸に衝突した際のエネルギーが大地を盛り上げ、広大なイラン高原を作りました。このイラン高原が今のイランです。
次いで北(正確には西北)です。北はアナトリアという半島がメソポタミアに隣接しています。こちらも造山活動でその東部が山岳高原地帯となっており、メソポタミアと地理的に区分されていますが、このアナトリアが今のトルコです。
そして南です。南は広大なアラビア半島が拡がっています。イスラム教発祥の地であり、不毛な砂漠の大地ですが、近年石油資源が発見されてからは世界での影響力を増している地域です。もっとも大きなサウジアラビアのほか、ペルシア湾沿岸のクウェート、バーレーン、カタール、UAE(アラブ首長国連合)、そしてアラビア半島の南にイエメン、オマーンといった国々が並んでいます。
最後は西です。西は狭隘なガザ地峡(パレスチナ)でエジプトのデルタ地帯につながっており、エジプトから北アフリカ、そしてサハラ以南のブラックアフリカへと道は開かれています。
このように、“メソポタミア”は東のイラン、北のトルコ、南のアラビア半島、西のエジプトに囲まれており、古来よりこうした周辺からの侵入に悩まされた豊饒の大地なのです。
では、“メソポタミア”の今はどうでしょうか。
まず中心であるチグリス・ユーフラテスの流域はイラクという国家になっています。この国は後程イラクのところで説明しますが、1921年にイギリスの手によって産み出された人工的な国家と言う性格があり、それが政情の不安定さの原因となっています。
そして、イラクの西は植民地時代にフランスの支配下に置かれたため、イラクとは切り離されシリアという、これも人工的な国家が作られました。今日でも悲惨な内戦が激しさを増していますが、その遠因は“メソポタミア”から切り離された植民地分割にある、とも言えるでしょう。
また、フランス統治下時代に「キリスト教徒が多数を占める地域」を作る、という思惑によってシリアから切り離されたレバノンという小国が地中海に面しています。日産のカルロス・ゴーンの母国です。
さらに、その南に拡がるパレスチナは預言者ムハンマドに遡る血筋のハーシム家出身の国王が世襲統治するヨルダン、西アジアの不安定要因となっているユダヤ国家イスラエル、ユダヤ人に故郷を追われたパレスチナ人の自治政府に三分されています。
いかがでしょうか、西アジアを鳥瞰していただけたでしょうか。頭の中で真ん中に“メソポタミア”、東にイラン、北(西北)にトルコ、南にアラビア半島、西にエジプト、そんな西アジアの地図をイメージしていただければ十分だと思います。
E番外編「さまざまな挑戦④~海外で働く女性~」
さまざまな挑戦シリーズの最後は、日本経済新聞1月4日付けの記事から海外で活躍する女性たちを紹介します。最初は、八尾祐美子さん、44歳の彼女は東京ガスというお堅い会社のプリスベーン事務所長です。
事務所長というだけでも驚きますが(エネルギーという業界の海外所長が女性という異例さ)、それだけではなく彼女の職責は石炭層へ付着したメタンガスをLNG(液化天然ガス)として2015年に日本へ輸出するという社運を賭けたプロジェクトの現場責任者ですから凄い話です。いわゆるシェールガスの一種(それらを非在来型資源と言います)で、こうした非在来型資源の登場は世界のエネルギー事情を一変する革命的事件です。
このプロジェクトの全容は、東京ガスの公式サイトで取り上げているほどですので、ぜひご覧ください(http://www.tokyo-gas.co.jp/Press/20110307-02.html)。
さて、八尾さんは上智大学の出身、同期で約30人が入社した女性総合職、その中で彼女ははじめてのボーナスでPCを買い、独学で使い方を習得(1990年代でしょうから大変でしたでしょう)、3年目の支社勤務で検針員のデータをPC処理する方法を導入して評価され、長期留学制度でアメリカのMBAで学び、ここで「自分のできることを持ち寄り、チームで課題を解決すること」を身に付けたのです。いわゆるファシリテーション・スキルです。そして、明らかに能力を伸ばした彼女は東日本大震災後の日本のエネルギー需要を支えるプロジェクトの責任者にまで自分の可能性を発揮したのです。
次に、ニューデリーでインフォブリッジ・ホールディングを率いる繁田奈歩さん、38歳の彼女はインド市場へ参入を目指す日本企業の支援を手掛けています。
インドと日本というワクワク感のあるビジネスを展開する女性、なんか凄そうです。実はやはり凄くて、東京大学在学中にはじめての海外旅行でインドを訪れ、空港から宿まで一緒だった大学生がその後行方不明になる事件に遭遇、「安全な送迎サービスを提供する会社を作ってやろう」とインド人と共同で会社設立、大学を卒業するためにその会社は閉じたが、卒業後はベンチャー企業に入って中国子会社を立ち上げて上海へ、その子会社をMBO(Management Buyout、会社経営陣が株主から自社株式を譲り受けオーナー経営者として独立する行為)するなどの変遷を経て、2008年からインドへ進出し、今は200人のスタッフを束ねる立場です。
彼女を方向付ける価値観は明確です。「仕事の依頼や誘いに対する返事はYes、チャンスの女神は前髪しかない、逃せば二度と掴めない」「誰だって挑戦する権利もあれば失敗する自由もある」ということです。
最後に、東京ソフトというアウトソーシング企業のブラジル法人の社長を務める上野陽子さん、39歳の彼女の人となりはご自分のブログが一番の材料、「変化是機会」という邱永漢(日本及び台湾の実業家、作家)の言葉を大切にする彼女の価値観があふれています(http://yokoblog.jugem.jp/)。
彼女は12歳のとき、ディスプレーに天気予報やニュースが流れるのを見て「この仕事に関わりたい」と決意、情報処理を学んでSE(システムエンジニア)として働きはじめる。しかし、何か物足りなくなってカナダと中国へ留学、中国では現地企業で写真のデジタル化に従事し、日本企業向けの営業をする中から日系人のコーヒー農園の話を聞いて南米に興味を持ち、ブラジルへの進出を検討していた東京ソフトへ入社、半年後にはブラジルへ赴任し、現地法人を立ち上げる、という神業のようなスピードで今に至っています。
新しいことにどんどん挑戦する彼女は、明らかに優れたコンピテンシーとして「自信」「先見力」「達成指向性」に満ち溢れているようです。
こうして三人の女性の遍歴を見てきましたが、いずれも明確な価値観、高いレベルでのスキル、優れたコンピテンシーを自ら磨いてきたのがよくわかります。まさに「天は自ら助けるものを助ける」という好例のようなものです。
いかがでしょうか、このシリーズでは9人の女性を取り上げましたが、かなり強い閉塞感に覆われている現代の日本社会でもできることはたくさんある、ということですし、同時に日本を出てもできることはたくさんある、ということがおわかりいただけたでしょうか。すべては皆さん自身の心の持ちようなのですから。
E番外編「さまざまな挑戦③~フェアトレード~」
今回は、フェアトレードの現場で活躍している女性の話です。フェアトレード、聞いたことないな、という方も多いでしょうから、ウィキペディアから紹介しましょう。
フェアトレード(Fair Trade、公正取引)、発展途上国の原料や製品を適正な価格で継続的に購入することを通じ、立場の弱い途上国の生産者や労働者の生活改善と自立を目指す運動。オルタナティブ・トレード(Alternative Trade)とも言う。連帯経済の一翼を担う活動でもある。「公正取引」という表現は政府との関係がある組織にも使われているので、誤解対策のために「適正な報酬での取引」という交代表現も使われている。国際的な貧困対策、環境保護を目的としアジア、アフリカ、中南米などの発展途上国から先進国への輸出において、こうした取引形態が採用される場合がある。主な品目としてコーヒー、バナナ、カカオのような食品、手工芸品、衣服がある。需要や市場価格の変動によって生産者が不当に安い価格で買い叩かれ、あるいは恒常的な低賃金労働者が発生することを防ぎまた児童労働や貧困による乱開発という形での環境破壊を防ぐことを目的としている。最終的には生産者・労働者の権利や知識、技術の向上による自立を目指す。
いかがでしょうか、社会的な新しい価値を創り出すビジネススタイルと言えるかもしれません。日本でも1980年代後半からはじまり、生協や大企業でも国際的な商品仕入れの中で取り入れるところも出てきています。
そのフェアトレードの最前線で頑張っている女性、高橋百合香さんをご紹介します。彼女は33歳、ネパリ・バザーロという会社で働いています。会社は、ネパールの衣服、アクセサリー、食品などを輸入するとともに、陸前高田で自生する椿から油を搾って化粧品に加工するなど、幅広い活動を展開しています。詳しくはhttp://www.verda.bz/。
この高橋さんは、高校生の頃に病気や飢えに苦しむアジアやアフリカの子どもたちの写真に衝撃を受け、途上国を支援する仕事につきたいと思うようになり、大学でシュウカツをする中で今の会社を知り、社長から「覚悟を決めなさい」と背中を押されて「ここで頑張ろう」と決めたそうです。
このネパリ・バザーロでは高校生の仕事体験を受け入れていますが、その紹介サイト(仕事の学校)から興味深いやり取りがありましたので、かいつまんでご紹介します。やり取りが高橋さん本人かどうかはわかりませんが、こういう仕事に就く人たちの価値観が窺えると思います。
<御社で一番大切にしていることは何ですか? >
生産者視点、弱者視点を忘れず、社会貢献を達成するという目的に向かって進むことです。 その意味では、フェアトレードを推進する情熱を常に持ち続けながら、具体的な仕事を進める力と技術を磨くことでもあります。リーダーシップは特に大切です。
<どんな学生(高校生)時代を送っていらっしゃいましたか?>
スポーツはテニスと自転車、趣味はアマチュア無線に没頭。秋葉原をうろつくネクラ。狭い世界しか見ていなかったので、勉強は先生が驚くほどにできたと思います。この狭い世界観がその後の私の人生を苦しませることになりました。この壁を破り、現在に至ることはあり得ないぐらいの価値観の転換と思います。
<社会人になってみて、高校生のうちにしておきたかった!と思うことがあれば教えてください。>
ネクラ人間(電車人間?)には無理だったと思いますが、もっと世界の問題に目を向けていたら、今の自分はもっと深く考え、まわりを動かす力をつけていたかもしれません。でも、自分に気がつき、現在のようなかかわりがもてたことに大いに感謝しています。
<仕事体験にあたり気をつけて欲しいことや、よく見て欲しいところはありますか?>
ここの職場での出来事は、短時間で、わかりやすい機会が持てるかはわかりませんが、社会貢献、経済と精神の自立ということを考えながら、新しい価値観の共有をしてもらえたら嬉しいし、ここに来た意味があると思います。従来の価値観からの脱却です。
<最後に、仕事体験に来る高校生に一言!>
評論家にならないで欲しい。どんなに小さいことでも意味があるということを常に考え、発見してください。お会いすることをとても楽しみにしています。
E番外編「さまざまな挑戦②~跡取り娘~」
今回は、いろいろあったけど家業を継ぎました、という女性たちのお話です。最初は造り酒屋です。
造り酒屋と言えば、今はお酒の仕込み時期、どの酒蔵でも大忙しです。その酒造りを担うのが杜氏(とうじ)さんです。酒造りには微妙な麹や酵母を扱うので、昔から女人禁制、女性が酒蔵に入るのはタブーとされたものです。
そういう常識を覆すように、近年酒造りに携わる女性がどんどん増えているようです。女性ならではの感性が酒造りに活かされるのだとか。
まずは、筆者の生活する会津には鶴乃江(つるのえ)という造り酒屋がありますが、その杜氏さんはお嬢さんの林ゆりさん、かれこれ15年ほどになりますでしょうか、彼女が醸した「ゆり」という純米大吟醸は今や鶴乃江を代表する銘柄となりました。
ところは変わって九州は福岡、久留米市にある山の壽(やまのことぶき)という造り酒屋、この老舗が福岡県種類鑑評会で堂々の知事賞を受賞しました。その経営者山口郁代さんは34歳のお嬢さん。ウェディングプランナーとして活躍していましたが、弟が家業を継がず、販売不振で倒産寸前というピンチにやむなく家業を継いだ、ということです。
しかし、このお嬢さんは杜氏こそしませんが、なかなかの経営手腕を発揮します。自分には酒造りの感性は無いと見極め、杜氏は外部から招聘して生産はすべて委ね、自分は予算、販売などの経営全般を取り仕切ります。
長い伝統の故に、なかなか新しいことに挑戦できず、毎年目減りする日本酒市場の中で閉塞感が強い造り酒屋ですが、こうした女性が増えることは、必ず新しい刺激を産むことになるでしょう。澱んだ水からは何も産まれないのですから、どんどん新しい水を入れて刺激と競争を産み出すことが重要だと言えます。
銀座の老舗呉服店を継いだ女性もいます。アメリカ留学からシティバンクへ入り、31歳で銀座支店長に抜擢された千谷美恵さん。彼女は後継ぎがいないために廃業を考えていた両親を説得し、銀座の呉服屋という古色蒼然たる世界に飛び込みました。お客さまはほとんど昔からの伝統芸能などの関係者で、どう見ても先細りは避けられません。そこで彼女は肩肘張らずに和服に親しめるよう、実家の呉服屋とは別に自分の店を出し、「着物がふたたび日常生活の一部になるまで力を尽くしたい」と意気軒昂です。
ちなみに、東京商工リサーチが保有する企業代表者データを分析したところ、全国で24万社あまりが女性社長、全体に占める割合は10,4%、昨年より0.3%増加しているのだそうですから、女性の経営者が活躍することは珍しくもないのでしょう。特に、飲食業や教育関連などを含むサービス業が37%を占め、男性社長を含む全体ではサービス業の割合が27%なので、女性の比率の高さが目立っています。また、ベンチャー企業勤務などを経て社会人経験5年以内で起業する若い女性も増えていて、ツイッターやフェイスブックなどのソーシャルメディアを活用して、企画・製造した製品を開発し、大手の物販企業へ売り込むパターンも多いそうです。
こうした女性の経営陣への進出の中でも、今回取り上げた方々は伝統的で女性には入りにくい業種で活躍している、という意味では多くの示唆を皆さんに与えるのではないでしょうか。東京のような都会でなくても、インターネットに依存せずとも、最初から無理だと諦めないことが結果につながると言えます。
E番外編「さまざまな挑戦①~若い女性~」
現代の日本社会はかなり強い閉塞感に覆われている、とよく言われます。ある種の出口なしで、未来に向けたわくわく感が無い、ともよく言われます。しかし、本当にそうでしょうか。今回のシリーズでは、そうした日本の中で、あるいは日本を出て、活躍しているさまざまな人たちにスポットをあててみたいと思います。それは、日本の中でもできる、ということですし、同時に日本を出てもできる、ということでもあるからです。
まずは、若い女性たちの活躍をお届けします。
最初は「若い」と言いますか、なんと1997年生まれの女子高校生。
彼女は椎木里佳さん、株式会社AMFの代表取締役で、“世界に日本のJKのかわいい文化を”をテーマにTokyo Teens TVを製作、サイバーエージェントが設立したJCJK総研(女子中高生の動向を調査・研究する目的)の編集長も勤めています。
彼女の場合は、お父さんがソニーから独立して映像コンテンツ制作会社を設立したこともあり、創業に適した環境に恵まれていたとも言えますが、とはいえ、日本のJKブームをうまく利用した商魂はたいしたものです(ご本人もえらく可愛いのでWebで探してください)。
ついで、1992年生まれの、これまた若い女性です。
彼女は大関綾さん、今日に至った流れをRe Life(リライフ、起業の魅力と現実を伝えることをコンセプトにした起業家インタビューサイト)からお届けしましょう。
「2006年11月、中学3年生、事業家を目指し、中小企業経営者の方々に交じってビジネスオーディションへ応募する。入賞後、さらに本大会へと進み月刊アントレ賞と来場者賞を受賞する。14歳8カ月という最年少記録も樹立する。
2007年4月、入学後、厳しい校則の壁が立ちはだかる。学校と交渉を繰り返すが在学中の起業は認められないという判断が下る。2007年11月 、東京都教育委員会に問い合わせ、起業が許される都立高校への再受験を決意し希望退学する。
2008年4月、入学後、2010年春の起業を目指してニュービジネスの研究に入る。 テーマを『社会の資本力にも組織力にも負けず、デフレーションにも影響を受けない独創的なビジネスの発見』と、定めた。2009年10月、Nobletieの試作品が完成。ビジネス基本構想が固まる。2010年1月、家族親戚とともにノーブル・エイペックス社を設立。代表取締役社長に就任(高校2年17歳)。」
また、彼女自らが語る家庭環境は以下のとおりです。
「私の両親は小学生のころ離婚して、母が女手ひとつで私と妹を育て上げました。母は、朝早くから夜遅くまで、私たちを養うためにほとんど毎日仕事をしていました。そんな母の姿を見て、将来は私が頑張って母に楽をさせてあげたいと思うようになったのです。最初は、母に楽をさせてあげるために社長になるという漠然とした目標しか考えていなかった私でしたが、実業家の叔父の影響を受け、好きな仕事をして、自由に生きていけるという経営者の魅力に段々と憧れを持つようになりました。」
お父さんが起業家という椎木さんとは違うプロセスで大関さんが起業へ向けたビジョンを暖めたことがわかります。
そして、今は自身で企画開発したネックウェア(ノーブルタイ、セパレーツタイ)を全国百貨店、スーツ量販店や海外で販売しています。こちらは年長なだけに、既にビジネスとして根付いた活動を展開しています。詳しくはこちらまで(http://ayaohzeki.com/)。
いかがでしょうか、凄いですよね。
こうした活気を見ると、日本もまだまだ捨てたものではないと思うのです。皆さんもこうした若い女性の挑戦を知る中から、ご自分の可能性を見つけて欲しいと思います。もちろん、起業がよいなどと言うつもりはありません。就職であれ、起業であれ、それ以外であれ、ご自分が選んだ道に敢然と挑戦していただきたい、ということです。
D番外編「私たちはどう見られているか」
私たちが市場(マーケット)に出てゆく場合、私たちが市場へどう働きかけるか、あるいは私たちが市場へ何を伝えるか、ということは非常に重要です。同時に、私たちが市場にどう見られているか、あるいは私たちが市場からどういうメッセージを受け取るか、ということも非常に重要です。
そういう観点に立った時、一つ参考になるお話を差し上げたいと思います。
それは、他の国の人たちはそれ以外の国の人たちをどう見ているか、ということです。
イギリスの観光庁が観光業界向けに作成した手引きがあります。イギリスを訪れる外国人客に、ホテル従業員はどう対応すべきか、というマニュアルのようなものとお考えください。
まずは、カナダ人、「カナダ人にアメリカ人と呼んではいけません」、なるほどです。カナダは強国アメリカの隣国としてある種の屈折した感情を持っています。また、カナダにはフランス語圏(ケベックやオンタリオなど)があり、英語万能の世界でもないのです。
ついで、ロシア人、「ロシア人は長身なので、天井の高い部屋を用意するべきだ」、そんなにロシア人は背が高かったかな、とも思いますが、イギリス人はそれほど背が高くないので、そうなのかもしれません。
ついで、フランス人、「面識のないフランス人にはほほ笑みかけたり、目を合わせたりしてはいけない」、これもうなずけますね、フランス人はプライバシーを大切にしますから。
ついで、ベルギー人、「ベルギーの複雑な政治や言語圏の話をしようとしてはいけない」、ベルギーがフランス語圏とオランダ語圏で分裂しそうな現状を日本人はどれほど知っているか、ということです。
ついで、ドイツ人とオーストリア人(要はドイツです)、「総じて遠慮がなく要求が厳しいため、無礼で攻撃的に見えるので、苦情には迅速に対応すること」、自尊心の強いゲルマン系だということでしょう。
ついで、オーストラリア人、「冗談で英国人をPomsという俗称で呼ぶのは、親しみを込めた表現だと心得ておくこと」、これはちょっと説明が要りますが、イギリスとオーストラリアはもともと同じ民族で、スポーツではライバル関係にありますから、お互いを俗称で呼び合うことが多いのです。で、イギリス人はオーストラリア人をオージー(Aussie)と呼び、オーストラリア人はイギリス人をPoms(イギリス人はすぐに日焼けして赤くなるのでザクロ=pomegranateのようだ)と呼ぶのです。ですから、馬鹿にしていると受け取るな、親しみの表現だ、と注意している訳です。
では、この手引きで日本人はどう書かれているか、です。
一つ、「日本人の要望には、たとえ具体的に言われなくても、すべて先回りして対応すること」。
二つ、「はっきりノーと言わず、もっと感じのよい言い方を考えなければならない」。
いかがでしょうか。
ここから見えてくるのは、私たち日本人は「質の高いサービスを求める」、そして「あからさまに否定されることを嫌う」と見られているということでしょう。
前段は悪い話ではありません。逆に言えば、日本のサービスが世界的に高い水準にあることの証明でもあるからです。また、そうした高いレベルのサービスは世界の多くの顧客に歓迎されるでしょう。
しかし、後段は問題です。異なる価値観が多様に存在する市場(世界市場)では、自分が当然だと考えている価値観が受け入れられるとは限りません。そうしたときに、否定を嫌っていては先が開かれません。常に新しい価値は異なる意見のぶつかりあいから、それを止揚(アウフヘーベン、古いものが否定されて新しいものが現われる際、古いものが全面的に捨て去られるのでなく、古いものが持っている内容のうち積極的な要素が新しく高い段階として導かれる現象)することで生まれるからです。異なる意見を否定すれば、解決は「足して二で割る」、あるいは「どちらかの意見を押し通す」という方法を辿るしかなく、新しい価値には結びつかないのです。
こうして見ますと、私たちが市場にどう見られているか、あるいは私たちが市場からどういうメッセージを受け取るか、という面から自分自身を振り返ることで別の自分自身を見い出せるのではないでしょうか。
D「海外観光客1千万人時代」
第191話「観光振興の行方」や第228話「外国人観光客」で、年間1,000万人を超える海外からの観光客の重要性をお伝えしてきました。なにせ、GDPを数兆円も押し上げる経済効果があるからです。どうやら昨年は目標の1,000万人を超えたようですが、それを題材とした日本経済新聞の連載から、皆さんのビジネスチャンスにつながるようなヒントを探したいと思います。
第一は、「接客のサービスは世界一だ」ということです。
これは、言葉にすることが前提となる英語圏とは異なり、言葉にしないで自分の感情を伝えようとする日本人を相手に商売を重ねてきた日本では、いわゆるマニュアル化を超えたサービスを一人一人の従業員が提供することが当たり前に行われています(もちろん、全然できていないところも少なくないのですが)。お客さまが言葉にできないが困っていること、あるいは困りそうなことを察知し、しかも押しつけがましくならずにサービスを提供する、そうしたシルクタッチ(絹の肌触りのようなきめの細かい、ざらざらしない)のサービスこそが日本の強みです。
ですから、これから海外からの誘客を考えるのであれば、こうしたサービスの質を上げることにまずは経営のベクトルをあわせた方がよいでしょう。少なくとも、アジアからのお客さまを見下げて、こんなものでよいのだ、と低いレベルにサービスをあわせるようでは間違いなく生き残れないでしょう。
第二は、「外国人の知恵を活かす」ということです。
日本で生活する外国人は、その数を増やしていますし、今では田舎の町や村でも外国人に会うことは珍しくなくなりました。この人たちの知恵や経験を海外からの誘客に活かすことです。私たちの目では価値があるように見えるものでも、外国人から見れば理解できないものもたくさんあるはずです。逆に、私たちからするとつまらないものでも、外国人から見れば興味深いものもたくさんあるはずです。
「集団が賢くあるための必要条件は、多様性、独立性、分散性である。」という格言をぜひ思い出して、どんどん自分と異なる視点を持つ人たちの意見を吸い上げてください。もちろん、皆さんの近くに住んでいる外国人もその対象なのです。
第三は、「滞在時間を増やす」ということです。
海外からの観光客の消費額は、その滞在時間に比例することがわかっています。その意味では、1時間でも長く、1日でも長く、地域に滞在していただくことです。そのためにどうしたらよいか、そこにアイディアを集めることが重要です。
そうした中に、行政的な手続きをどう減らすか、という問題もあります。行政では外国人の国内活動に多くの制約を設けています。国内の治安を維持するという彼らの立場からすれば当然のことです。しかし、可能な範囲でそれを効率化することは可能なはずです。
例えば、沖縄ではクルーズ船の入国審査を簡素化し、写真撮影などを省いて、パスポートを預かる仮許可書での入国を認めたそうです。そうしましたら、たった5分で上陸が可能になり、乗客は浮いた時間を惜しむようにアウトレットモールへ一直線、手続きの簡素化が生んだ時間が消費に回ったのです。
こうした行政手続きを簡素化させるには、それぞれの地域がその必要性を行政へ強く訴え、かつ行政の懸念する治安面での問題を解消する方向で努力することが欠かせません。そうした中から、海外からのお客さまが安心して楽しめる日本(あるいは地域)が見えてくるのではないでしょうか。
このコラムの読者は信州上田地域を中心として拡がりを見せていますが、皆さんの地域でもぜひ海外からの誘客に本気を出してみてはいかがでしょうか。間違いなく、地域の中小企業や小規模事業者にとって大きなビジネスチャンスがそこにあるのです。
C「胎動するASEAN経済共同体」
日本の中小企業や小規模事業者にとって重要な位置を占めている東南アジアについては、アジアとの付き合い方シリーズ、あるいは東南アジアに見る市場開拓シリーズでさまざまにお伝えしてきました。今回は、その背景にあるAEC(ASEAN経済共同体)のお話です。
既にASEANの関税自由化については何度か紹介してきましたが、2015年、そうです来年末にはAECとして、域内(フィリピンからミャンマーまでのASEAN全域)では関税が原則的にゼロになります。
例えば、タイで部品を作り、それをカンボジアへ送って組み立て、さらにベトナムで検品し、シンガポールの港から日本へ輸出する、というような物流システムが関税ゼロで実現できることになります。
これはまさに革命的なことです。経済市場において人口6億人の「国」ができあがるようなもので、しかもその国の中には賃金格差もあり、物価格差もある訳ですから、比較優位にある領域だけを上手に組み合わせれば、そこから得られる利益はこれまでとは比べ物になりません。例えば、人手のいる仕事は賃金の安いカンボジア、技術力の必要なところは先進のタイ、港湾設備はシンガポール、というような「よいとこどり」が可能になるのです。
さらに、将来的にはサービスや労働についても域内のやり取りや移動を自由化する構想も進められています。
こうなりますと、第247話で触れた海外進出の候補地として東南アジアの魅力がますます大きくなることがおわかりいただけるでしょう。
12月31日付の日本経済新聞によれば、ホンダはASEAN内で生産工程の分業化を進めていますし、ニコンはタイのデジカメ生産ラインの一部をラオスへ移管しましたし、豊田紡績もラオスに自動車用シートカバー工場を建設中です。
こうした動きは大企業が先導していますが、皆さんに注意していただきたいのは、「水牛のあとにはサギが群れる」ということです。大企業に動きが出れば、当然ながらその周辺に中小企業や小規模事業者にとってのビジネスチャンスも生まれるのです、ちょうど、水牛が草を食めば、昆虫が驚いて飛出し、それをサギが食べる、ということです。
読者の中からは、「海外海外と言いますが、それは大企業では簡単かもしれませんが、中小企業や小規模事業者では無理ですよ」という声も届きますが、決してそうではありません。
皆さんの地域でも探してみれば海外へ進出している、あるいは海外の市場を開拓している中小企業や小規模事業者を見つけることは容易なはずです。
筆者の生活する会津という田舎でも、オイルレスベアリングを製造している企業は従業員100名未満ですが、中国や東南アジアが大きな市場となっているようです。また、古くからの酒造業でもアメリカや韓国へ大吟醸と本醸造を輸出している蔵元があります。
ただし、AECで注意していただきたいのは、EUの経済統合とは異なり、政治統合はまったく意識していないという点です。EUの統合は「偉大なヨーロッパの再生」という高尚な仰々しさがあるのに対して、AECの統合は「みんなが豊かになればよいのだ」という実利的な猥雑さに満ちているということです。
それが長期的に東南アジアのプラスへ働くかどうかは、神様でもおわかりにはならないことでしょう。ですから、あくまでも「経済」という面に着目したAECであることを念頭に置いていただきたいと思うのです。
C「伝説の相場師が語るこれからの日本」
この原稿が掲載されるのは1月12日の予定ですが、実はこれが今年最初の出稿になります。そういう意味では、2014年という新しい年のお話を差し上げたいと思います。1月3日付けの日本経済新聞に石井久(いしいひさし)という方のインタビューが掲載されています。あまりにも興味深い、示唆に富んだ内容ですので、このインタビューからこれからの日本を少し読み解いてみたいと思います。
この石井さんは立花証券の元社長で、1953年のスターリン暴落(日経平均株価の下落率10%は当時最大、1987年のブラックマンデーまで34年間破られることはなかった)を直前に予測した「伝説の相場師」です。「相場師」などという言い方も今や死語に近いですが、ようは株式市場だけで生きている株のプロです。
で、その石井さんのインタビューから重要なことを抜き出してみましょう。
「向こう3年ほどは(株価は)高くなるとみる。2000年のIT相場の高値(日経平均株価20,0833円)は超えるだろう。(ただし)安倍政権が続き、経済重視の政治が続くことが条件だ。1989年末の最高値(日経平均株価38,915円)をうかがうような大相場にはならないとみている。」
いかがでしょうか、キーワードがいくつか散りばめられています。
① 安倍政権が続くこと
② 経済重視の政治が続くこと
③ しかし、株価はかつての最高レベルまでには戻らないこと
もう一つは。
「長期では日本経済を悲観している。人口減少下でも政府は移民政策に消極的だ。国の借金は1,000兆円に及ぶ。貿易赤字も定着し、必然的に円は弱くなる。個人資産の6割はオーストラリアドル債で保有している。キャピタルフライト(資本逃避)が本当に起きる前に、政府は行動しないといけない。」
いかがでしょうか、個人資産をたくさん保有する相場師の意見ですから、当然ある種の膨張されたメッセージ性があり、必ずしも客観的なものとは言えないかもしれません。
しかし、やはり重要なキーワードが見て取れます。
① 人口減少をどうするのか
② 借金の多さも問題だ
③ 貿易赤字もどうにかしないと
④ このままでは金持ちは日本から逃げ出すぞ
私たちはこうしたメッセージをきちんと受け止める必要があるでしょう。その中には、日本の近未来と、それを回避するための課題(イシュー)が散りばめられているからです。そして、そうした課題解決の道筋には必ず中小企業や小規模事業者のビジネスチャンスも隠されているからです。
いずれにせよ、今の日本には経済以外のことに血道を上げる余裕はありませんし、人口の減少、国債の増加、貿易赤字の拡大といった課題に向き合う必要があるのは明らかだと言えます。
B-C「アジアとの付き合い方38~インド⑤~」
南アジアシリーズの最後、インドも5回目で一段落にしたいと思います。今回は、インドという巨大な市場へ進出して成功を収めている外資企業の事例をご紹介します。残念なことに日本企業の成功事例はそう多くありません。筆者は日本企業の失敗は、インドの驚くべき多様性、複雑さに十分な注意を払うことを怠り、そこで起こる予想外の出来事に対する覚悟が足らなかったのが主な原因ではないかと考えています。既に第199話でホンダ・モーターサイクル・アンド・スクーター・インディア(HMSI)の事例を取り上げました。その背景にも、提携先のヒーロー財閥との経営上の食い違いや係争というインド特有の事情があったのですが、その後は独自路線で成功を収めつつあります。
スズキもマルチ・スズキ・インディアを1981年に立ち上げ、今や日本での生産台数100万台を超える年間117万台を生産し、インド市場の39%を握るまでに成長しています。しかし、ここに至る道筋は容易なものではありませんでした。経営をめぐるインド政府(提携先であり大株主)との争いは裁判にまで発展し、2012年夏には工場で暴動が発生し、一ヶ月もの間、操業停止に追い込まれたほどです。
しかし、こうした苦難を乗り越えて、ホンダ(二輪)とスズキ(四輪)がインドで確固たる地位を築けたのは、ひとえにそうした局面を迎えた時の経営者の覚悟があったからです。核実験が行われても、パキスタンとの紛争があっても、スズキはインドから撤退しませんでしたし、ホンダは圧倒的な優位に立つ、かつての提携先との競争にも怯みませんでした。こうした予想外の出来事に対する覚悟、そしてインドの驚くべき多様性、複雑さに対する十分な配慮、これが成功を導く唯一の道ではないかと思うのです。
例えば、今、インドの教育市場が熱いのです。インドの平均年齢は25歳と若く、インドにおける数学教育の先進性もあいまって、その教育ニーズは高いものがあり、インド政府も1兆円を超える予算を投じて、インドの競争力の根源である教育水準の維持向上に全力をあげる構えです。
こうした中、日米のIT関連企業は本格的なインド進出を進めています。具体的には、カシオはプロジェクターや関数電卓などの売り込みを図るために営業マンを増強し、リコーはNGOと提携して教育システムの事前調査に乗り出しました。
さらに、シスコシステムズ(アメリカのネットワーク関連企業)は遠隔学習システムを供給し、インテル(アメリカのIPUメーカー)は教員支援プログラムを通じて自社製品の販売拡大を狙っています。
ここで注目して欲しいのは、ユニリーバの成功事例です。ユニリーバでは、農村部の衛生環境の劣悪さを解消するため、一回使いきりの小さな袋入り石鹸を開発販売するとともに、子どもたちに石鹸での手洗い習慣の必要性を指導するプログラムに取り組み、「石鹸を買ってもらう」営利行為と、「貧しい農村部の健康を守る」という社会貢献を両立させ、巨大なインド市場を手に入れることができました。
こうした考え方でインドの教育市場へ参入するのであれば成功が期待できますが、単にプロジェクターを売る、パソコンを売るという行為では、ソーシャル・マーケティング(social marketing)で言うところの「新たな社会的価値の創造」はもたらされないのではないでしょうか。
さて、インドを5回にわたってお伝えしてきましたが、何分にも巨大な国であり、その社会、経済、文化、宗教も実に多様ですので、断面断面をお伝えするに止まったことをお詫びしたいと思います。これをきっかけにインドのさまざまな実態をお調べいただければ、21世紀の市場と言われるインドは、皆さん、そして中小企業や小規模事業者に近い存在になると思います。
B-C「アジアとの付き合い方37~インド④~」
インドの3回目では、その特殊な経済体制についてご紹介しました。いわば、インドのカントリーリスクと言えるものです。しかし、4回目の今回はインドの日のあたる部分についてお話を差し上げたいと思います。
インドの魅力は12億人を超える人口規模、とりわけ2億人を上回り、急速にその数を増やしている中間層にあり、まさに21世紀の市場として期待されています。
そして、もう一つの魅力が今回お話するIT基地としてのインドです。
世界中のIT企業がインド詣でに血道をあげる、というのがここ十年以上続いています。既にインドのソフトウェア輸出額は6兆円を突破し、今やインドを抜きにしたITビジネスは考えにくい、というほどの状況に至っています。
その原因はいくつかあげられますが、第一に、インドはイギリス統治下にあったこと、さらに国内の複雑な言語事情から第二公用語の英語を非常に重視しているため、インド人の英語でのコミュニケーション能力が高いことがあげられます。これは英語を基本言語とするITビジネスでは非常に優位性を発揮します。
第二に、インドは数学教育に特徴があり、ゼロの概念をいち早く導入したほか、二桁どうしの暗算を小学生に覚えさせ(インド式九九)、高校生ではかなり高いレベルの数学に挑戦させています。こうした数学的素養は、二進法を前提とするITの世界では大きなポイントになります。
第三に、インド人は中国人、アルメニア人、ユダヤ人に並ぶ世界四大移民集団と言われ、実に1,500万人を超えるインド人(印僑)が世界各地で活躍しています。このインド人ネットワークを通じたビジネスの展開は、極めて速く、かつ信頼性に富んでいることから、国をまたいだITビジネスでは多大なアドバンテージをもたらしています。
このようなインドの優位性に加え、高いレベルのIT技術者の月あたりコストが欧米では1万5千ドルにも達するに対して、インドでは5千ドル程度と3分の1に過ぎないという価格差もあいまって、2000年にはわずか4千億ドルに過ぎなかったインドのIT関連輸出額は、今や6兆ドルと実に15倍の規模にまで拡大しています。
その事業内容は、第一にITアウトソーシング(企業の管理プログラム構築など、コンピュータやインターネット技術に関連した業務の外部委託)、第二にビジネス・プロセス・アウトソーシング(BPO、総務・人事・経理・給与計算関係のデータ出入力業務やコールセンターなどの外部委託)、第三に完成品、あるいは半完成品としてのソフトウェアがあげられます。
そして、こうした業務に携わるIT企業もタタ・コンサルタンシー・サービシズ(コンサルティング・ソフトウェア開発・インフラ管理におけるITサービス、顧客はAT&T・ボーイング・ブリティッシュエアウェイズ・IBM・マイクロソフト・ゼネラルエレクトリックなど)、インフォシス・リミテッド(ビジネスアプリケーションやパッケージ・ソリューションが主体)、ウィプロ(組み込み系アプリケーションが強い)など、世界規模のITサービス企業が目白押しです。
こうしたインドのITサービス企業は、Accenture、IBM、HP、さらに日本のITメガベンダー(日本IBM、NTTデータ、日立製作所、NEC、富士通)との間で、時には市場を奪い合い、時には提携し、激しい競争を続けています。
2回目、3回目でご紹介したインドの宗教や経済体制の複雑さと比較して、こちらにはまったく違うグローバル・スタンダードの世界が拡がっている、そこにインドのさらなる多様性が現われていると言ってよいでしょう。
B-C「アジアとの付き合い方36~インド③~」
インドの3回目は、その特殊な経済体制です。インドが2兆ドルもの経済規模を抱え、2億人以上とも言われる中間層をますます拡大していることは、世界中の企業にとって垂涎の的となっています。まさに、21世紀の新しい市場です。しかし、そうしたインドの経済体制は必ずしも世界標準のそれではありません。今回は、そういった特殊事情に触れたいと思います。
まず、私たちが理解しなければならないことは、インドは1947年の独立以来、インド国民会議派(ネール、そして娘のインディラ・ガンジー=シク教徒による暗殺、そして孫のラジーヴ・ガンディー=スリランカ内戦で暗殺、次はひ孫のラフル・ガンジー)が主導する社会主義的計画経済が1990年まで続いたということです。これは、中国の改革開放が1978年にはじまったことと比較すると、中国経済の一回り遅れにインド経済があることを意味しています。
1991年からはLicense Raj(投資や産業、輸入の許可制)を廃止し、 多くの部門での外国からの直接投資を許容するなど、それまでの“Hindu rate of growth(インドの低成長)”と決別する方向性を示しています。
しかしながら、その改革開放は十分とは言えません。
第一に、社会主義経済の特徴である経済への国家の干渉は金融、交通、郵便などの広範な領域で残っています。例えば、エネルギー、不動産、保険、小売といった分野では、海外からの直接投資はいまだに規制されています。こうした外資規制を緩和することができるかどうか、次に述べる貿易収支の赤字をにらんで、今後の展開に注意が必要でしょう。
第二に、インドは恒常的な貿易赤字国であり、外貨準備高も乏しいという問題です。これは、数十年に及ぶ“Hindu rate of growth”の結果、輸入に頼らざるを得ない石油資源に見合う輸出産業を育てられなかったことのツケですが、毎年1,000億ドルを超える貿易赤字は経済成長に必要な原資をどこに求めるかという難しい問題を提起しています。これを外資導入で解決しようというのがインドの改革開放であった訳ですが、このところそのスピードは鈍化しており、今回のアメリカによる量的金融緩和政策の縮小がインドからの外資引き上げにつながるとすれば、インドの国際収支はかなり危険な状態に陥るかもしれません。
第三に、長年の社会主義的計画経済がもたらした複雑な行政構造及び煩雑な行政手続きであり、それがもたらす世界第95位という統治機構の腐敗です。東南アジアで悲惨なレベルにあるベトナムの第112位、フィリピンの第129位よりはましですが、第75位の中国よりも酷い状況は経済活動に対する大きな障壁です。
第四に、こうした閉塞的な経済状況の中で巨大な財閥が依然として強い力を維持している、ということです。いわば、社会主義的経済の中で国営企業が巨大な地位を占めるのと同じように、“Hindu rate of growth”はインド国内でタタ(パールシー系)、ビルラー、リライアンス、ターバル、マヒンドラ、ヒーローといった多くの財閥へ独占的な地位を与えたのです。従って、日本企業がインドに進出する際は、財閥との合弁、あるいは提携を図るケースが多くなっています。
こうしたインドの特殊性に注意することが、インドに進出する、あるいはインドを新しい市場として開拓する際には重要だとお考えいただきたいのです。そして、「中国と比べてインドは自由だ」などという錯覚は起こさないようにしていただければよろしいと思います。
B-C「アジアとの付き合い方35~インド②~」
インドの2回目は「宗教の博物館」とも言うべき多様性です。今から3,500年ほど前、中央アジアからイラン高原に至る草原の地からインド亜大陸へ押し寄せたインド・アーリア(コーカソイド)の人々は、天・地・太陽・風・火などの自然神を崇拝するバラモン教をもたらしました。このバラモン教の一大特徴は輪廻(りんね、生き物が死して後、生前の行為、つまりカルマ=業の結果、次の多様な生存となって生まれ変わること)であり、この業(ごう)から逃れるには修行と瞑想を重ねることで解脱(げだつ、悟り)の境地に入る、という考え方にあります。
皆さんはヨーガに見られるような修行者をご存知でしょうが、あの修行は解脱に入る道として、今もインドの多くの人々の尊敬を集めています。
しかし、こうしたバラモン教は生前に犯した罪の結果、卑しむべき存在として生まれ変わる(輪廻転生)というカースト制度につながったため、それを批判する仏教やジャイナ教という新しい宗教を産み出しました。
このうち、ジャイナ教は「真理は多様に言いあらわせる」と説き、一方的判断を避けて「相対的に考察」することを重要視し、同時に戒律に従って正しい実践生活を送ることを勧めたのです。今ではインドに450万人を数えるに過ぎませんが、そのほとんどが商人であり、経済的な地位は低くありません。
一方、私たちに身近な仏教は輪廻と解脱を重んじながらもカースト制度を否定し、その普遍性から南はスリランカから東南アジアへ拡がる上座部仏教、北はガンダーラからシルクロードを辿って中国、チベット、朝鮮半島、日本へ拡がる大乗仏教へと変貌しながら教線を伸ばすことになりました。現在、世界ではキリスト教23億人、イスラム教15億人、ヒンズー教9億人に続く4億人の信者を抱えています。しかし、発祥の地インドではヒンズー教やイスラム教の興隆とあわせて衰退の一途を辿り、今はわずかに900万人を数えるに止まっており、ほとんど社会的な影響を持っていません。
一方、一時期ジャイナ教や仏教に勢力を奪われたバラモン教は、土俗の多様な信仰を吸収しながらヒンズー(ヒンドゥー)教へと変貌を遂げ、無数とも言える神々と、その神々が与えるさまざまな利益(長寿、健康、繁栄、蓄財など)を用意することによって、インド亜大陸に生きる人々の圧倒的な信仰を集めることになったのです。このため、現在のインドでは(ヒンズー教から分派したと考えられる)シク教、ジャイナ教、仏教を信仰する人も憲法上は広義のヒンズーとして扱われているほどです。このように、ヒンズー教は非常に多様な信仰形態を有しており、インドの大地同様の複雑さを現わしていると言えるでしょう。また、ヒンズー教はさまざまな聖典や叙事詩でも知られており、その一つである“ラーマーヤナ”はそのドラマ性からインドから東南アジア一帯へと伝わり、タイではラーマキエンという舞踊劇となり、インドネシアでは影絵芝居の演題として親しまれています。この“ラーマーヤナ”に登場する猿の王ハヌマーンは、皆さんの親しんだ西遊記の孫悟空のモデルにもなっているほどです。
こうしたヒンズー社会に12世紀以降、カイバル峠を下って侵攻してきた中央アジアの人々がもたらしたのがイスラム教で、19世紀にムガール帝国が滅びるまでは一貫してインドの支配階層はイスラム教徒でしたので、インド亜大陸でたくさんの信徒を獲得することになりました。その結果がパキスタンやバングラディシュの分離独立につながりましたが、今でもインドに1億5千万人を数えており、ヒンズー教徒との対立はムンバイテロ事件やヒンズー至上主義者によるイスラム教徒襲撃などの緊張を産み出しています。
ここでインド的なのが、シク教とゾロアスター教です。シク教は16世紀にヒンズー教とイスラム教の両方の影響から生まれたものですが、パンジャーブ地方を中心に2,000万人ほどの規模となっています。ちなみに、今のインド首相であるマンモハン・シンはシク教徒であり、ターバン姿で有名ですが、髪の毛と髭を切らず、頭にターバンを着用する習慣はシク教徒の男性によく見られ、それがいつしかインド人=ターバンというイメージを作ることになりました。
ゾロアスター教は言うまでもなく古代ペルシアを代表する宗教ですが、世界中でわずか10万人ほどの信徒の多くがインドで生活しており、パールシー(ペルシアから来た人たち)と呼ばれています。このパールシーは数こそ本当に少ないのですが、イギリス統治下で貿易に従事したことから大きな財力を蓄え、インドの二大財閥の一つタタ財閥はパールシーが起こしたものです。また、皆さんもご存じのクイーンのボーカリストであるフレディ・マーキュリーは、東アフリカのタンザニアで生まれたパールシーです。
いかがでしょうか、まさに「宗教の博物館」インドの複雑さが少しおわかりいただけたでしょうか。
B-C「アジアとの付き合い方34~インド①~」
「東南アジアだけではなく、中小企業や小規模事業者が市場として考えるアジアの他の国々も紹介して欲しい」というご意見をいただきまして、東南アジア以外の国々をご紹介してきました。いずれも中小企業や小規模事業者が今後考える海外進出の相手となる可能性がありますし、また、日本とは違う環境の中での市場を想像することは、日本国内におけるビジネスチャンスを考えるヒントにもなると思うからです。東南アジア、東アジア、北アジア、中央アジアとつないできて、南アジアの最後はインドです。しかし、人口は12億人を超え、日本の8倍以上の巨大な面積に加え、数多くの言語と数多くの民族、数多くの宗教を抱えるこの大国を伝えるのは難しいことです。そこで、インドに入る前にその周辺をざっとお知らせし、さらにインドについても数回に分けてご紹介することにご理解をいただきたいと思います。
今回は、インドの表層をさらってみたいと思います。そして、このあとはインドの民族や宗教、インドの経済、インドのカントリーリスク、インドにおける外国企業の市場開拓などに触れてゆきたいと思います。
インド、インド亜大陸の大部分を占める巨大な陸塊です。北にヒマラヤ山脈、西に広大なタール砂漠、東にミャンマーを隔てるアラカン山脈と、インド亜大陸は「陸からの侵入が難しい」孤立した地形となっている反面、貿易風に恵まれ、「海に開かれ陸に閉ざされた」インド亜大陸の特性は第244話でお伝えしたとおりです。
この日本の8倍以上もある大地に実に12億人を超える人々が生活し、その人口は今でも毎年1千万人以上も増え続け、2030年代までには中国を抜くのは確実です。
既に国としてのGDPも2兆ドル近くに達しており、これは世界第10位、パキスタンの10倍におよび、ブラジル、ロシア、イタリア、カナダと並ぶ水準なのです。また、一人あたりGDPは1,500ドルとベトナム並みの水準ですが、いわゆる「中間層(世帯所得が5,000~35,000ドル)」は現時点で2億人を超え、15年間で人口の7割に達するとの予想もあることから、その市場価値は大変大きくなりつつあります。
この経済規模は、まさに21世紀の魅力ある市場といってよいでしょう。
一方、その内情は実に複雑です。
民族的にはインド・アーリア系(コーカソイド)の諸民族、先住のドラヴィダ系(オーストラロイド)の諸民族が混交し、歴史的に統一国家の経験がほとんどないことからも、地域的にさまざまな言語グループが分立する状態になっています。例えば、インド全体としての公用語となっているヒンディー語(インド・アーリア系)ですが、その話者が5億人であるのに対して、ベンガル人の話すベンガル語(インド・アーリア系)も2億人、南部インドに多いタミール語(ドラヴィダ系)は7,500万人、北部に多くパキスタンにも話者が分布するウルドゥー語(インド・アーリア系)は6,000万人と、日本的には「方言」レベルの言語が国家並みの人口を抱えています。
さらに、それを複雑にしているのが宗教です。
私たちになじみの深い仏教をはじめ、さらに古い歴史を持つジャイナ教、バラモンからの伝統に根ざすヒンズー教、パキスタンやバングラディシュを産み出したイスラム教、シン首相が信徒であるシク教はおろか、東方諸派の影響が残るキリスト教の諸宗派、古代ペルシアで栄えたゾロアスター教(パールシー、人口は少ないが経済力で大きな力を占めています)など、まさに宗教の博物館とも言うべき多様性を残しています。
このように、民族、言語、宗教といったさまざまな面で多様なインドは、12億人を超える「人間の玉手箱」のような様相を呈していると言えるでしょう。ここが、多民族国家でありながら漢民族と中国文化が圧倒的な地位を占めている中国との大きな差です。この違いをきちんと認識していただくことが、インドを把握する近道かもしれません。
『大学と長野県企業との情報交換会』開催のご案内
第2回となる、『大学と長野県企業との情報交換会』の長野会場での開催のご案内です。関東・首都圏の大学の就職担当職員の方々と、長野県企業の皆様
との接点を増やしていただくことを目的に下記の交流会を企画いたしました。
学生の意識や就職動向を理解していただくとともに、大学とのきめ細かな信頼関係づくりの機会として、お役立ていただければ幸いです。
「大学と長野県企業との情報交換会」
■開催日時:平成27年2月18日(水) 12時30分~15時 (受付:11時30分~)
■場 所:メルパルク長野(長野県長野市鶴賀高畑752-8) 1F ホール
■内 容:
□特別講演会「長野県経済の現状と今後の展望及び産業構造から見る採用環境について(仮称)」
講師:長野経済研究所 調査部 部長代理兼上席研究員 宮前 肇様
□情報交換会(1部・2部)
1部:各企業ブースに大学等のご担当者様が訪問する大学訪問型
2部:各大学等ブースに企業のご担当者様が訪問する企業訪問型
※1部・2部ともに、15分区切りの時間割で進行いたしますのでご了承下さい
※休憩時間を利用し、運営側で企業ブースと大学等ブースを入れ替えます。
□会場配置・訪問形式
大学側ブースを設け、企業ご担当者様から、自由にブースにお伺いしていただきます。
■参加企業様:長野県内60社程度
■参加大学様:関東・首都圏を中心とする60校決定
【お問合せ先】
AREC・Fiiプラザ事務局 担当:草野
TEL:0268-21-4377 FAX:0268-21-4382
Mail: arec10アットarecplaza.jp
※アットを「@」に置き換えてください。
『大学と長野県企業との情報交換会』開催のご案内
第2回となる、『大学と長野県企業との情報交換会』の長野会場での開催のご案内です。関東・首都圏の大学の就職担当職員の方々と、長野県企業の皆様
との接点を増やしていただくことを目的に下記の交流会を企画いたしました。
学生の意識や就職動向を理解していただくとともに、大学とのきめ細かな信頼関係づくりの機会として、お役立ていただければ幸いです。
「大学と長野県企業との情報交換会」
■開催日時:平成27年2月18日(水) 12時30分~15時 (受付:11時30分~)
■場 所:メルパルク長野(長野県長野市鶴賀高畑752-8) 1F ホール
■内 容:
□特別講演会「長野県経済の現状と今後の展望及び産業構造から見る採用環境について(仮称)」
講師:長野経済研究所 調査部 部長代理兼上席研究員 宮前 肇様
□情報交換会(1部・2部)
1部:各企業ブースに大学等のご担当者様が訪問する大学訪問型
2部:各大学等ブースに企業のご担当者様が訪問する企業訪問型
※1部・2部ともに、15分区切りの時間割で進行いたしますのでご了承下さい
※休憩時間を利用し、運営側で企業ブースと大学等ブースを入れ替えます。
□会場配置・訪問形式
大学側ブースを設け、企業ご担当者様から、自由にブースにお伺いしていただきます。
■参加企業様:長野県内60社程度
■参加大学様:関東・首都圏を中心とする60校決定
【こちらは定員に達したため、募集を締め切らせていただきました】
【お問合せ先】
AREC・Fiiプラザ事務局 担当:草野
TEL:0268-21-4377 FAX:0268-21-4382
Mail: arec10アットarecplaza.jp
※アットを「@」に置き換えてください。
B-C「アジアとの付き合い方33~ヒマラヤ周辺~」
「東南アジアだけではなく、中小企業や小規模事業者が市場として考えるアジアの他の国々も紹介して欲しい」というご意見をいただきまして、東南アジア以外の国々をご紹介してきました。いずれも中小企業や小規模事業者が今後考える海外進出の相手となる可能性がありますし、また、日本とは違う環境の中での市場を想像することは、日本国内におけるビジネスチャンスを考えるヒントにもなると思うからです。東南アジア、東アジア、北アジア、中央アジアとつないできて、南アジアの四番目はヒマラヤ周辺のネパールであり、ブータンです。
中国とインドが戦ったことがあるのを忘れている人が多いと思いますし、近頃もちょっとした武力衝突がありました。また、インドはパキスタンとカシミールの地を巡って緊張関係にあり、中国とパキスタンの間にも国境を巡る争いがあります。
それはどうしてでしょうか。
それは、長い歴史の中でチベットが四方にさまざまな影響を与えてきたことに原因があります。チベットを今の中国におけるチベット自治区に限定すると話は見えません。チベット仏教を通じて、チベットの影響力はカシミール東側(ラダック)、ヒマラヤ山脈の西麓に位置するブータンやシッキムなどに拡がっていきました。このチベットを支配下においた清朝の歴史を継承する中国が、こうした古き広き“チベット”に対する権利を主張する根拠がそこにあります。
さて、そうしたヒマラヤ周辺の諸国家、諸地域の中で、今回はネパールとブータン、そして今はインドに含まれたシッキムを簡単にご紹介しましょう。
人口約2,600万人、一人あたりGDP約700ドルのネパールは、ヒンズー教が支配的な国としていささか特殊な位置を占めます。民族的にも過半をインド・アーリア系のパルバテ・ヒンドゥー(山地のヒンドゥー教徒の意味)が占め、そこにさまざまなチベット系の少数民族が混在しています。また、イギリス統治下で傭兵や茶園労働力などとして利用されたため、周辺に多くの移住者を送り出しています。
ヒンズー教の関連からインドとの関わりが深く、インドとネパールの国民はビザなし、パスポートなしで行き来でき、ネパール国民はインドで自由に働くことができるほどです。
また、山襞に隔てられた地形から少数民族は互いに孤立して生活する傾向にあり、そうした地形的特性と民族問題、貧困問題を背景としてネパール共産党統一毛沢東主義派(マオイスト)という政治勢力が農村部に大きな力を持ち、王制廃止後の今でも都市部と農村部での政治的緊張は続いています。
シッキムはかつてシッキム王国として知られ、ネパールとブータンの間に位置しますが、ダージリンで知られる茶葉生産が盛んになったため、もともとのチベット系が人口の25%であるのに対し、茶園労働力として流入していたネパール系が75%を占めるようになりました。このため、王国の政情は不安定となり、最終的には1975年、インドに併合されたのです。
ブータンはそのシッキムの東にある人口72万人の小さな仏教国で、チベット仏教の宗派争いで敗れた一族がチベットから独立した歴史を持ちます。
隣接のシッキムがネパール移民の問題によりインドへ併合された経過に強い危機感を抱き、「ブータン北部の伝統と文化に基づく国家統合政策」を採用してブータン南部に多いネパール移民を排除し、さらにチベット系民族衣装着用の強制、チベット系ゾンカ語の国語化、伝統的礼儀作法(ディクラム・ナムザ)の順守などのアイデンティティ政策を進め、今日では国民総幸福量、いわゆる幸せの指標であるGNH(Gross National Happiness)により、「世界一幸せな国ブータン」を目指すなど、独自の国づくりをひた走りにしています。日本ではジグミ・ケサル・ナムゲル・ワンチュク国王夫妻の2011年の来日で一躍脚光を浴び、一時はブータンブームが起きたほどです。
いずれも規模の小さな国家群ですが、こうしたインド周辺の状況を知っていただけると、次回からのインドの紹介で参考になると思います。
B-C「アジアとの付き合い方32~スリランカ~」
「東南アジアだけではなく、中小企業や小規模事業者が市場として考えるアジアの他の国々も紹介して欲しい」というご意見をいただきまして、東南アジア以外の国々をご紹介してきました。いずれも中小企業や小規模事業者が今後考える海外進出の相手となる可能性がありますし、また、日本とは違う環境の中での市場を想像することは、日本国内におけるビジネスチャンスを考えるヒントにもなると思うからです。東南アジア、東アジア、北アジア、中央アジアとつないできて、南アジアの三番目はスリランカです。
かつてはイギリス人からセイロンと呼ばれ、“シュリー・ランカー(シンハラ語で聖なる島)”を正式名称とすることからもわかるように、スリランカはかつてイギリス統治下にあり、シンハラ人が多数を占めるインド洋の島です。日本人にとっては「紅茶」「仏教」「宝石」の島であり、近年は明石康さんも尽力した25年以上の激しい内戦でも知られました。
この島は古く2,500年ほど前にインド亜大陸北部からインド・アーリア系(コーカソイド)のシンハラ人が渡来してから歴史に登場することになります。もっとも、山岳地域にはヴェッダ人(ワンニヤレット、森の民)というオーストロイドの狩猟採集民が知られていますので、人類ははるか昔からこの島に住んでいました。その後、今から2,300年ほど前にインドから仏教(戒律を重んじる上座部仏教)が伝わり、それ以降、綿々と仏教への厚い信仰で知られています。
また、この島はインド亜大陸と狭く浅い海峡を隔てるだけの位置にありますので、古くからインド南部のタミール人(ドラヴィダ系、オーストライド)の渡来も多く、イギリス統治下においては「少数民族を優遇して多数民族を抑え込む」政策のためにインドから新たにタミール人が連れて来られたために、人口2,000万人のうち、シンハラ人が約1,500万人、タミール人が約300万人、イスラム教徒のムーア人(言語的にはタミール系)が約200万人という民族構成となっています。
こうした民族構成のために、独立を目指して多数派のシンハラ人では仏教復興運動が起こり、北インド出自と仏教を基本的要素とする民族意識が高まったために、シンハラ仏教ナショナリズムが登場し、これに反発するタミール人との間で内戦にまで緊張は高まることになりました。
タミール人はスリランカにこそ約300万人ですが、インドでは約6,000万人を数える大きなコミュニティであるため、スリランカ内戦にはインドも深く関与することになり、インド元首相のラジーヴ・ガンディー、スリランカの現職大統領ラナシンハ・プレマダーサが暗殺され、国内避難民30万人を数えるなど、スリランカ内戦はまさに泥沼状態に陥りました。それが、ノルウェーをはじめとする国際社会の働きかけにより、ようやく2009年に終結を迎えることとなりました。
さて、こうした四半世紀にわたる内戦はスリランカ経済に大きな爪痕を残しましたが、もともと温暖な気候で農業が盛んであり、勤勉な国民性ともあいまって、アパレル、観光などで高い成長を示しつつあります。一人あたりのGDPもフィリピンを超える3,000ドル近くにもなり、経済成長率も6%を上回っていますので、ますます今後が期待できます。政情の不安定さというカントリーリスクがなくなれば、豊かなこの島の未来は明るいものと言えるでしょう。
B-C「アジアとの付き合い方31~バングラディシュ~」
「東南アジアだけではなく、中小企業や小規模事業者が市場として考えるアジアの他の国々も紹介して欲しい」というご意見をいただきまして、東南アジア以外の国々をご紹介してきました。いずれも中小企業や小規模事業者が今後考える海外進出の相手となる可能性がありますし、また、日本とは違う環境の中での市場を想像することは、日本国内におけるビジネスチャンスを考えるヒントにもなると思うからです。東南アジア、東アジア、北アジア、中央アジアとつないできて、南アジアの二番目はバングラデシュです。
筆者はまだ「ベンガル」と言われた方がわかりやすいのですが、バングラデシュはベンガル語で「ベンガル人の国」という意味で、植民地インドがパキスタンとインドに分離独立する際に、地理的、民族的な条件ではなく、イスラム教というだけの共通項ではるか1,000km以上も西に隔てられたパンジャーブとともにパキスタンを構成しましたが、さすがに一つの国を維持することができず、半年間で300万人を超える犠牲者を出した独立戦争により、インドの支援を受けて1971年にバングラデシュとなった国です。
こうした独立の経緯から、どの宗教を信仰しているかという点よりも、同じベンガル民族であるという意識の方が重要視される傾向にありますので、パキスタンのようにイスラム至上という考えは少なく、少数派のヒンズー教徒や仏教徒もさほどの差別を受けずに生活できているようです。ただし、ミャンマー国境沿いにはベンガル民族に属しない少数民族の問題が残されています。
また、政情に関してはパキスタンと同様で軍の影響が強く、民政が必ずしも安定しないという問題を抱えています。
人口は1億5千万人を超えて世界第7位、ガンジス川流域のデルタ地帯は日本の4割程度と狭いため、世界で最も人口密度の高い国です。
経済的にはパキスタンよりも状況が悪く、一人あたりのGDPは700ドル程度と世界の最貧国の一つに上げられています。
主な産業は農業ですが、農業というよりも「米」の国です。ガンジス川のデルタに加え、モンスーン気候で雨に恵まれていることから、二期作、三期作も可能で、穀物の自給率は90%を超えています。
また、繊維業も盛んで、近年はソーイング(縫製)の受け皿として大いに注目を浴びています。私たちの衣類もこれまではメイドインチャイナが幅を利かせていましたが、スウェーデンのH&M(ヘネス・アンド・マウリッツ)や、「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングといった世界のアパレルメーカーがバングラデシュにアウトソーシングの生産拠点を設けていますので、これからはメイドインバングラデシュが主流になるかもしれません。なにせ、バングラデシュの輸出の8割は衣料品が占めているほどです。
ただし、その反面、生産拠点の多くは中小の工場であり、その労働環境も劣悪ですので(ダッカ近郊ビル崩落事故でビル内の縫製工場に勤める1,000名以上が死亡しました)、今後はよりフェアトレード的な観点に立ったアウトソーシングが求められるでしょう。
なお、パキスタン同様にバングラデシュも海外への出稼ぎに40万人を超える人々が従事しており、出稼ぎ先はイスラム教国が多く、最大はサウジアラビアで、クウェートやアラブ首長国連邦などの湾岸諸国にも多く、東ではマレーシアやシンガポール、日本でも1万人ほどの在日バングラデシュ人が存在しています。
B-C「アジアとの付き合い方30~パキスタン~」
「東南アジアだけではなく、中小企業や小規模事業者が市場として考えるアジアの他の国々も紹介して欲しい」というご意見をいただきまして、東南アジア以外の国々をご紹介してきました。いずれも中小企業や小規模事業者が今後考える海外進出の相手となる可能性がありますし、また、日本とは違う環境の中での市場を想像することは、日本国内におけるビジネスチャンスを考えるヒントにもなると思うからです。ということで東南アジア、東アジア、北アジア、中央アジアとつないできました。いよいよ、アフガニスタンのカイバル峠を下って、インド亜大陸へ入りましょう。そこは、パンジャーブの地です。
パンジャーブ、それはペルシア語で「5つの水」を意味するパンジュ・アーブ、インダス川とその4つの支流が織りなす豊饒の地です。
ヒマラヤ山脈の西端、チベット高原から流れ出したインダス川は、ヒマラヤ山脈に沿って東進するガンジス川と並んで、5,000年前には青銅器と小麦によるインダス文明を産み出したインド亜大陸の母なる川です。
しかし、そのインド亜大陸はイギリスの植民統治から独立する際に、人口の多数を占めるヒンズー教徒と少数派のイスラム教徒の間の勢力争いから、イスラム教を国教とするパキスタンと、それ以外のインドに分離する道を選びました。インド独立の父と言われるガンジーが「一つのインド」を訴えましたが、イスラム教徒が多数を占めるパンジャーブと、遠く西に離れたベンガルはパキスタンという、イスラム教だけで結びつき、東西に分離した国家を産み出したのです。
そうです、そのパンジャーブが今のパキスタンとなったのです。
そうした建国の経緯からパキスタンはイスラム教を国教とし、憲法で公式にイスラムの理念にのっとった政治を行うことを宣言するなど、今日でもイスラム法(シャリーア)や部族社会が一定の影響力を持っています(特に西北のアフガニスタンとの国境地域)。
また、このあとに紹介するバングラデシュ(ベンガル)の分離独立やインドとの戦争をはじめ、さまざまな政情の不安から、クーデターを繰り返す半世紀を過ごしてきました。
このため、人口は世界第6位の1億8千万人という規模にあり、2050年には3億人を超え、中国・インド・米国に次ぐ世界第4位の人口大国になると予想されていますが、一人あたりのGDPは1,000ドル台とラオスと同じレベル、識字率も6割を下回り、1日2ドル未満で暮らす貧困層は9,700万人と国民の半数近くを占めています。
こうした状況に加え、イギリス統治だった関係で英会話が可能な人が多いことから、海外で働くパキスタン人はかなりの数に上っています(出稼ぎ送金は月額10億ドル)。
これだけの人口規模を抱えていますので、その市場的可能性は大きいのですが、最大のカントリーリスクである政情不安がどう落ち着くのか、この見定めが重要な国と言えます。
産業的には農業と繊維業が主なもので、地下資源に乏しいことからエネルギーをはじめとする輸入超過が続いており、IMF(国際通貨基金)をはじめとする国際支援が無ければ輸入代金にもことかく現状です。
A「海外直接投資」
年明けは縁起のよいように日銀短観ではじめましたが、引き続き景気のよい話を差し上げます。それは、海外直接投資、とりわけM&Aが記録的な水準に伸びている、ということです。
海外直接投資は、要するに投資先の企業に対する株式の取得、貸付、債券保有、不動産の取得ということですが、この中でM&A(mergers and acquisitions、合併と買収)は株式を取得することでその企業を買うということに他なりません。
12月17日付けの日本経済新聞によれば、昨年の日本企業による東南アジアでのM&Aは
100件近く、その額も1兆円近いレベルに達しています(海外子会社設立も含んで)。
しかも、これまでのような製造業、不動産などに限らず、金融、小売、食品などの多様な業界に及んでいることが特徴的です。
例えば、金融業では三菱東京UFJ銀行がタイで銀行を約5,600億円で買収して話題となりましたが、都市銀行に限らず地方銀行、あるいは信用組合でも東南アジアへの進出は急を告げています。滋賀銀行、北陸銀行、横浜銀行、福岡銀行などが事務所を開設する、あるいは七十七銀行がインドネシア4位の商業銀行バンクネガラインドネシアと提携、池田泉州銀行がタイ4位のカシコン銀行と組み、大垣共立銀行がベトナム最大のベトコム銀行と業務協力の覚書を交わすなど、本当に枚挙に暇がありません。慎重居士で有名な金融業界での東南アジアブームは、そこに確実な資金需要があることを物語っています。金鉱が発見されたアメリカ西部の町には必ず銀行が開かれ、絹ブームで浮かれる東北や関東の町には日銀の支店がいち早く設けられるのです。
それ以外の業界でも、アサヒビールはインドネシアの飲料水企業を買収し、アートネイチャーはカンボジアに生産工場を造り、ユニ・チャームはミャンマーの日用品大手を買収し、という具合です。
では、どうして東南アジアなのか、です。
それは、一つにはASEANが2015年には関税を全面的に廃止して大きな経済圏ができること、一つにはチャイナプラスワンで人件費の高騰が続き、経済の不安定化が懸念される中国以外に海外拠点を築こうという流れが加速化していること、一つには東南アジアの巨大な人口規模と所得向上が大きなビジネスチャンスになっていること、などがあげられます。
そして、それは同時にこうした海外進出を支える「人材」に対する大きな需要をもたらしています。このところの日本企業の外国人登用、留学生採用といったグローバルな人材確保の大きなうねりは、皆さんの今後にも大変な影響を与えると予想されます。
こうした需要に対する備えをどうするかが問われているのです。そうです、皆さん自身のグローバル化が問われています。
その際にお考えをいただきたいのは、「安易な『体験』をいくら積み重ねたところで、真にグローバルな人材に育つことは難しいのであって、かえって『体験』そのものが自己目的化してしまうおそれすらある。」という文部科学省平成21年度国際開発協力サポートセンター・プロジェクト「グローバル人材育成のための大学教育プログラムに関する実証的研究」の厳しい指摘です。
第68話で触れたように、「『経験した』ということで満足するのではなく、その一つ一つの行動や現象から、共通する要素(共通項)を見つけ体感することが、どのような変化の時代が来ても対応できる人間になれるのではないでしょうか。」という読者の指摘はまさにそれを指していると言えるでしょう。
自分がどういった人間になりたいのか、というビジョンを明確にし、それに近づくために「経験」を重ね、そうした「経験」の中から普遍的に価値のあるもの(さまざまな局面でも応用できるもの)を紡ぎ出す、こうした流れをぜひ念頭にしていただきたいと思います。
C「年頭に際して」
皆さん、新年おめでとうございます。5月1日にはじまったこの連載コラムにお付き合いをいただきまして、本当にありがとうございます。このコラムは、「地域中小企業の人材確保・定着支援事業」の一環としてお届けするものです。このため、このコラムでは①これから社会に参加する若者の皆さんに「働く」、あるいは「ビジネス」ということがどういったものなのかを知っていただく、②中小企業や小規模事業者で働くために重要な知識やスキル、あるいは“社会人基礎力”や一般常識を身につけていただく、③中小企業や小規模事業者の海外進出や市場開拓において必要とされるさまざまな国や地域の情報や文化風土などの基盤的な知見を知っていただく、そうしたことを大きな狙いとしています。
そして、昨年はあわせて245話のコラムをお届けしました。残すところ、あと45話になりますが、引き続きご愛読をお願いいたします。
さて、年頭ですので、年頭らしく昨年を振り返りますと、年初に10,688円であった株価がこれを出稿している段階では15,000円を超えているのですから、株の時価総額という観点で日本経済を見ますと、5割近く図体が膨らんだと言えます。
これは企業の価値がそれだけ膨らんだということにつながりますので、さまざまな点で企業は経営の自由度を増しています(資金不足、利益不足という心配が減っています)。これは、皆さんの今後を考える上では朗報と言えます。
それは、日銀短観にも如実に現われています(第66話参照)。
日銀が12月16日に発表した12月の全国企業短期経済観測調査(短観)を見ますと、中小企業(非製造業)では現時点でのDI(景気動向指数)はプラス4と、実に21年10ヶ月ぶりにプラスに転じました。第一四半期の時点では、まだマイナス4でしたので、日本経済の回復は中小企業にまで及びつつあると言えるでしょう。
これを大企業(製造業)で見ますとプラス16と、これも6年ぶりに高い水準にあり、先行きの予測もプラス14ですから、日本経済の旗頭と言える製造業で景気回復がかなり拡がっていることがわかります。これは、設備投資計画も同様で前年度比で5%近い増加を見込んでいますので、長年設備投資を抑えてきた日本の製造業もいよいよ設備更新期に入りつつあると言えるでしょう。
こうした景気の回復感は、雇用にも影響を与えており、自社の人員が「過剰」から「不足」を差し引いた雇用人員判断では全体でマイナス10に達していますので、人手不足を感じている企業がかなりの割合になりつつあるとわかります。このため、三大都市圏におけるアルバイト・パートの募集時給は953円と前年比0.7%の増加(リクルートジョブズ調べ)、これは5年ぶりの高い水準です。同じように、現金給与の総額も10月には前年比0.1%の増加と、正社員のボーナスやパートの時給などを中心として働く人の懐具合は改善されつつあります。
これから社会へ出る皆さんには、少なくとも景気が後退している局面よりも、景気が回復している局面の方が有利なのは当然です。その意味では、嫌な言い方ですが、「買い手市場」から「売り手市場」に変わりつつありますので、自分を安売りせずに、対象となる会社のビジョン、価値観、経営者などをよく把握してください。今回、厚生労働省がようやく立ち入り調査を行ったブラック企業などは選ばれませんように、十分ご注意ください。