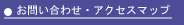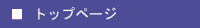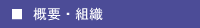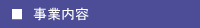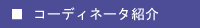過去の記事
C「アジアのカントリーリスク~エネルギー~」
中小企業や小規模事業者の市場開拓で重要な位置を占めているアジア、しかし、そこには多くのカントリーリスクも存在しています。こうしたカントリーリスクに注意することが、中小企業や小規模事業者の海外進出には欠かせません。例えば政治体制、中国やベトナムのように今でも一党支配を続けているかぎり、その体制が動揺する、あるいは崩壊する危険性は常に存在します。例えばインフラ、東南アジアの多くの地域では道路や橋梁、港湾といったインフラは未整備の状況です。例えば宗教、インドネシアやマレーシアのようにイスラム教が多くを占める地域ではその宗教的戒律にも注意が必要です。例えば反日感情、韓国や中国ではこれまでの歴史的経緯を尊重しませんと予想しない事態が生じかねません。
こうしたカントリーリスクの中で、中長期的に深刻になりそうなのがエネルギー問題です。アジアにはエネルギー資源に恵まれている国が数多くあります。インドネシアやブルネイの天然ガス、中国やインドネシアの石炭、ミャンマーやマレーシアの石油など、その輸出が経済を支えてきた過去もありました。
しかし、今、エネルギーを自給できる国はアジアではさほどありません。
日本や韓国、台湾のようにもともとエネルギー資源に恵まれていない国は当然としても、中国でも石炭を除いては天然ガスも石油も輸入に頼る状況です。石油ではとうとうアメリカや日本を抜いて、世界一の石油輸入大国になってしまいました。
資源大国のインドネシアにしても、天然ガスや石炭の輸出では追いつかないほどの石油を輸入するようになっています。マレーシアも同様で、天然ガスの輸出では石油の輸入をカバーできなくなりつつあります。
こうしたアジアでのエネルギーの海外依存は人口の増加に伴って、これからますます深刻な事態を迎えようとしています。かつての石油ショックが日本経済を直撃したように、中東の異変がアジア経済を左右する危険性を秘めているのです。
では、こうしたエネルギーの海外依存にどう対応してゆくのでしょうか。日本では二度にわたるオイルショックの過程で、世界有数とも言われる省エネルギー技術を進化させてきました。
具体的な数字で見ますと、“GDP電力生産性”という指標があります。GDPを上げるためにどれだけの電力エネルギーを消費するのか、という指標ですが、日本は4.49(ドル/kWh)に対して、アメリカは3.23、即ち日本の方が電力エネルギーをアメリカよりも40%近く効率的に使用していることになります。
しかし、アジアは悲惨です。韓国で2.09、中国に至っては1,32という低水準です。韓国は同じGDPを稼ぐのに日本より2倍以上の電力エネルギーを消費し、中国は3.5倍もの電力エネルギーを消費しているのです。電力エネルギーはもともと石油であり、石炭であり、天然ガスです。
これは大きなカントリーリスクにつながりますが、同時に「日本の省エネルギー技術は韓国や中国で売れる」というビジネスチャンスにもなります。
重要なポイントは、カントリーリスクの高い国にはカントリーリスクを減らす技術やサービスが受け入れられる、ということです。
皆さんもこうした感覚でカントリーリスクを考えていただけると(政治体制や反日感情というビジネス以外の分野は別ですが)、そこに中小企業や小規模事業者のビジネスチャンスが見えてくるのではないでしょうか。
例えば、この頃テレビを賑わせているPM2.5(粒子状物質)、北京やハルビンのあの汚れた大気、あれを見て、単にカントリーリスクと受け止めるのではなく、そこに大きなビジネスチャンスが拡がっていると感じていただきたいのです。第2話でお伝えしたように、「困っている人を見つける」ことがビジネスにつながるのですから。
B-B「アジアとの付き合い方21~韓国②~」
「アジア全体の市場に対する知見を増やす記事を」という読者の声にお応えして東南アジアをシリーズでお伝えしてきました(第162話~第173話)。そうしたところ、「東南アジアだけではなく、中小企業や小規模事業者が市場として考えるアジアの他の国々も紹介して欲しい」というご意見をいただきまして、東南アジア以外の国々をご紹介したいと思います。いずれも中小企業や小規模事業者が今後考える海外進出の相手となる可能性がありますし、また、日本とは違う環境の中での市場を想像することは、日本国内におけるビジネスチャンスを考えるヒントにもなると思うからです。韓国の経済状況について、前回はご説明をしてきました。今回は韓国と日本の関係、特になぜ反日感情が強く、同時に日本でもヘイトデモに見られるような排外的な動きが目立つのか、その辺をご説明したいと思います。これが韓国を考える際の最大のカントリーリスクになるからであり、同時に韓国を中小企業や小規模事業者の海外進出の対象として捉える際に皆さんが最低押さえておくべき知識となるからです。
さて、韓民族、私たち日本民族と極めて近い位置にある人たち、言語的には韓国語と日本語は類似点が多く、日本人がもっとも学びやすい言語と言われています。遺伝子的にも歴史的にも以前から朝鮮半島と日本列島の間では度重なる人間集団の行き来がありましたので、近縁の関係にあると言えるでしょう。ただし、韓民族はその地政学的な位置から、中国や北アジアとの関わりも強く、遺伝子構成や食生活などでその影響が濃く現われ、この辺が日本文化との差になって現われていると言えます(焼肉がその典型)。
こうして極めて近い関係にある韓国は近いが故に歴史上、何度も日本からの侵攻に悩まされてきました(朝鮮半島から日本への侵攻は元寇以外比較にならないほど少ないのです)。古くは高句麗の広開土王碑にあるように、5世紀初頭から日本は朝鮮半島に侵攻を繰り返しており、最終的に7世紀、白村江の戦いで唐・新羅連合軍に大敗するまで続きました。さらに、新羅に続く高麗王朝、その後の李朝朝鮮でも倭寇という日本人主体の侵攻は国を衰えさせたほどです。
そして、極めつけは豊臣秀吉の二度にわたる大侵攻で、朝鮮半島は戦火に焼かれ、職人や文化人をはじめとして数多くの人たちが日本へ連れてゆかれる被害にあったのです。ちなみに、日本の島津焼、唐津焼、有田焼、萩焼といった名窯はこのとき連れてきた朝鮮人陶工の手によるものです。
さらなる悲劇は、1910年の朝鮮併合です。「朝鮮の独立を守る」という大義名分で日本は清朝とも(日清戦争)帝政ロシアとも(日露戦争)戦ったのですが、その結果は李朝朝鮮の日本への併合、日本による植民地支配だったのです。この35年間にわたる日本の植民地支配は、創氏改名(日本風の姓名に強制的に変えさせました)や強制連行(日本へ労働力として連れてきました)といった悲劇とあわせて韓民族の記憶に今も鮮明に残っており、当時の植民地支配に協力した韓国の人たちの財産を政府が没収するという「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」が2005年に成立したほどです。
こうした過去の積み重ねが引き起こした反日感情は、もともと自分たちが文化を日本へ伝えてきたという自負心が強い韓民族にとっては、かなり深刻で強烈なものです。
とはいえ、日本と韓国の経済的な関わりは大変大きなものがありますし、地政学的にも日本と一番近い国であり、北朝鮮の脅威をともに受けている国際関係もありますので、こうした過去を乗り越える相互理解が待たれるところです。
こうした韓民族の感情や歴史的な経緯に十分注意していただくことが、中小企業や小規模事業者の海外進出の対象として韓国を考える際に大変重要になるでしょう。
B-B「アジアとの付き合い方⑳~韓国①~」
「アジア全体の市場に対する知見を増やす記事を」という読者の声にお応えして東南アジアをシリーズでお伝えしてきました(第162話~第173話)。そうしたところ、「東南アジアだけではなく、中小企業や小規模事業者が市場として考えるアジアの他の国々も紹介して欲しい」というご意見をいただきまして、東南アジア以外の国々をご紹介したいと思います。いずれも中小企業や小規模事業者が今後考える海外進出の相手となる可能性がありますし、また、日本とは違う環境の中での市場を想像することは、日本国内におけるビジネスチャンスを考えるヒントにもなると思うからです。今回は韓国、近くて遠い国、韓流のドラマやポップスは身近なのに、どこか隙間を感じる人も多いのではないでしょうか。
香港や台湾ではその生い立ちと言いますか、歴史と言いますか、そこからお話をはじめましたが、韓国ではそれは最後に廻したいと思います。あまりにも日本との関わりが多すぎて、何をどうお伝えしたらよいか悩むからです。
そこで、韓国、正式には大韓民国、韓民族の国です。極めて不幸なことに第二次世界大戦の終結とその後の冷戦の過程で、韓民族は二つに切り裂かれ、北は朝鮮民主主義人民共和国、通称北朝鮮として私たちを悩ませています。
この韓民族は(北では朝鮮民族と言いますが)、世界に約8,000万人、韓国に約5,000万人、北朝鮮に約2,400万人、歴史的な経緯から中国に約200万人、中央アジアのウズベキスタンに約100万人、そのほかアメリカに約150万人をはじめ、カナダ、オーストラリアなど世界各地にコリアンタウンを産むほど移住しています。
そのうち韓国については、面積は日本の4分の1と狭く、人口も日本の半分以下ということから、国内市場に限りがあるのが韓国経済の一つの特徴となっています。なにせ、インドネシア、フィリピン、ベトナム、タイと東南アジアの国々は軒並み韓国より大きな人口=市場規模を有しているのです。
GDPは約1兆2千億ドル、一人あたりGDPも約22,000ドルと、台湾と規模では3倍近く、一人あたりではほぼ同じという水準です。しかし、これだけの経済規模でありながら外貨準備高は約3,400億ドルと台湾におよびません(対外債務は外貨準備高を超えています)。また、GDPの75%以上が十大財閥に占められ、貿易への経済の依存度は96%という異常な水準に達しています(ドイツでも60%、中国は40%、日本は30%)。
韓国経済を支えた原動力は、企業の乱立(オーバーストア現象)を政府の介入で整理し、業種ごとに絞り込み、世界で競争できる規模まで巨大化させた財閥にあります。それがサムソンであり、LGです。サムソン(三星)は25兆円近い売上と、35万人を超える従業員を抱え、韓国経済の2割を占めるほど。半導体、液晶、造船、携帯電話などでは世界有数となっています。LG(ラッキー金星)はサムソンに次ぐ情報通信メーカーですが、液晶ではサムソンを抜いて世界一です。
こうした巨大財閥は、韓国の国内市場が小さいこともあり、海外市場にその活路を求め、その戦略は大きな成果を上げました。しかし、その反面、あまりにも財閥への集中が進み過ぎ、それを支える中小・中堅企業が存在せず、国内でのイノベーションが起きにくいという課題、海外市場にその多くを委ねるために世界経済の好不況をまともに受けるという課題を抱えているのです。また、財閥のガバナンスとして経営者層に富と権力が集中するので、それ以外の一般の国民との間に大きな乖離が生まれており、それが過激な労働運動に結び付く傾向もあります。
このように、国家的に選択と集中を財閥中心に進めた韓国経済は、国際競争力の向上という果実を得た反面、過度の集中や過度の海外依存が国内の矛盾や疲弊につながりかねないという問題を抱えることになったのです。今、韓国では“同伴成長”という考え方で、財閥の野放図な活動を抑え、中小企業や小規模事業者を保護しようという動きが出ていますが、これがまさに韓国経済の問題をあからさまに現わしていると言えるでしょう。かつて、財閥中心の産業集積を国の力で進めた韓国は、今回も同じように国の力で大企業と中小企業の両立を実現しようとしています。しかし、この「国の力」というところに韓国経済のカントリーリスクが存在しているとは言えないでしょうか。
B-B「アジアとの付き合い方⑲~台湾②~」
「アジア全体の市場に対する知見を増やす記事を」という読者の声にお応えして東南アジアをシリーズでお伝えしてきました(第162話~第173話)。そうしたところ、「東南アジアだけではなく、中小企業や小規模事業者が市場として考えるアジアの他の国々も紹介して欲しい」というご意見をいただきまして、東南アジア以外の国々をご紹介したいと思います。いずれも中小企業や小規模事業者が今後考える海外進出の相手となる可能性がありますし、また、日本とは違う環境の中での市場を想像することは、日本国内におけるビジネスチャンスを考えるヒントにもなると思うからです。台湾の複雑な状況は前回お伝えしましたので、今回は台湾の経済的なポジションをお話したいと思います。
台湾、それは美麗島(フォルモサ、麗しの島)と呼ばれ、古くは16世紀、ポルトガルの船が台湾へ漂着したとき、その緑あふれる美しさに思わず“Ilha Formosa(麗しき島)”と叫んだと伝えられています。そして、17世紀にはオランダが台湾を占拠しましたが、1662年、明朝滅亡の混乱の中、鄭成功(別名:和唐内、国姓爺)がオランダ勢力を追い払い、自前の政権を台湾に樹立し、中国本土の清朝と対立したのです。このとき、中国海商の鄭芝竜と日本女性田川氏との間に鄭成功が長崎の平戸で生まれた経緯から、近松門左衛門の人形浄瑠璃(のちに歌舞伎)“国性爺合戦”が作られることになりました。その後、鄭成功の子孫は清朝へ投降し、台湾は中国の一部に戻りましたが、マラリア、デング熱などの風土病もあり、辺境の地として放置され、未開の状態が続くことになったのです。
それが一変したのが日清戦争後の1895年以降で、日本が台湾を植民地化し、後藤新平が上水道を整備し、八田與一がダムと用水路を築き、さらに義務教育制度を導入するなど、精力的な植民地経営を行った結果、台湾の近代化は大きく進むことになりました。
そして、1949年の中国国民党の渡台以降、今日の繁栄を見ることとなりました。
台湾は人口が約2,300万人、面積は九州を一回り小さくしたほど、4,700億ドルを超えるGDP(香港の約2倍)と一人あたり20,000ドル(日本の半分くらい)という所得水準はアジアの中では高い位置を占めています。電化製品や半導体を中心とする輸出は堅調で、外貨準備高は世界第4位の4,000億ドル(日本の3分の1くらい)という水準ですから、韓国とは異なり通貨危機の危険性もありません。まさに、アジア経済の優等生と言ってよいでしょう。
そうした台湾を代表するのがホンハイ(鴻海精密工業)、TSMC(台湾積体電路製造)、群創光電、友達光電、UMC(聯華電子)といったEMS(Electronics Manufacturing Service)の受託生産を得意とする企業群です。
ホンハイは中国、インド、メキシコ、ブラジルなどに生産拠点を構え、80万人を超える従業員を抱える台湾随一の企業グループで、シャープの再建支援でも有名になりました。各種パーツのOEM供給、組み立て、受託生産に特化したビジネスモデルで、大量受注大量生産で規模を拡大し続けてきました。現在は、アップルからの委託でiPhoneやiPadの製造に携わっています。また、液晶パネルの群創光電(イノラックス、シャープよりも液晶では売上が大きい)も傘下にしています。
TSMCは台湾の新竹に生産拠点を構える世界最大級の半導体生産受託企業で、その売上は1兆7千億円(日本ですとシャープの7割程度)、1987年の創業からわずか30年もたたずにこの規模を実現しました。このビジネスモデルも大量受注大量生産で、半導体の莫大な開発コストに耐えるにはこれ以外の方法は採りようがないのです。この点で自社内の需要を優先する日本の半導体企業は耐えられなかったと言えるでしょう(日本の半導体企業はそのほとんどが自社の電化製品向けからはじまっています)。
こうした台湾流の受託生産による大量受注大量生産というビジネスモデルと真っ向からぶつかっているのが、この後にご紹介するサムソンやLGといった韓国の企業です。
さて、筆者はアジアを訪れる機会に恵まれていますが、何よりも台北は過ごしやすいと感じました。まず、日本語、英語、漢字が通じるのは大きいですね。漢字は中国本土が簡体字になってしまい、どこをどう略したのやら慣れるまで大変ですが、台湾は昔の儘ですので、筆談ができるのが便利です。また、同じ植民地体験ではあっても、韓国とは違って反日感情はほとんど気になりません。これも助かります。
政治的な不安定さはあるものの、台湾はその経済力、さまざまなインフラ、そして反日感情の薄さからして、日本の中小企業や小規模事業者がパートナーとして考えるには格好の相手ではないでしょうか。
そして、自社内の需要を前提とする日本の半導体企業と、お客さまを第一に大量受注大量生産を貫いてきた台湾のEMS企業の違いを見るとき、内内意識を拭い去り、市場やお客さまと向き合うことの重要さを感じていただければ、必ずそれは中小企業や小規模事業者でも生かされる教訓になると思うのです。
B-B「アジアとの付き合い方⑱~台湾①~」
「アジア全体の市場に対する知見を増やす記事を」という読者の声にお応えして東南アジアをシリーズでお伝えしてきました(第162話~第173話)。そうしたところ、「東南アジアだけではなく、中小企業や小規模事業者が市場として考えるアジアの他の国々も紹介して欲しい」というご意見をいただきまして、東南アジア以外の国々をご紹介したいと思います。いずれも中小企業や小規模事業者が今後考える海外進出の相手となる可能性がありますし、また、日本とは違う環境の中での市場を想像することは、日本国内におけるビジネスチャンスを考えるヒントにもなると思うからです。二番目は台湾です。これはややこしいです。「台湾は国であって国ではない」、これが現状です。1949年に中国の国共内戦が終わり、中国本土は中国共産党により中華人民共和国として新しくスタートしました。一方、敗けた中国国民党は台湾へ逃げ込み、中華民国として存続したのです。そして、国連をはじめとする世界のほとんどの国々は中華人民共和国を中国として認知することになり、彼らが主張する「一つの中国」という原則を受け入れ、中華民国との国交を断絶したのです(日本も1972年の日中国交回復からは同じで、台湾の大使館は日本にはありません、代わりに港区白金台に台北駐日経済文化代表処があります)。ですので、中華人民共和国からすると台湾は中国の一部であり、現在は不法に中国国民党が占拠している、ということになります。一方、台湾では自分たちは中華民国という一つの国であり、その存在を国際的に認めて欲しい、ということになります。
しかし、現実的には中国本土と台湾は経済的には極めて密接な関係にあり、中国本土にたくさんの台湾企業が進出し、沿海部を中心として工場や営業拠点を構えています。今や中国経済における台湾企業の存在は無視できないほどに大きくなっています。台湾からしても、貿易相手としても生産拠点としても販売市場としても中国本土の占める割合はかなりのレベルにまで至っています。
従って、政治的には中国本土と台湾は緊張関係にありますが、経済的には分かちがたい相互依存関係にあると言えます。
こうしたことから、台湾では台湾独立を目指す人たち(後述する民主進歩党)、現状維持を望む人たち(中国国民党)、香港やマカオのように「一国二制度」での中国への復帰を目指す人たちなどが入り乱れ、選挙のたびに争う状況となっているのです。
それに加えて難しいのが、1895年から1945年まで日本が植民地として支配していたこと、これには賛否両論があり、日本統治時代に交通、衛生、教育などのインフラが整えられたことが戦後の台湾の成長に貢献したという意見もありますし、やはり植民地として虐げられていたという意見もあるところです(一般的には親日的な人たちが多いと筆者は感じています)。そして、もともとの原住民であるオーストロネシア系の人たち(主に山岳地域に居住し人口の約2%)、清朝初期以降に中国本土から移住してきた本省人(福建省出身が多く人口の約85%)、国共内戦で敗けて1949年以降に中国本土から移住してきた外省人(戦後台湾を支配してきた中国国民党関係者で人口の約13%)という三重構造になっていることです。ですので、例えば台北から羽田までの飛行機に乗りますと、日本語を話す客室乗務員、英語を話す客室乗務員、北京語(外省人が使う)を話す客室乗務員、福建語(本省人が使う)を話す客室乗務員と、四種類のサービスが用意されているほどです。
こうした台湾の複雑な状況は政治にも色濃く現われており、四年に一度の総統選挙(台湾のトップを決める)では、本省人と台湾独立派が押す民主進歩党の候補と、外省人と現状維持派や中国復帰派が押す中国国民党の候補が激しく争うことになります。現在は中国国民党の馬英九が総統ですが、その前は民主進歩党の陳水扁が総統という具合です。
B-B「アジアとの付き合い方⑰~香港~」
「アジア全体の市場に対する知見を増やす記事を」という読者の声にお応えして東南アジアをシリーズでお伝えしてきました(第162話~第173話)。そうしたところ、「東南アジアだけではなく、中小企業や小規模事業者が市場として考えるアジアの他の国々も紹介して欲しい」というご意見をいただきまして、東南アジア以外の国々をご紹介したいと思います。いずれも中小企業や小規模事業者が今後考える海外進出の相手となる可能性がありますし、また、日本とは違う環境の中での市場を想像することは、日本国内におけるビジネスチャンスを考えるヒントにもなると思うからです。その最初は香港です。「香港と中国は違う国なんですか」とよく質問されます。そうですね、中国については、「中国を知る」というシリーズで断片的ではありますがお伝えしてきました。でも、中国と香港、中国とマカオ、中国と台湾の関係は、となると皆さんもよく整理されていないと思います。
香港、正確には中華人民共和国香港特別行政区と言いまして、間違いなく中国(中華人民共和国)の一部です。でも、「一国二制度」と言いまして、中国本土とは違うルールで成り立っている特殊な地域です。これはポルトガルの植民地だったマカオも同じで、中華人民共和国マカオ特別行政区となります。
それは、香港は1842年、あの悪名高いアヘン戦争の結果、イギリスに割譲と99年間租借された地域で、1997年に中国へ返還されるまではイギリスの植民地だった歴史があります。ですので、当時の香港はイギリス=資本主義のルールで統治され、中国本土が中国共産党に社会主義のルールで統治されていたのとはまったく別の地域だったのです。
当時(1997年)、香港が中国へ返還されるとき、中国本土と同じような政治経済体制になるのを嫌った多くの香港人や香港資本がカナダをはじめとする世界各地へ散らばっていたことを筆者は今でも鮮明に覚えています。「これまでのように自由な商売ができなくなる」という怖れを抱いたわけです。
そこで、中国共産党も中国本土と同じルールにしたのでは大混乱になって、せっかくの香港の繁栄が駄目になってしまうという危機感から、「一国二制度」というルールを作りました。返還後50年間は香港の特殊な地位を認め、国家としては中国に属するが、高度な自治権と、これまで同様の法律・行政・経済のルールを認める、という内容です。ただし、高度な自治権とは言っても、トップである行政長官は中国本土が認めることが前提ですので、かなり強く中国共産党の意向が反映されることになり、この辺の自治権を巡って、民主化を求める人たちと、中国本土とのつながりを重視する人たちのつば競り合いが頻発することになります。
経済的には、人口は700万人を超え、面積は東京都の約半分、狭いところに経済活動が活発なので土地の値段が非常に高く、オフィスの賃料は157ドルと東京の5倍近い高額、GDPは約2,500億ドル(シンガポールとほぼ同じ、日本の約20分の1)、一人あたりのGDPは約36,000ドル(日本の80%程度、英独仏とほぼ同じ)、失業率はわずか3%程度、貿易相手国は当然ながら中国本土が5割以上を占め、日本やアメリカ、シンガポールなどが続きます。
世界屈指のビジネス拠点で、2年連続で「世界で最も競争力の高い国・地域」に選ばれ、ビジネス・人的資本・文化・政治などを総合評価した世界都市ランキングにおいて世界第5位の都市と評価されています。また、ニューヨークやロンドンと並んで世界トップレベルの金融センターとなっています。富裕人口も非常に多く、資産100万ドル以上を持つ富裕世帯は約20万世帯を超え、これは全体のおよそ1割にあたり、世界有数の密度となっています。17年連続で「世界で最も自由な経済体制」に選出されているように、経済は規制が少なく低税率な自由経済が特徴です。
このように、中国の一部ではありながら自由な経済体制を持ち、金融センターであると同時に、今や世界の工場とも言えるシンセンやトンガンと言った広東省南部と地続きである利点を持つ香港は、今も昔も日本企業が海外進出を図る際の拠点となってきました。
中小企業や小規模事業者が海外を考えるとき、香港は有力な選択肢の一つになるでしょう。香港から中国本土を、香港から東南アジアを、何よりも香港はアジア各地に拡がる中国系(華僑)ネットワークの拠点なのですから。
ところで、マカオは特にご紹介しませんが(人口約60万、GDP約290億ドルと経済規模が小さいので)、カジノと観光で潤っている広東省南部の小さな地域です。
B-A「東南アジアに見る市場開拓⑪~システムを売る~」
東南アジア(あるいはアジア)への進出をさまざまな観点から進めている日本企業の事例を取り上げることで、より鮮明に中小企業や小規模事業者の新天地になりうる東南アジアを実感していただき、同時に新しい市場を開拓する際に重要なエッセンスを汲み取っていただきたい、そういう思いではじめたシリーズもこれで最後です。今回も、多くの情報を日本経済新聞の記事からいただいております。最後の事例は、単品を売るのではなくシステムを売る、というお話です。これまで日本の企業はトータルなシステムを売るのが苦手と言われてきました。それはトータルなシステムとなると、たくさんの企業とアライアンスを組み、それをマネージメントする能力が求められるからで、例えば水ビジネスなどでは、個別の濾過技術とか給排水技術などでは日本の企業が優秀なのに、全体として水システムを売る、という話になりますとフランスやイギリスの企業に後れを取ることがよくあったのです。
今回は鉄道です。鉄道と言えば、車両を売るとか、線路を敷設するとか、運行システムを提供するとか、そういった個別のビジネスが大半を占めていたのですが、今回は違います。
アジア向けに鉄道システム全体を売ろうというビジネスが今大きな注目を集めているのです。
具体的には、タイの都市鉄道、バンコク市内に23㎞の新路線を整備する計画で採用されたのがJR東日本と丸紅と東芝の連合体です。車両、架線、信号システム、駅設備、車両基地など、それもメンテナンスまで含めたワンパッケージで提供することになります。
何よりも強みと評価されたのが、日本の鉄道が遅れず、事故らず、定時安全運航を続けている実績でした。これは世界でも珍しい品質なのです。
そして、これをタイでも実現するために、20人を超えるスタッフを現地に駐在させ、鉄道要員を育成し、定時安全運航に必要なノウハウを教え込むほどの力の入れようです。
かつて、「物を売れば終わり」と言われた日本流ビジネスとは大違い、ここが単品を売るのと、トータルなシステムを売るのとの大きな違いです。その違いにこだわるだけ、日本の海外進出も本気のレベルになったということでしょう。
さらに、ここでもアライアンスは如何なく発揮され、車両や鉄道本体に関わるところはJR東日本、送配電網などの機器系は東芝、全体のプロジェクトマネージメントは商社である丸紅と、「お互いに得意な分野を活かすアライアンス」が貫かれています。
こうしたシステムビジネスは交通インフラ事業として日本企業が力を入れており(その意味ではGEともぶつかるのですが)、タイ以外でもマレーシアとシンガポールを結ぶ高速鉄道網をJR東日本が、台湾新幹線向けの制御システムはJR東海が、ハノイの地下鉄には東京メトロが、ホーチミンの都市鉄道には日立製作所が、インドネシアの都市鉄道には三菱重工業と住友商事が、マニラの都市鉄道には丸紅がそれぞれ売り込もうと必死です。
いかがでしょうか、海外進出の段階的な発展を考えますと、ワンストップ(一つの窓口でさまざまなサービスを受けられる)かつフルターンキー(完成してすぐに使いはじめられる状態で引き渡す)で、クライアントが使いやすいように提供するシステム型のビジネスが重要になることがおわかりいただけたでしょうか。
本来、ビジネスは川下で稼ぐよりも、川上で川の流れそのものを抑える方が分がよい、と言われますが、まさにそのとおりなのです。
中小企業や小規模事業者もアライアンスを組む価値があれば、こうしたシステムビジネスに参画することも夢ではありません。そのためには、自社の強みをとことん伸ばすという経営の戦略性が必要とされます。そういう観点で中小企業や小規模事業者の今後を考えていただきたいと思います。
B-A「東南アジアに見る市場開拓⑩~アルコールの市場~」
東南アジア(あるいはアジア)への進出をさまざまな観点から進めている日本企業の事例を取り上げることで、より鮮明に中小企業や小規模事業者の新天地になりうる東南アジアを実感していただき、同時に新しい市場を開拓する際に重要なエッセンスを汲み取っていただきたい、そういう思いではじめたシリーズの十回目です。これも、多くの情報を日本経済新聞の記事からいただいております。前回はコーヒーとパンでしたが、今回はアルコールです。
アジアにおけるアルコール市場の規模は、日本が約11兆円、中国が約19兆円、インドが約3.8兆円、韓国が約2.5兆円、タイが約1.2兆円、フィリピンが約9,000億円、ベトナムが約6,500億円、マレーシアとシンガポールが約3,000億円、インドネシアが約2,000億円という状況です。これを年間一人あたりで見ますと、日本が約87,000円、中国が約14,000円、インドが約3,000円、韓国が約50,000円、タイが約17,000円、フィリピンが約9,000円、ベトナムが約7,000円、マレーシアが約10,000円、シンガポールが約60,000円、インドネシアが約800円です。インドネシアが非常に低いのはイスラム教の信徒が大半を占め、厳格なイスラム教の教えではアルコールは好まれないからです。
アジア全体では45兆円にも達するアルコール市場は、まさに巨大な規模と言えるでしょう。しかも、まだまだ一人あたりの消費額は所得に比例して伸びるのですから。
さて、そうしたアジアのアルコール市場、これまではその多くが地酒で占められていましたが、ビールを中心として日本企業も懸命に市場へ挑戦しています。
サントリーでは、日本食レストランを中心としてプレミアムモルツのたる生を展開していますが、品質保持のために定温コンテナで日本から輸出し、機械やグラスの洗浄や温度管理を教えるセミナーを店舗向けに開催するほどのこだわりです。これだけのこだわりですと、やはり価格帯も一杯1,000円程度の高額になりますので、対象国もシンガポールや韓国、香港といったところです。
サッポロはベトナムにいち早く自社工場を整えましたので、ここを拠点にタイ、ベトナム、シンガポール、マレーシアでたる生を供給しています。
アサヒは韓国で黒ビールを提供し、キリンはドバイで一番搾りを凍らせるフローズンを売る、そんな具合でビール各社はアジア市場の開拓に必死です。
この戦略を見てみますと、基本はどうも生ビールのようで、これは缶ビールや瓶ビールの領域では既に市場をかなり抑えている欧米系のメーカー、例えばハイネケンとかバドワイザーとかが強いので、日本は欧米系の苦手な生ビールを攻めるという図式のようです。
そして、高級ブランドを守ろうとするサントリーやキリン、アサヒと、現地化を進めようとするサッポロの違いも目立ちます。
いずれにせよ、中国市場がそうであるように、ビールもいずれは現地生産の時代を迎えるでしょうから、それまでの間に自社のブランドをどう浸透させるか、その知恵比べになっているようです。
今回は必ずしも「現地の嗜好や所得にあわせる」工夫とは言えませんが、もう一つの重要な要素であるブランドをどう浸透させるか、資生堂は新ブランドまで踏み込みましたが、ビール業界はそこまではいかないものの、現在のブランドの高級感を生ビールで伝えようと必死のようです。
このように、市場の規模や成熟度、自社の持つブランドの特性などから、海外進出にもさまざまな形態があることをご理解いただければ、中小企業や小規模事業者の海外進出も選択肢が拡がるのではないでしょうか。
B-A「東南アジアに見る市場開拓⑨~食の市場~」
東南アジア(あるいはアジア)への進出をさまざまな観点から進めている日本企業の事例を取り上げることで、より鮮明に中小企業や小規模事業者の新天地になりうる東南アジアを実感していただき、同時に新しい市場を開拓する際に重要なエッセンスを汲み取っていただきたい、そういう思いではじめたシリーズの九回目です。多くの情報を日本経済新聞の記事からいただいております。東南アジアと言えば、人口6億人、これだけの人口が食べる量は莫大です。そこに新しい市場を見つける日本企業もまた、コンビニ業界と同じように多いのです。
今回はそうしたインドネシアの食の市場を開拓している商社の動きを見てみましょう。
まずは、ミルクコーヒーです。コーヒーはお茶や炭酸飲料と並んで「飲む」嗜好品としては巨大な位置を占めています。
インドネシアでは“コピ”と呼ぶ、屋台のコーヒーが定番、一杯3,000ルピア(約30円)で楽しめる庶民の飲み物です。ここに商機を見つけたのが以前第32話でご紹介した豊田通商です。
豊田通商の新商品は“コピコ”と名付けたペットボトルです。常温でも冷たくしても美味しいミルクコーヒー、値段は5,500ルピア(約50円)と高目ですが、コーヒーの苦さとミルクの滑らかさを組み合わせ、持ち運びができる便利さをセールスポイントに、月に500万本も売れるヒットになったのです。しかも、日本のボトリング受託の大手企業と共同進出してリスクを軽減し、販売のパートナーは地元から選び、商品開発はこの二社に任せて、自分は材料や設備の調達、工場建設や法務などの支援に廻ったのです。
ビジネスアライアンスの基本とも言える、得意なところを受け持ち、苦手なところはパートナーに任せるスタイルを貫いた訳です。お見事ですね。
次は“パン”です。それも日本で売れている商品をそのまま持ち込むなんていう無謀なことはしません。
パンケース付の自転車をジャカルタの街並みを走り回る、そんなビジネスモデルで“サリロティ”という菓子パンを10,000ルピア(約100円)で売り歩くのは、敷島パンと双日の連合軍です。人気の秘密はふっくらもちもちの食感、これを産み出すために好適な小麦をオーストラリアから調達するのは商社である双日、それを菓子パンに製品化するのはパンメーカーの敷島パン、この組み合わせで大成功を遂げたのです。
これもビジネスアライアンスの基本で、やはり得意なところを受け持ち、苦手なところはパートナーに任せるスタイル、そこにインドネシアの低廉な労働力を活かした自転車販売という一工夫が噛み合わさり、今ではスーパーやコンビニのパン売り場でも90%ものシェアを握る新国民食に育ちつつあります。
いかがでしょうか、同じような目の付け所は中小企業や小規模事業者でも可能です。そして、前にもお話した「現地の嗜好や所得にあわせる」工夫と、「お互いに得意な分野を活かすアライアンス」という当たり前の手法があれば、中小企業や小規模事業者でも海外市場を開拓することは十分可能だと思います。
そして、何よりも新しい市場へ挑戦する気持ち、これを失わないことが重要ではないでしょうか。
D「グローバル人材」
中小企業や小規模事業者における「人材」の重要性は今さらご説明するまでもないでしょう。その「人材」、これは皆さんが目指す一つの目標でもあるのですが、今の社会でどういった人材が求められているのか、これを国際化という視点から見ていきたいと思います。そこには、皆さんが中小企業や小規模事業者で活躍する際のヒントがあると考えるからです。まずは、日本経済新聞のショッキングなニュースから、「国家公務員試験(総合職)」に2015年からTOEFLを導入」、いかがでしょうか。
国家公務員上級試験、昔の高等文官試験にとうとうTOEFLです。Test of English as a Foreign Language、非英語圏の出身者のみを対象としており、英語圏の高等教育機関が入学希望者の外国語としての英語力を判定する際に用いるテストで、リーディング、リスニング、スピーキング、ライティングの4部から構成されており、試験時間は約4時間。
1部30点で合計120点が満点です。凄い時代になったものです。
これを受けて、文部科学省では中学3年生、高校3年生向けの英語能力テストの開発でTOEFLとの連携を明確にしました。ということは、今検討されているセンター試験廃止後の新テストでもTOEFLの導入がありうるのでしょう。
こうなりますと、上から下まで、官から民まで、英語=TOEFLという流れになることは避けられず、皆さんの人物評価にもTOEFL基準の英語力が加わることは目と鼻の先と言えます。
また、国公立私立の133大学の学長や理事長を対象とした日本経済新聞アンケートでは、10年後に自分の大学から海外に留学するケースが全体の3割以上になると半数近くが予想しており、同じように10年後に自分の大学における海外からの留学生が全体の3割以上になると3分の1近くが予想している結果となりました。
要するに、日本の大学の国際化は加速度的に進む、というのが現場の学長や理事長の予想なのです。こうなりますと、企業側の国際的な人材の確保という流れとあいまって、人物評価にグローバルという評価軸が加わるのは間違いないことでしょう。
さらに、教育再生実行会議ではセンター試験廃止後の新テストの創設とあわせ、知識偏重の入試から脱却し、意欲や適性を重視することで、イノベーションを起こせる若者像を目指すよう提言しています。
この三つの情報に流れているのは、これからの社会で求められるのはグローバルに活躍できる人材だ、というメッセージでしょう。
しかし、グローバル人材は語学力(英語力)だけでしょうか。筆者は決してそうではないと思います。
もちろん、語学力で勝負する人たちはたくさんいるでしょうし、そこではTOEFLのハイスコア、あるいはトリリンガルな、マルチリンガルな語学力(英語+α+β)を目指すことになります。
でも語学力以外の能力や知見、素養もグローバル人材には求められます。既に文部科学省ではスーパーグローバルハイスクール構想の中で、語学力と並んで、国際的素養と問題解決力を目標としてあげています。
海外での人材コンサルティングでは、「実務や管理能力よりも、行動力や旺盛なチャレンジ精神が求められる」とも、「上の指示で動くだけではなく、現地の流れを読みながら自分で考え、自分で切り開く力が必要」とも言っています。
いかがでしょうか、世の中が「グローバル人材」へと流れてゆく状況、その中でTOEFLに代表される「国際化を評価軸とする人物評価」がはじまろうとしている現状、そして何よりも求められる「挑戦する精神」、こういった中から皆さんが中小企業や小規模事業者で活躍する際のイメージを見出していただきたいと思います。
C「人を活かす会社」
これから社会へ出てゆく皆さん、特に中小企業や小規模事業者での活躍を心に誓う皆さんには、既に第1話で「極めて重要なことが、どの企業を選ぶのか、あるいはどの企業に選ばれるのか、です。」「その企業の価値観につながるような情報を探してみてはいかがでしょうか。なんと言っても、かなりの人生をともに過ごす相手です。」とお伝えしました。今回は、日本の有力企業436社を対象として、日本経済新聞が行った「人を活かす会社」調査の結果をご紹介したいと思います。雇用・キャリア、ダイバーシティ経営、育児・介護、職場環境・コミュニケーションという四つの評価軸で比較分析し、どういった企業が多様な人材を積極的に受け入れ、その能力を活かしているのか、それをランキングしてみようという面白い試みです。皆さんが企業を選び、選ばれる際に参考になると思います。
ランキング上位は次のとおりです。
①富士フィルムホールディングス
②SCSK(住商情報システム+CSK)
③日立製作所
④パナソニック
⑤イオン
⑥パソナグループ
⑦トッパン・フォームズ(凸版印刷の連結子会社で電子帳票類を主力製品とする)
⑧サントリーホールディングス
⑨ネスレ日本(世界最大の食品メーカーNestlé の日本法人)
⑩日本興亜損害保険
⑪損害保険ジャパン
⑫ソニー
⑬リコー
⑭大日本印刷
⑮日産自動車
⑯TOTO(衛生陶器・住宅設備機器を製造するメーカー)
⑰第一生命保険
⑱富士通
⑲凸版印刷
⑳花王
いかがでしょうか、なるほどと思える会社もあるでしょうし、どうしてと思う会社もあるかもしれません。そこで選ばれた背景を個別に探ってみたいと思います。
まずは第1位の富士フィルムですが、ここは育児求職が最長2年(3歳児まで)、出産祝い金もあり、介護休職も2年間、キャリアアップのための学資も100万円まで支給と、育児・介護、雇用・キャリアアップに力を入れています。
第2位のSCSKでは、働きやすい職場環境が売り、残業の半減、有給休暇の100%取得など、職場環境・コミュニケーションで高得点です。
第3位の日立製作所では、外国人や女性の採用、登用を積極的に進めています。女性管理職を1,000名と倍以上に増やし、女性役員も視野に入れています。取締役や理事(社内役員)では外国人の登用が目立ち、採用でも1割は外国人という状態です。
第6位のパナソニックでは、出産後の職場復帰を支援、第12位のソニーでは経営トップと若手社員との交流が盛ん、といった具合です。
いかがでしょうか、皆さんも就職先を考えるとき、雇用・キャリア、ダイバーシティ経営、育児・介護、職場環境・コミュニケーションという四つの評価軸で比較分析してみるのも有効ではないでしょうか。
B-A「東南アジアに見る市場開拓⑧~ファミリーマート~」
東南アジア(あるいはアジア)への進出をさまざまな観点から進めている日本企業の事例を取り上げることで、より鮮明に中小企業や小規模事業者の新天地になりうる東南アジアを実感していただき、同時に新しい市場を開拓する際に重要なエッセンスを汲み取っていただきたい、そういう思いではじめたシリーズの八回目です。多くの情報を日本経済新聞の記事からいただいております。前回はタイのサハ・グループをご紹介しました。ローソンと組んで、先行するセブンイレブンを追いかけようとしているところです。
今回は、同じコンビニ業界第3位のファミリーマートの海外進出戦略を見てゆきたいと思います。
日本におけるコンビニ業界の勢力図は、年商6兆円の市場でセブンイレブンとローソンがそれぞれ3分の1近くを占め、ついでファミリーマートが25%という三強体制となっています。しかも、この寡占状況は年々強まっており、上位と下位との店舗あたり売上額にも差がついていますから、三強以外が生き残ることは困難になりつつあり、収益性ではセブンイレブン>ローソン>ファミリーマート>三強以外という構図も固定化しています。従って、ファミリーマート以下のコンビニは日本では行き詰まり状態にあると言えるでしょう。
このため、コンビニ業界では海外進出が激しさを増し、特に下位グループでは存亡をかけたチャレンジとなっています(セブンイレブンはもともとの本拠地であるアメリカを除いて約9,000店舗、ローソンは約500店舗であるのに対してファミリーマートは約13,000店舗が海外)。
今回ご紹介するのは、そのファミリーマートのお話です。
西友資本ではじまったこのコンビニも今は伊藤忠商事の傘下に入っています。日本では約9,000店舗の第3位でしかありませんが、早くから海外に進出していたこともあり海外では約13,000店舗を主にアジアへ展開しています。
そのファミリーマートが、いよいよプライベートブランド(PB)を本格的に展開することになりました。世界中のすべてのファミリーマートでPBを売ることになりますが、日本の本社ではブランド管理や対外交渉を担うだけで、商品開発はそれぞれの現地に委ねるという、サハ・グループが語るとおりに、「現地の嗜好や所得にあわせた商品開発」でPBを構築しようということです。
第1号として、台湾、ここには約3,000店舗を展開していますが、ここでジュース、缶詰、カップ麺、洗剤などを次々と立ち上げる予定です。生産は現地企業へ委託、商品開発でも現地企業との提携を進めるとのこと。
そして、第2号として、タイ、ここでは約100アイテムのPBを開発し、タイで試験的に投入して市場の反応を探り、高品質の生産機能を活かしてASEANへの輸出も視野に入れているようです。
いかがでしょうか、国内ではシェアや収益を飛躍的に改善できる見通しが無い、という追い込まれた状況にある業界第3位の企業が、生き残りと成長をかけて海外で挑戦する、ここに中小企業や小規模事業者が海外進出を進める上での心構えがあり、そして「現地を知る」ことに力点を置くことの重要さが読み取れるのではないでしょうか。
B-A「東南アジアに見る市場開拓⑦~タイのサハ・グループ~」
東南アジア(あるいはアジア)への進出をさまざまな観点から進めている日本企業の事例を取り上げることで、より鮮明に中小企業や小規模事業者の新天地になりうる東南アジアを実感していただき、同時に新しい市場を開拓する際に重要なエッセンスを汲み取っていただきたい、そういう思いではじめたシリーズの七回目です。海外進出をする際に、多用される方法が現地の企業と提携することです。提携の方法には合弁(互いに資本を出し合って会社を作る)とか技術供与とか生産や販売の委託とかさまざまにありますが、要するに相手国の企業と手を結ぶということです。
タイは東南アジア有数の市場や生産機能を持ち、日本企業もかなり前から進出している重要な相手国ですが、そのタイには日本企業との提携で成長してきたサハ・グループがあります。
サハ・グループは中国系のチョクワタナー家が1942年に起業し、日本製品の輸入を軸に成長を続け、現在は傘下に300あまりの企業を連ね、食品、飲料品、化粧品、衣類、トイレタリー(生活日用品)、家電販売、物流、不動産などを手広く手がけ、従業員は10万人を超える巨大企業グループです。
提携している日本企業もライオン、日清食品、ワコール、ミズノ、キューピー、大王製紙、ローソンなど80社にのぼります。まさに、日本企業との二人三脚で現在の繁栄を築いてきたと言えます。
そのサハ・グループの経営者ブンチャイさんが日経フォーラム世界経営者会議に参加するため日本を訪れ、次のようなメッセージを送っていますので、ご紹介しましょう。この中には中小企業や小規模事業者が海外に進出する際のヒントが数多く含まれているからです(このフォーラムにはGEのジェフリー・イメルトも参加していました)。
① 日本企業が海外に(東南アジアに)進出する際は、それぞれの国や地域における消費者の行動パターンや嗜好を理解することが重要でしょう。品質さえよければ売れる、という以前の成功パターンを捨てないといけません。市場で受け入れられる商品というだけではなく、消費者の好奇心をそそる、そうした新しい要素を加えることも必要です。そのためには、現地の企業とよい提携関係を築くことも欠かせません。
② ASEANでの関税自由化が2015年に実現すると、タイの生産拠点としての役割は今以上に大きくなるでしょう。既にASEANでは“メイド・イン・タイ”というだけで競合する商品よりも1、2割高額でも売れてゆきます。この品質面での優位さを活かして、ASEANへ進出したい企業はタイに拠点を置くことをお勧めします。タイは地理的にもASEANの中心にあり、インフラも周辺と比べて整備され、いわゆるハブ機能(さまざまな物流が集まる場所)を発揮しています。
③ 今回、サハ・グループではローソンと提携し、ローソン108を展開して、先行するセブンイレブンを追撃しますが、「時間の制約」が消費におけるキーワードとなりつつあり、消費者の利便性を高めることが勝負になります。地域特性や所得層などを分析して、店舗の形態を変えたいと考えています。日本には存在しないような店舗をタイで作ることもありえるでしょう。とかく成功体験の多い日本の企業ほど、成功したビジネスモデルをそのまま海外で展開しようとします。何か新しい手法を導入しようと提案しても、必ず日本の本社へ問い合わせ、本社がNoであれば駄目、こういう事例が多すぎます。
いかがでしょうか、実際に日本企業の海外進出のパートナーを長く勤めてきた方の、地に足をついたメッセージではないでしょうか。「現地を知る」ことの重要さには、中小企業や小規模事業者の海外進出のエッセンスがあると言えるでしょう。
B-A「東南アジアに見る市場開拓⑥~化粧品~」
東南アジア(あるいはアジア)への進出をさまざまな観点から進めている日本企業の事例を取り上げることで、より鮮明に中小企業や小規模事業者の新天地になりうる東南アジアを実感していただき、同時に新しい市場を開拓する際に重要なエッセンスを汲み取っていただきたい、そういう思いではじめたシリーズの六回目です。なお、今回は10月30日付の日本経済新聞の記事から多くの情報をいただいております。自動車、バイク、高齢化と来ましたが、今回は化粧品です。化粧品と言いますと男性にはあまりピンとこないかもしれませんが、女性にとっては極めて大きな問題で、世界の化粧品市場は1,500億ドル(約15兆円)という規模だそうですので、これは大変な額です(日本は1兆円強、ユーロモニター・インターナショナルの調査による)。
東南アジアにも当然のことですが3億人を超える女性が存在しますので、この市場を抑えることはどの化粧品メーカーにとっても課題となっています。
しかし、これまで日本の化粧品メーカーはいわゆる高級品志向で、「百貨店で売る」というのが一般的な販売戦略でしたし、それでかなりの利益も生まれていました。しかし、東南アジアで急拡大しているのは中間層、この中間層をどう市場化するか、ここに焦点が移りつつあるようです。
皆さんもご存じの資生堂、日本1位(シェア38.5%)、世界6位の化粧品メーカーです。さて、その資生堂が資生堂インドネシアをまもなく設立します。これまでインドネシアでは資生堂の高級ブランドをジャカルタの高級百貨店で輸入販売する形態でしたが、資生堂では新しくアジアの中間層、20代から30代の女性をターゲットに新しいブランド“Za”を立ち上げました。
資生堂のキャッチコピーを紹介しますと、「Za(ジーエー)は、常に周りが憧れるような、いきいきとして自信にあふれ、洗練された美しさを目指す女性を応援するコスメティックブランドです。Zaは高品質ながら手にとりやすい価格を実現。使用ステップもシンプルでテクニックフリーです。瞬時にいきいきとした、スマートな表情になれるだけでなく、ライフスタイルをも美しく輝かせます。世界の中で最も高い成長性と多様性を加速させているアジアの主要都市で、日々輝き、活躍している女性たちの美しさに着目しています。ブランド名Zaは、アルファベットの最初と最後の文字(英語「a-to-z」は「すべて」の意)。Zaすべてのアイテムはシンプルなのに巧みに、美しさの可能性を最大限引き出します。現在、中国(香港を含む)、台湾、タイ、ベトナム、シンガポール、マレーシア、インドネシア、ニュージーランドで展開中です。」とのこと(http://www.za-cosmetics.jp/)。
この“Za”を人口2億5千万人の巨大市場インドネシアで売ろう、ということです。
そこで大きな問題(カントリーリスク)になるのが、イスラム教です。イスラム教では戒律に定めるものしか使えないことになっています。そこで、戒律に定めるものだと宗教的に認めるハラルという制度があり、ハラル認証を受けることが市場で受け入れられる前提となります。かつて、味の素がハラル認証を受けずに豚の酵素を触媒として利用していた事件が起こり、インドネシアで関係者が逮捕される事態に陥ったほどです。
今回の“Za”では、ベトナムの資生堂の工場がハラル認証を受けましたので、無事にインドネシアへ輸出することができるようです。
こうして資生堂は今でも売上の45%を占める海外市場をさらに拡大し、ロレアルをはじめとする世界のビッグファイブに見劣りする海外戦略を立て直す決意と思われます。
いかがでしょうか、化粧品という限られた市場の中でも海外進出、特に東南アジアの重要さは増しており、資生堂のような優良企業(あまり冒険をしないという意味でも)でさえ、新しいブランドを立ち上げ、新しく現地法人を設立し、新しい市場へ挑戦するのです。
こうしたアグレッシブなチャレンジにこそ、中小企業や小規模事業者が新しい市場を開拓する際の重要なエッセンスが含まれていることをご認識いただきたいと思います。
B-A「東南アジアに見る市場開拓⑤~高齢化~」
東南アジア(あるいはアジア)への進出をさまざまな観点から進めている日本企業の事例を取り上げることで、より鮮明に中小企業や小規模事業者の新天地になりうる東南アジアを実感していただき、同時に新しい市場を開拓する際に重要なエッセンスを汲み取っていただきたい、そういう思いではじめたシリーズの五回目です。なお、これまでのコラムと同様に今回も日本経済新聞の記事から多くの情報をいただいておりますことをご紹介したいと思います。ですので、第9話でお伝えしたように、「現代日本におけるリベラル・アーツは他ならぬ日本経済新聞であるのかもしれません。」ということです。今回は、「高齢化」がキーワードです。そして、東南アジアだけではなく中国も含めて事例をお伝えいたしましょう。
アジアの高齢化は日本同様に進んでいます。日本の65歳以上の人口比は25%近くにまで達していますが、韓国や台湾では12%、タイや中国、そしてシンガポールでも9%、ベトナムやインドネシアでも5~6%という段階にまで至っています。
これだけ高齢化が進みますと、当然のことですが介護福祉という大きな問題が待ち構えることになります。
2020年にはアジア全体で65歳以上の人口は4億人を超えると予想されますので、大変な市場が現われることになります。
こうしたアジアにおける高齢化は、高齢化先進国である日本にとって大きなビジネスチャンスになるのは間違いありません。何せ、あらゆる近未来の問題は日本で既に起こっており、それに対するビジネスも日本で既に成立しているからです。
例えば、中国では毎年900万人近い老人(60歳以上)が増えています。これまで中国では儒教思想の影響もあり、老人の面倒は家族が見るのが当たり前でした。しかし、長い間の一人っ子政策はそれを許さなくなっています。四人の祖父母と二人の父母を一人の子どもが面倒みるという“421家庭”が増えているからです。
こうなりますと、老人ホームや老人向けマンション、介護サービスなどは引く手あまたの状況になります。もちろん、高額な費用負担の問題がありますので、「全国民が」という話にはなりませんが、そこは富裕層の多い中国のこと、富裕層だけでも6兆円を超える市場規模になると見込まれています。そこで、ニチイ学館、セコムなどの企業は介護用品や介護施設などで中国進出をはじめているのです。
また、タイでは東南アジアに先駆けて高齢化が進んでいることから、高齢者支援センターを全国に整備し、介護要員の確保や病院による介護施設の設置などを進める予定です。これに呼応して、千葉県浦安市に本拠を置くリエイグループでは既に介護施設の運営をはじめていますが、料金こそ現地の類似施設の2倍と高額なものの、日本流の肌理の細かいサービスは好評を得ているようです。
既に高齢化が進んでおり、それに対応するビジネスも成立し、しかも日本的な細かいところまで手の届く、お客さま本位のサービスを売りにできる日本企業にとって、アジアの高齢化が大きなビジネスチャンスになることは間違いないでしょう。
第2話で既にお伝えしたように、「困っている人をみつける」ことが、ビジネスにおける需要を意味するのですから、中小企業や小規模事業者が新しい市場を開拓する際に重要なエッセンスには、こうした先見力といち早く行動に移す経営判断の迅速化が含まれているとお考えいただきたいのです。もちろん、カントリーリスクには十分ご注意ください。
B-A「東南アジアに見る市場開拓④~ホンダとインド~」
東南アジア(あるいはアジア)への進出をさまざまな観点から進めている日本企業の事例を取り上げることで、より鮮明に中小企業や小規模事業者の新天地になりうる東南アジアを実感していただき、同時に新しい市場を開拓する際に重要なエッセンスを汲み取っていただきたい、そういう思いではじめたシリーズの四回目です。前回はスズキの話を差し上げました。インドでの成功、ミャンマーでの挑戦ですね。
今回はそのインドでホンダがどうしようとしているかをお伝えしたいと思います。ただし、四輪(自動車)ではなく二輪(バイク)です。
ホンダは既に1984年(スズキが自動車で進出したのとほぼ同じ時期)、インドのヒーローグループ(インドの中堅財閥)と合弁でヒーロー・ホンダを立ち上げ、インド市場の50%近くをシェアするまでになっていました。しかし、インドからの輸出にウェイトを置きたいヒーローグループと、インドの内需にウェイトを置きたいホンダが衝突することになり、2011年には提携を解消し、ホンダはホンダ・モーターサイクル・アンド・スクーター・インディア(HMSI)を設立して、かつての提携先とライバル関係に入ったのです。これは、一般的にはあまり勝ち目のない戦いです、なぜならば商品はほぼ同じ、ライバルの方が市場に長く、そして深く食い込んでいるからです。
そこでホンダが取った戦略が、広大な農村部を地道に開拓するという泥臭いものでした。インドの経済成長はそのほとんどが都市部に集中し、農村部は貧しいというのが通り相場でした。人口の7割は農村部に住んでいますが、そのほとんどは低所得層です。しかし、インドの経済成長とあわせて中間層が農村部でも拡大しているのは事実です。
この農村部の中間層に目をつけたのがホンダで、日本経済新聞の記事によれば、農村で小規模なビジネスを営んでいる小資産家を相手に販売代理店を着々と増やしているのです。現在は都市部を中心として約1,200店の販売代理店を、この3年間で2,500店にまで増やそうという考えです。
農村部に生活し、農村部でビジネスし、農村部をよく知っている小資産家、当然ながら上昇志向は強く、新しいチャンスにも敏感な人たちを販売代理店としてうまくネットワーク化しようというのですから、これはなかなか優れた市場開拓戦略と言えるでしょう。
こうしたホンダのインド市場開拓はライバルからシェアを奪う勢いを見せており、HMSIスタート時には10%程度であったシェアも今では30%をうかがうところまで来ているのです。
ちょうど、こうしたホンダと似たような戦略を取っているのがユニリーバ(イギリス&オランダ系の家庭用品メーカー)です。ユニリーバでは、農村部の人材を訪問販売員に育てる“シャクティ・プロジェクト”、シャクティとはヒンズー教におけるエネルギーの根源、インドの地母神の意味ですが、まさにインドの大地から湧き出すように女性の販売員が村々を訪れ、便利な生活をもたらす石鹸や洗剤、食品などを販売してゆくのです。その結果は、なんと年間に330万世帯で販売実績をあげることになったのです。
いかがでしょうか、「郷に入れば郷に従え」はよく言われる諺ですが、ホンダがインドで取っている地道な市場開拓の進め方には、中小企業や小規模事業者が新しい市場を開拓する際に重要なエッセンスが含まれていることをご認識いただきたいと思います。
B-A「東南アジアに見る市場開拓③~スズキとミャンマー~」
東南アジア(あるいはアジア)への進出をさまざまな観点から進めている日本企業の事例を取り上げることで、より鮮明に中小企業や小規模事業者の新天地になりうる東南アジアを実感していただき、同時に新しい市場を開拓する際に重要なエッセンスを汲み取っていただきたい、そういう思いではじめたシリーズの三回目です。皆さんはスズキというと何を思い出されますか。軽自動車の雄、浜松に本社を置く独立色の強い自動車メーカー、そうですね、でもインドで圧倒的なシェアを握っていることはご存知でしょうか。マルチ・スズキ・インディアは、1982年にインド政府と合弁で立ち上げられ、今やインド随一の自動車メーカーであり、スズキの日本での生産台数100万台を超える年間117万台を生産し、インド市場の39%を握るまでに成長しています。
しかし、スズキはインドで大きな成功を収めた反面、東南アジアでは大きく出遅れてきました。東南アジアにおける自動車の8割を超えるシェアは日本車が抑えていますが、スズキはわずかに8%を握るだけです。これは、企業規模からインドとの両面作戦を取る余裕が無かったことによりますが、東南アジアではベトナムで3,000台、インドネシアで15万台、タイで3万台と微々たるものです(中国では16万台、パキスタンでは8万台)。
こうした状況はスズキにとっては受け入れがたい現実で、どうにかして東南アジアの市場をこじ開けたい、特にASEANの関税自由化を控えた現状ではなおさら強く望まれることです。何せ、6億人を超える人口がモータリゼーション時代に突入するのですから。
そこでスズキは、人件費が格安で、しかもASEAN加盟国(関税の自由化のメリットを受けられる)であるミャンマーを拠点に反転攻勢に出ようとしています。
その背景には、既に1998年の段階でミャンマー政府と合弁で小型トラックを6,000台生産した歴史があり、その後の外資不足から部品の輸入ができなくなったために事業は清算されたのですが、スズキは清算後も駐在員をミャンマーへ残し、生産設備を手入れし続けて、将来の再開に備えたのです。この辺の粘り強さが、インドでも成功したスズキのコア・コンピテンシーと言えるでしょう。
そして、この間のミャンマーの自由化路線と国際的な認知とあわせ、いよいよミャンマーでの生産再開にこぎつけたのです。今はまだ以前の小型トラックの生産ラインを使っていますが、今後はティラワ(ヤンゴンの南の国際港)の経済特区に用地を確保し、関連部品メーカーと一緒に“スズキ村”を開発する計画です。
その背景には、現在のミャンマーにはまったく自動車関連産業は存在せず、すべての部品や材料は輸入するしかない反面、2015年にASEANの経済共同体が創設されれば関税はASEAN内で自由化され、必要な部品や材料はタイやベトナムなどから輸入可能で、しかもミャンマーの人件費はタイやインドネシアの4分の1以下ということがあります。これは、組立型産業である自動車産業にとっては大きなアドバンテージとなるからです。
いかがでしょうか、インドで成功したスズキはインドに安住することなく、次の巨大市場を目指して東南アジアを開拓する、しかもそのためにはミャンマーというカントリーリスクの高い国で先行投資も厭わない、こうした企業のダイナミズムこそが新しい市場を開拓する際に重要なエッセンスであり、中小企業や小規模事業者にも強く求められていることだとご認識いただきたいと思います。
B-A「東南アジアに見る市場開拓②~海外進出の拠点~」
東南アジア(あるいはアジア)への進出をさまざまな観点から進めている日本企業の事例を取り上げることで、より鮮明に中小企業や小規模事業者の新天地になりうる東南アジアを実感していただき、同時に新しい市場を開拓する際に重要なエッセンスを汲み取っていただきたい、そういう思いではじめたシリーズの二回目です。まずは、海外進出の拠点、あるいは中核として東南アジアを選んだ企業のお話です。
その前に、日本経済新聞の記事やWeb上での情報をもとに、日本とそれ以外の国々との競争条件を調べてみましょう。第一は法人税率、当然低い方が有利です。日本は38%、香港は16.5%、シンガポールは17%、タイは20%、フィリピンは30%。第二は管理職月あたり人件費、これも安い方が有利です。日本は5,487ドル、香港は4,016ドル、シンガポールは4,672ドル、タイは1,602ドル、フィリピンは1,194ドル。第三はオフィス賃料(㎡あたり)、これも安い方が有利です。日本は35ドル、香港は157ドル(さすがに高いですね)、シンガポールは80ドル、タイは21ドル、フィリピンは20ドル。ざっとこんな感じです。人口や経済については、第162話から第173話までを参考にしてください。
佐川急便は海外事業の統括会社をシンガポールに設立しました。ここを拠点に全世界規模での物流網を構築するためです。シンガポールにはアメリカのフェデックスをはじめとする世界の大手物流企業がほとんど拠点を構えています。まさに、国際物流のハブを形成しているのです。ハブに自分も出てゆかなければ国際戦略は立てようがないのでしょう。
三井物産はアジア・太平州三井物産をシンガポールに設立しました。この現地社長の決裁する金額は本社の営業本部長の権限を上回る層です。それは、「ここにいないと重要な商談ができない」というシンガポールの経済力によります。
日産自動車やトヨタ自動車は開発や生産、部品調達の機能をタイに置こうとしています。それは、裾野の広い自動車産業に関係するさまざまな製造業がタイに集積していて、周辺国の組み立てや下請けの工場を含めた生産の一括管理に向いていること、そしてASEAN内における関税自由化で輸出拠点として有利になることがあります。
また、日本経済新聞の社長100人アンケートによれば、「これからの生産をどうしますか」という質問に対して、国内生産を拡大は7.5%に過ぎず、海外生産を拡大は44.4%と圧倒的です。その拠点としては、タイ、インドネシア、ベトナム、ミャンマーがあげられています。
また、「中国以外で有望な市場は」という質問に対して、57.5%の経営者がインドネシアをあげ、他にはタイ、ベトナム、ミャンマーというところです。さまざまなカントリーリスクはあるものの、人口や所得の伸びが著しいことから魅力が高いのです。
では、カントリーリスクとは何でしょうか。一般的には経済に悪い影響を与えかねない不安定要素のことを指します。これが多ければ多いほど、ハイリスクな国と言えるでしょう。例えば、中国のように政治体制の問題もカントリーリスクにあげられます。電力が不足しており停電の危険性がある(上海)、洪水が起こるとライフラインが止まる(タイ)、組合運動が盛んで労働争議が心配(韓国)、交通網が整備されていないので物流に時間がかかる(ベトナム)、などがそれにあたります。
具体的な事例としては、多くの企業経営者が今後に期待するインドネシアでは、このところ通貨安と最低賃金の引き上げという問題が起こっています。通貨安は輸入品の急騰につながりますから、部品を輸入して組み立てる産業ではダメージが大きいですし、最低賃金の引き上げは政府が認めれば人件費の高騰につながり、政府が認めなければ政治的不安定さが拡大しますので、いずれにしてもカントリーリスクの典型のようなものです。
こうしたカントリーリスクをきちんと把握し、それに対する備えを整えることが重要ですので、中小企業や小規模事業者として海外進出を目指す場合には十分注意してください。必要な情報はジェトロ(日本貿易振興機構、JETRO)で得ることができます。
B-A「東南アジアに見る市場開拓①~アジア・バロメーター~」
中小企業や小規模事業者にとって、重要な海外市場、海外生産拠点となっている東南アジアの現状について、第162話から第173話までシリーズでお伝えをいたしました。皆さんも東南アジアのイメージが頭に残っているでしょう。そして、これから拓ける広大な市場にも想いを巡らせているかもしれません。なにせ、人口6億人を超える巨大で、ある意味手つかずの市場です。今回は、そうした東南アジア(あるいはアジア)への進出をさまざまな観点から進めている日本企業の事例を取り上げることで、より鮮明に中小企業や小規模事業者の新天地になりうる東南アジアを実感していただき、同時に新しい市場を開拓する際に重要なエッセンスを汲み取っていただきたいと思います。
まず、新潟県立大学の猪口孝学長が進めている「アジア・バロメーター」という世論調査から、東南アジアをはじめとするアジアの国々の“生活の中身”“国民意識”をお伝えいたしましょう。
まず、「子どもに対してどのような価値観を教えたいか」という質問に対して、“思いやり”が突出したのは日本だけ、中国、韓国、台湾、香港、シンガポールでは“独立”“勤勉”“正直”が上位を占め、他人を強く意識する日本と自己を強く意識するその他の国々との差が明らかになっています。
また、「国民として考える重要性の順位」という分析でも面白い結果が出ており、“個人生活”⇒“社会関係”⇒“国家の強さ”という順番なのは日本とインドネシアと台湾、“個人生活”⇒“国家の強さ”⇒“社会関係”という順番なのは中国、インド、モンゴル、韓国、ミャンマー、“社会関係”⇒“個人生活”⇒“国家の強さ”という順番なのはタイとベトナム、“国家の強さ”⇒“社会関係”⇒“個人生活”という順番なのはシンガポールとアフガニスタン、“国家の強さ”⇒“個人生活”⇒“社会関係”という順番なのはカザフスタン、ブルネイ、フィリピン、パキスタンとなっています。ここでは、国家というものの存在が強い国々と、弱い国々(日本、インドネシア、台湾、タイ、ベトナム)との違いが見て取れます。
さらに、「営業許可を求めても役人が受け付けないときにどうするか」という質問に対して、“賄賂を使う”という選択をしたのは非常に少なく、インドで5.1%、中国で2.3%、日本では0.3%に過ぎず、東南アジア(あるいはアジア)と言えば賄賂の巣窟というイメージとはかなりかけ離れた結果となっています(とはいえインドでは5%以上が賄賂を使うのですから驚きです)。
このように、一口で東南アジア、あるいはアジアと言っても、それぞれの国の状況には違いがあり、一括りで片づけられるようなものではない、ということを皆さんはよく記憶していただきたいと思います。
それが、これからお伝えする東南アジア(あるいはアジア)への進出をさまざまな観点から進めている日本企業の事例を理解するうえでも重要な要素となるのです。
C「中小企業とは④~開業支援~」
中小企業や小規模事業者が日本の経済のかなりの部分を支えている、というお話を第192話でお伝えいたしました。その中で、あまりにも低い開業率(欧米は10%以上、日本は5%以下)にも触れさせていただきました。この低い開業率、そして第194話でお伝えした「事業承継(後継者問題)」が、日本の中小企業や小規模事業者に重くのしかかっています。要するに、どんどん中小企業や小規模事業者が減ってゆく、ということです。
中小企業や小規模事業者が減るのは、一見競争が少なくなって助かると思う人もいるでしょうが、社会全体の多様性が失われ、結果として経済や市場が失速し、ビジネスアライアンスを組む相手にも事欠く、という事態を招きかねません。こうした現象がいち早く訪れ、10大財閥の売上がGDPの70%を超えるまでに経済の寡占化が進んだ韓国では、さすがにこれはまずいということで、今は「同伴成長委員会」という組織を立ち上げ、大企業の経済活動を規制し、中小企業や小規模事業者を保護しようと動いているほどです。
日本においてもそうした動きがはじまっており、「事業承継」についての支援策は前回ご紹介しました。今回は、開業率の方(起業家を増やす)についてお話を差し上げたいと思います。
ベンチャーブームの前でしょうか、15年ほども前になりますが、同じように開業率の低さが問題となり、経済産業省や総務省が起業支援にそろって動いたことがありました。確か小渕内閣か橋本内閣だったと思います。今回も似たような現象がはじまっていまして、筆者の住んでいる福島県では、この半年の間に小規模事業者活性化事業、被災地復興創業支援事業、地域需要創造型等起業・創業促進事業と、ちょっと見には何が違うのかよくわからない支援制度がはじまり、3分の2の補助を謳い文句に起業家予備軍を集めています。
こうした支援制度の成果は別の問題として、皆さんも仮に起業を考えているのであれば、まさにチャンスの時期です。公的な支援に加え、融資先まで紹介してもらえるのですから、願ったりかなったりの優遇措置です。長野県でも対象になる支援制度もありますので、ぜひWebで調べてみてください(“ミラサポ<https://www.mirasapo.jp/>”も使えるでしょう)。
さて、それではどんな創業が出てきているのか、今回はそれもご紹介したいと思います。
日本経済新聞が伝える、あの東日本大震災で甚大な被害を受けた気仙沼市の高校生たちの挑戦です。
それは、「なまり節ラー油(なまらー)」という新しい商品の開発です。鰹節より燻す回数が少ない「なまり節」、気仙沼ではカツオやサバを使って作るのですが、これを原料としたラー油ベースの調味料で、気仙沼の高校生のクラブ活動「高校生による気仙沼のドライフードのイノベーション!」から生まれたものです。
そして、震災復興を支援するために東京大学i.schoolの修了生を中心とした有志によって立ち上げられたi.club(任意団体)が、Webを通じて資金を集め(クラウドファンディング)、協力者を集めて、事業化を成功させたのです。
政府の支援制度に依存せず、純粋に民間の力と地元の高校生のアイディアではじめられたことに、筆者は素晴らしい可能性を感じています。皆さんも以下のURLで、彼らの活動をぜひご覧いただきたいと思います(http://innovationclub.jp/reports/)。
そうして考えますと、公的な支援制度を活用すれば、さらに起業への心理的、物理的な障壁は少なくなるのではないでしょうか。皆さんの中で起業をお考えの方がいらっしゃったら、お気兼ねなくこのコラムの事務局(信州大学繊維学部AREC一般財団法人浅間リサーチエクステンションセンター:0268-21-4377)までご連絡ください。
C「中小企業とは③~事業承継~」
中小企業や小規模事業者の直面する問題として、これまでも市場開拓、人材確保、経営資源の豊富化、資金繰りなどさまざまに見てまいりました。今回は、中小企業や小規模事業者の見えざる問題として、「事業承継」を考えてみたいと思います。
多くの中小企業や小規模事業者では経営者が創業者である、あるいは創業者の家族である、という形態が多いものです。これは、株式を上場していないので、内内の観点から経営者が決まる、という背景もあります。株式を上場していれば内内だけが株主という訳にはまいりません。不特定多数の株主の評価が経営者を決める力となるからです。
従って、中小企業や小規模事業者の経営者が青年期、壮年期であるうちは何の問題も起きないのですが(不慮の事故を除いて)、経営者が壮年期を過ぎ、老年期に入ると問題が浮かび上がってきます。
それは、「誰が経営を継ぐべきか」という悩ましい問題です。
悩ましい理由の一つは、その会社の株をどう継ぐかということです。家族や次の世代であれば相続ということになりますが(税法上の問題はあります)、そうでなければ株を継ぐのはその会社を買うのと同じですから、新しい経営者はそれだけの資力が無ければ困ります。もっとも、株主一族に雇われる形態で経営者を継ぐのであれば問題はありませんが、その場合は二頭立ての馬車になる危険性があることを承知しなければなりません。
また、家族や次の世代が継ぐ場合は、相続税のほかに、果たして経営者として適任かという問題も残ります。
そんなこんなでいわゆる「事業承継」は中小企業や小規模事業者の難問の一つとされています。
筆者の知り合いでも、数件ほどこの悩みに直面したケースがありますが、皆さん、若い頃のようには働けない、心身ともに辛い、でも替われる人がいない、ということで、この先どうしようかと悩んでいるのです。筆者はそういう場合(一応経営コンサルタントですので)、飛躍を目指して会社を二次創業するだけの気力と体力が無いのであれば、そして後継者に心当たりが無いのであれば、いっそのこと企業を売りなさい(売れるうちに)と助言することにしています。
それはさておき、この悩ましい「事業承継」を支援する仕組みがいくつかありますので、この際にご紹介したいと思います。皆さんが選んだ中小企業や小規模事業者で経営者が60歳代以上で、なおかつ社内で認知された後継者がいない場合は、こういった知識も必要になるからです。
第一は、中小企業庁が全国に設置してある「事業承継支援センター」で相談対応や専門家派遣、開業希望者とのマッチングなどのサービスを受けることができます。中小企業基盤整備機構の事業承継・知的資産経営支援室に問い合わせると、近くのセンターを紹介していただけます。長野県の場合は、長野市と松本市の商工会議所に設置されているようです。
第二は、取引先の銀行で支援してくれるケースがあります。これは銀行からしてもお得意様が無くなると大変ですから、引き継いでくれる方を探してくれるのです。ただし、重要なお得意先(融資の返済を保証できる)であることが必要です。
いずれにせよ、日本の中小企業の社長さんの二人に一人は60歳以上、8割の社長さんは「事業継承が経営上の問題点」と認識している現状がありますので、皆さんも中小企業や小規模事業者を選択する際は、経営者の年齢や後継者の問題にも十分な注意を払っていただきたいと思います。経営者が変わると会社がころっと変わる、ということもよく発生するからです。
C「中小企業とは②~若者応援企業~」
前回は中小企業や小規模事業者の定義、あるいはそれに対する政府の支援策についてお話を差し上げました。今回は、皆さんがそうした中小企業や小規模事業者を選ぶ際のポイントについてお伝えしたいと思います。かなり以前になりますが、第1話で「企業には必ず価値観があり、それを調べるのが重要」ということをお伝えしました。また、数回にわたり、中小企業では経営者のウェイトが大きく、経営者がどういった人なのかを把握することも重要だとお伝えしました。それは、価値観が相容れない場合、なかなか上手に関係を築くのが難しいからです。
こうした若者から見た中小企業、あるいは小規模事業者の基準に、この頃は政府も本腰を入れはじめているようです。
既に就職に際しての支援策については、第99話で若者チャレンジ奨励金、新卒応援ハローワーク、新卒者就職応援プロジェクトといったものをお知らせしてきました。
今回は、若者の採用と育成に積極的な企業を厚生労働省が「若者応援企業」に認定する、という話題です。
その背景には、自分の就職した会社がいわゆるブラック企業だと若者の4人に1人は考えているという笑えない現実があります。異常な長時間労働、パワーハラスメント、いじめなどで心身に不調を訴える若者は枚挙に暇がありません。このため、若者が安心感を求めて大企業へ殺到し、中小企業や小規模事業者では人手不足や人材確保に頭を悩ませている、という現実があります(大企業は求人倍率が0.7倍の狭き門、中小企業は1,91倍と応募者不足)。
そこで、「国が優良と認めたホワイト企業を教えて欲しい」という若者の声に応える形で、「若者応援企業」という認定制度がはじまったのです。
例えば長野県ですと、今日現在で次のような企業が該当しています。
(http://nagano-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/oshirase/_114858/_114859.html)
赤田工業㈱。㈱アールエフ、飯田精密㈱、オリオン精機㈱、KOA㈱、㈱しなの富士通、㈱GAC、㈲多田プレシジョン、長野日本無線マニュファクチャリング㈱、ハイブリッド・ジャパン㈱、㈱ホクト精工、マンズワイン㈱小諸ワイナリー、㈱黒澤組、三協電気工業㈱、宮尾鉄筋㈱、伊那バス㈱、㈱ロイヤルオートサービス、知識工学㈱、㈲大吉(元祖ニュータンタンメン本舗)、㈲佐々木薬局、こんな具合です。
ざっと見て、本当に小さそうな会社から、かなりの規模の会社まであるようですが、皆さんの参考になるのではないでしょうか。
なお、若者応援企業の基準は次のようなものです。
① 学卒求人など、若者対象のいわゆる「正社員求人」をハローワークに提出すること
② 「若者応援企業宣言」の事業目的に賛同していること
③ 就職関連情報を開示していること
・社内教育、キャリアアップ制度
・過去3年度分の新卒者の採用実績及び定着状況
・過去3年度分の新卒者以外の正規雇用労働者(35歳未満)の採用実績と定着状況
・前年度の有給休暇および育児休業の実績
・前年度の所定外労働時間(月平均)の実績
④労働関係法令違反を行っていないこと
⑤事業主都合による解雇または退職勧奨を行っていないこと
⑥新規学卒者の採用内定取消を行っていないこと
⑦都道府県労働局・ハローワークで扱っている助成金の不支給措置を受けていないこと
③④⑤あたりは重要で、③は開示されているのですからありがたい情報です。
C「中小企業とは①~法的な位置付けと支援制度~」
このコラムは、中小企業・小規模事業者が地域で学んだ大学生などを地域において円滑に採用でき、かつ定着させるための自立的な仕組みを整備するために、①これから社会に参加する若者の皆さんに「働く」、あるいは「ビジネス」ということがどういったものなのかを知っていただく、②中小企業・小規模事業者で働くために重要な知識やスキル、あるいは社会人基礎力を身につけていただく、③政府が進めようとする民間企業の海外進出において必要とされるさまざまな国や地域の情報や文化風土などの基盤的な知見を知っていただく、そうしたことを大きな狙いとしています。ところで、その中小企業とは何でしょうか。大企業より小さな企業、そんな漠然としたイメージをお持ちかもしれません。しかし、中小企業基本法という法律では次のように定められています。
① 製造業、建設業、運輸業では、資本金3億円以下、常時使用する従業員300人以下のいずれかを満たす
② 卸売業では、資本金1億円以下、常時使用する従業員100人以下のいずれかを満たす
③ サービス業では、資本金5,000万円以下、常時使用する従業員100人以下のいずれかを満たす
④ 小売業では、資本金5,000万円以下、常時使用する従業員50人以下のいずれかを満たす
⑤ 旅館業では、資本金5,000万円以下、常時使用する従業員200人以下のいずれかを満たす
⑥ ソフトウエア業・情報処理サービス業では、資本金3億円以下、常時使用する従業員300人以下のいずれかを満たす
また、法人税法では、業種が何であれ資本金が1億円以下であれば中小企業として扱われます。
さらに、おそらくは株式を上場していないこともあげられます。資金を株式市場からは調達できない、銀行借入で資金を調達するしかない、という意味になります。
一方、小規模事業者は同じ中小企業基本法で「小規模企業者」として定められ、商業・サービス業では従業員5人以下、製造業では従業員20人以下とされています。
さて、そうした中小企業や小規模事業者に対して、政府はどんな現状分析を行い、その将来像を描いているのでしょうか。経済産業省中小企業庁の参事官が一面広告で次のように表明していますので、皆さんも参考にしてください。
第一は、日本の企業の99.7%は中小企業(小規模事業者を含む)、従業員数も全体の66%、GDPへの貢献度も製造業については40兆円と全体の50%を占めている。中小企業がこれだけの力を持つ国は日本しかない。この中小企業が活性化するかどうかが、日本経済再生の鍵を握るということ。
第二は、人材をはじめとする経営資源が不足しているのが最大の課題。また、長年の下請け関係が影響し、自分の強みが何であるか、それに気づいていないケースが多いこと。
こうした現状を打開するため、政府で取り組んでいることも次のように説明していますので、ぜひこうした支援策を活用してください。
第一は、あまりにも低い開業率(欧米は10%以上、日本は5%以下)を改善するため、“地域創業促進支援事業”を全国300ヶ所で展開し、開業前から開業後まで経営力の強化を支援できる体制を整えること。
第二は、中小企業がワンストップで相談が受けられる“(仮称)よろず支援拠点”を全国47ヶ所に開設し、経営資源や資金調達などを素早くサポートすること。
第三は、支援制度をWeb上で紹介する“ミラサポ(https://www.mirasapo.jp/)”を拡充し、複雑な中小企業支援制度を簡単に検索できるようにし、Web上で専門家との相談や異業種とのマッチングなどが可能になる双方向性のコミュニティ機能を実現すること。
第四は、中小企業の海外進出(既に5,600社)を増やすため、“中小企業海外展開現地支援プラットフォーム”を現状の10ヶ所から15ヶ所へ拡大すること。現在は、中国(重慶・成都)、インド(チェンナイ、ムンバイ)、インドネシア(ジャカルタ)、タイ(バンコク)、フィリピン(マニラ)、ベトナム(ホーチミン、ハノイ)、ミャンマー(ヤンゴン)、ブラジル(サンパウロ)です。
いかがでしょうか、政府の支援制度はそれに頼りすぎるといけませんが、いわばカンフル剤として利用するには便利なもの、自立できるようになったら離れるとしても、それまでは有効に使うことが中小企業や小規模事業者にとっては重要だと思います。
C「観光振興の行方」
地域の活性化の切り札として観光を考えるところも多いでしょう。それに携わる中小企業や小規模事業者も、直接観光業か、ステークフォルダー(stakeholder、利害関係者)かは別としても、かなりの数にのぼると思います。そうした観光の大きなユーザとして外国人が存在することは皆さんご承知でしょう。既に政府は“ビジットジャパン構想”を立ち上げ、年間の外国人観光客を1,000万人にしようとしています。1,000万人というと見当がつかないかもしれませんが、フランスは8,300万人、アメリカは6,600万人、中国は5,700万人で、1,000万人に近い国はオランダ、エジプト、韓国、ハンガリー、モロッコといったところですから、日本の1,000万人というのは、これだけ自然や文化に恵まれた国にしては少ないものではあります。
それはさておき、外国人観光客です。みずほ総合研究所のまとめた「みずほリポート~国内観光市場の見通しと雇用への影響~」によりますと、人口減少や所得の伸び悩みから日本人旅行者数は前年割れが続き、2010年から2020年にかけて約3億人から約2億人へと約1億人も減少する、というショッキングな予測が出されています。そうなりますと、外国人観光客誘致となるのは当然の流れです。
こうした外国人観光客への期待は日本だけではありません。特に2012年時点で8,300万人にまで拡大した中国人観光客の取り込みをめぐっては、アジア中で誘致競争が激しさを増しています。この誘致競争を分析することで、外国人観光客の取り込みへ向けたヒントが見つかるのではないでしょうか。いくつかの事例を日本経済新聞の記事からお伝えいたします。
韓国では、中国における韓流ブームをフル活用する戦略です。韓流スターと中国人向けテーマパークを前面に押し出して、中国人観光客の呼び込みに必死です。政府もビザなし観光を認めて、いわゆる規制緩和を進めています。こうした観光に関する規制緩和は大きなアドバンテージになるでしょう。
タイでは、中国人の消費意欲に的を絞り、中国人を受け入れる大規模商業施設を整備しています。政府も中国人観光客へのビザの免除や、中国本土での営業拠点を設けるなど、その支援に大わらわです。
オーストラリアでは、“グッディ・チャイナ”と名付けた誘致作戦をスタートし、中国語サイトをcnドメインで開設するほどの気の使いよう。誘客には中国人向けのテーマパーク(老街と呼ぶ古の中国の街並み)を整備しています。
こうした誘致競争の背景には、中国人観光客は数が多く、増加しており、かつ消費する金額が大きいというポイントがあります。特に銀聯カード(中国のクレジットカード)を利用できる施設や店舗では、一人あたり20万円近い中国人観光客の観光支出は魅力でしょう。
それでは、日本の状況を見ますと、政治的な問題もあって伸び悩んでいた中国人観光客ですが、9月以降は月あたり15万人を超え、全体の20%近い割合を占めるようになってきました。この変化を的確に掴み、中国人観光客の取り込みに先立って行動することが、これからの観光振興には欠かせないと思われます。
そのためには、韓国やタイ、オーストラリアの動きを参考にし、脅威にも感じながら、日本としての道を探る必要があるようです。
筆者が常々中国と関わりを持つたびに感じるのは、次のようなことです。
① 中国人のプライドを利用する。決して中国人を見下げることをしない。むしろ、中国から伝わった技術や文化を自分たちの地域で活かしている点をPRする。
② 中国人の旺盛な「消費欲」「健康欲」「自己顕示欲」をさらに喚起する。
③ 中国人の“群れ気質”を活用する。その意味での中国人向けの施設やサービス、商品などを用意する。
こうした点に注意するだけで、かなりのアドバンテージが取れるのではないでしょうか。もちろん、中国人向けの営業や宣伝が欠かせないことは言うまでもありません。そして、中国人観光客向けにできることを考えれば、地域の中小企業や小規模事業者にとってかなりのビジネスチャンスが巡ってくるのではないでしょうか。
C「規制緩和の続き~立ちはだかる壁~」
需要はあるのに供給されない、という不思議な現象について、これまで何度もお伝えをしてきました。それは、そういった現象が変わるとき、そこには必ずビジネスチャンスが生まれ、中小企業や小規模事業者にとって新しい市場が拓かれるからです。しかし、そこには必ず「規制」という大きな壁があります。この壁をどう壊せるのか、それにこそアベノミクスが本当に日本経済の再生を実現できるかどうかがかかっています。
これまでも医療、農業、雇用、福祉など、様々な分野での規制についてご紹介してきましたが、今回もその続きをお伝えしたいと思います。
派遣労働という形態があります。現在、企業は「同一業務」については3年以上の派遣を受け入れることができません。これは、受け入れる派遣元企業や派遣労働者が変わっても3年が限度です。ですので、例えばAという派遣労働者を1年、Bという派遣労働者を2年受け入れれば、そこで打ち切りとなります。
ということは、派遣労働者にとっては自分について3年ではなく、前に同じ業務で派遣されていた人がいれば、その人の派遣期間は3年から差し引かれることになります。これは、派遣労働者にとっては不安定極まりない話で、とても安定して同じ職場で働くことができません。
この例外は法律(政令)で決まっている26の専門業務だけで、これについては3年を超えて派遣を受け入れることができます。例えば、ソフトウェア開発、財務処理、調査、通訳、添乗などです。しかし、具体的にどういった業務ならば許されるのか、については、大きな問題があります。
というのは、皆さんが実際に派遣で働くと考えて欲しいのですが、例えば財務処理という業務のために派遣されているとして、実際の職場ではいろんなことは起きます。お客さまから電話がかかってきて、職場で電話を取る人が不在な場合、あなたならばどうしますか、「私は財務処理の派遣なので電話を取りません」などと言えるでしょうか。あるいは、職場に宅配便が届いて受付の女の子がいない場合、あなたならばどうしますか、「担当がいないので受け取れません」などと言えるでしょうか。
実は、あなたが財務処理で派遣されているとすれば、電話を取るのも、宅配便を受け取るのも「違反」と見做されるのです。それが所轄の労働基準局などに見つかれば摘発されることになります。実におかしな話ですが、民主党政権時代に正社員の仕事を奪ってはいけない、という理屈で厳しく規制されることになりました。
こうなりますと、受け入れる企業の方でも「これは頼んでいい業務なのか、頼んでいけない業務なのか」とその都度チェックせざるを得ず、どうしても派遣を利用することをためらってしまいます。派遣労働者の方でも「仕事を頼まれるたびに契約した業務に入っているかどうかを確認しないといけないので、時間と手間がかかってどうしようもない」ということになります。
もちろん、派遣労働が不安定なもので、派遣切りやワーキングプワーの問題など、様々な矛盾を抱えていることはそのとおりですが、だからと言って、実際に働いている人たちの仕事を奪う、あるいは仕事をしにくくするような規制では困ります。
こうした規制の矛盾は、今回ご紹介した派遣労働以外にもたくさんあることは既にご承知だと思います。そして、こうした規制の矛盾が新しい市場に立ちはだかっている壁ではありますが、壁が壊れたときには、一散に新しい市場が拓かれるのです。
前回お伝えした「トラブルをチャンスに」と同じように、「規制があるから新しい市場もある」とお考えいただき、規制緩和の流れを的確に読むことで、中小企業や小規模事業者のビジネスチャンスを見出していただきたいのです。
C「NISA」
皆さんはまだお金と真剣に向き合う機会は少ないでしょう。しかし、中小企業や小規模事業者にとってお金は生命線です。黒字でも資金繰りで倒産することがよくあるからです。そこで、今回はNISA(少額投資非課税制度)という、来年1月からはじまる仕組みをお伝えし、皆さんにも身近な「投資」の世界をご紹介しましょう。
NISA(少額投資非課税制度)は、もともと英国ではじまった少額投資を優遇する制度(Individual Savings Account、個人貯蓄口座、ISA)を日本流にアレンジしたもので、通常は利益の20%が課税されるところを、年間100万円までの投資であれば、その投資から得られた利益(株式売却益や配当)を非課税にする、という内容です。
ただし、一人一口座で、一度開設した口座は4年間は他の金融機関へ動かせませんのでご注意ください。
皆さんも年間100万円までの投資であれば(20歳以上の日本に住んでいる人ならば誰でも)、その結果がどれほどの利益を産もうと税金はかからないのですから、この際、思い切ってお小遣いを投資する手もあるかもしれません。
具体的には、証券会社や銀行にNISAの専用口座を開設し、この口座を利用して株や投資信託(株や債券を組み合わせた金融商品)を購入すれば、最長5年間、その間でいつ売却しても、得られた利益には税金はかかりません。
この口座の開設申し込みは今年の10月1日からはじまっていますが、既に300万件を超えており、最終的には500万件を超える大きなブームとなると期待されています。
では、税金をただにしてまで、どうして国はこういった制度を作ったのでしょうか。
そこには、日本の家計における金融資産、実に1,500兆円を超えると言われていますが、その多くは現金・預金(848兆円)であり、株式(124兆円)、投資信託(71兆円)が少なすぎる、という現状があります。
しかも、この現金・預金は銀行へ流れるのですが、銀行でもそうしたお金を企業への融資に廻すよりも国債の保有に廻してしまうので(融資54%、国債保有46%)、全体としてお金は貯められるだけ、という困った現象があるのです。一方で資金に困っている企業、特に中小企業や小規模事業者がおり、一方でお金がだぶついている銀行や家計があるのに、その間ではお金が流れずに、お金は預金や国債に化けるだけ、というのでは、体に血が流れないようなもので、いつまでたっても日本経済は元気になれない、という訳です。
もちろん、その原因には銀行がリスクを取りたがらない、ということもあります。バブル清算の過程で不良債権が問題となったトラウマから、企業への融資には必要以上に慎重になっているのです。
いずれにしても、こうした困った状況を変えるには、家計の現金・預金を株や投資信託へ換えることが重要で、その呼び水として作ったのがNISAだ、と言えるでしょう。
とあれ、とりあえず税金がただになるのですから(もちろん得した場合だけですが)、多くの人がこの制度を利用して、日本経済とダイレクトのお付き合いをするのも悪くないのではないでしょうか(1万円単位で投資できますので、そんなに資金を持たなくとも大丈夫)。
C「トラブル処理」
第183話で「トラブルをチャンスに変えよう」をお伝えしました。中小企業や小規模事業者で働くことは、組織が小さいだけに直接お客さま(ユーザやクライアント)と向き合うことが多くなります。そこでは、実にさまざまなトラブルが起こるものですが、組織がそれをサポートしてくれる機会には恵まれないこともあるからです。そして、初動期に多発しがちなトラブルは、逆に客さまとの距離を縮めるチャンスだということ、そしてLEAD法を使ってみましょうということをお伝えしました。
そうしましたら、タイミングよく日経プラス1で「トラブル発生」という特集をしていましたので、ご紹介したいと思います。
ここでまず繰り返し強調されているのが、「トラブルの際は謝り方が重要」ということです。
① 自分の非は即座に誤る。
② 謝る手段は電話、まずは肉声で伝えることが鉄則です。
③ トラブルが深刻ならば、相手先に飛んでゆき、会えなくても名刺を残す、会えるまで繰り返すのが重要です。
④ 電話で一報、出向いて謝罪、さらに詫び状も持参し、二重三重の手立てを用意する。
いかがでしょうか、素早く、率直に、直接、というポイントがおわかりいただけるでしょう。
次に強調されているのが、「トラブルは改善できる機会と受け止めて、学ぶ姿勢を現わす」ことです。
① 相手の言い分に耳を傾ける。
② 自分の非には責任を取り、罰を受ける覚悟を現わす。
③ トラブルの原因を探ることで改善につなげる。
④ トラブルの結果が、相手にも自分にもプラスとなって残るように努める。
いかがでしょうか、まさにトラブルはチャンスに変えられるのです。
そして、皆さんのすぐにでも役に立つヒントをお伝えいたしましょう。インターネット調査で支持の多かったものを記事から抜き出してみました。
(1) トラブル発生したら、最初にすることは?
第1位:すぐに出向いて謝る
第2位:電話で誤り、直接出向く
第3位:手書きで謝罪の手紙を送る
(2) 相手を訪問の際は?
第1位:上司と一緒に
第2位:スーツなど派手でない服装
第3位:相手の好みにあわせた手土産を持参
(3) 相手と向き合ったら?
第1位:まずは謝罪の言葉を
第2位:相手の目をしっかり見て
第3位:感情を込めて
(4) 許してもらうためには?
第1位:素直に非を認める
第2位:部下や下請け業者のせいにしない
第3位:うそをつかない
いかがでしょうか、この真逆をすると間違いなくトラブルは引きずりますのでご用心ください。それは、こういったことです。
「謝罪はメールですます」
「謝罪の際に身なりを気にしない」
「相手を見ずに(気持ちを入れずに)言葉だけで謝る」
「他人のせいにする」
皆さんもトラブルに巻き込まれたら、このコラムをぜひ参考にしてください。
C「ロレアルとパナソニック」
中小企業や小規模事業者において重要なことは、製造やサービスの品質です。品質が悪ければ、なかなか競争には勝てません。ですので、品質向上には十分過ぎるほどの注意を払うのが中小企業や小規模事業者にとっては生命線と言えます。利益に目がくらんで品質で手を抜くと、間違いなくユーザやクライアントから手酷いしっぺ返しを喰らうことになりかねません。
こうした品質では定評があるのが日本です。“メイドインジャパン”という言い方は過去のものとなりつつありますが、日本製、あるいは日本発の製品やサービスが良質なのは、世界中の消費者の評価となっています。
日本経済新聞の記事によれば、この品質に着目したのがロレアル、そう化粧品では世界一のフランス企業です。現在、ロレアルでは静岡の御殿場に工場を持ち、高級化粧品を年間5千万個生産していますが、そこに約20億円を投資し、生産能力を倍増するというのです。そして、日本製を強みとして、アジア市場を開拓しようというのです。そのためには現在フランスで生産している製品も日本の新工場へ移転するというのですから、なかなか本気な話です。
こうした動きはロレアルだけではないようです。
ユニリーバ(イギリス&オランダ)でも相模原工場で高級ヘアケア製品を増産し、P&G(プロクターアンドギャンブル、アメリカ)でも滋賀工場で高級化粧品を増産するそうです。
急速に所得が向上し、市場規模が拡大の一途を辿っているアジアで、新しい顧客を開拓するために、彼らは日本製の強みを最大限に活かそうとしているのです。
これに対して、日本発の高品質を活かせない事例もたくさんあります。
日本を代表する大企業パナソニックでは、とうとう半導体部門の従業員を7,000名も減らすことにしたのです。もっとも解雇の難しい国内では配置転換で対応し、解雇は主に海外の生産拠点で行うようです。
しかし、いずれにせよパナソニックが日本製の強みを活かすことができず、これまで重点分野として位置付けていた半導体事業を縮小することは事実です。
その原因は多くの経済評論家にお任せをしますが、筆者が見る限りでは、膨れ上がる開発コストを吸収することが、もはや単独企業の体力では難しいとわかった段階で、企業の壁を超えて事業統合に踏み切るのが唯一の道ではなかったのか、と思えて仕方ありません(半導体事業をサムソンへ集中させた韓国とは好対照)。
しかし、そうしたダイナミズムに踏み切れない日本の大企業は、みんなで顔を見回して、誰が言い出すのかを待っている間に、どんどんと事業の価値が毀損し、時期を逸してしまった、というのが真実に近いのかもしれません。
この辺がイノベーションに貪欲なGE(ゼネラル・エレクトリック)との差、ではないでしょうか。
C「これはイノベーティブでしょうか?~富士通の製造受託~」
中小企業や小規模事業者で重要なイノベーションの事例を数回にわたってご紹介してきましたので、皆さんにもイノベーションの具体的なイメージが持てていると思います。今回は、富士通がはじめた新事業を題材として、これがイノベーションと言えるかどうかを探ってみたいと思います。
富士通と聞くと皆さんは何を想像するでしょうか。日本を代表する総合エレクトロニクスメーカーであり、ハードウェアとソフトウェアを供給するITベンダーとしては日本第一位、世界第三位の大企業です。パソコンやサーバ、携帯電話やスマートフォンを作るだけではなく、情報システムの構築でも超大手、世界百ヶ国に拠点を持ち、グループ全体としては17万人もの従業員を抱えています。
そんな大企業も近年は経営の方向性を巡って悩みを抱えており、社長が解任されるなどその舞台裏はなかなか大変なようです。とりわけ、世界的なライバルのIBMがハードウェアからソフトウェアへ、ソフトウェアからソリューションサプライヤー(総合的な問題解決能力)へと大きく舵を転換したのと比較すると、依然として幅広の事業を自社内に抱え込み、「選択と集中」がうまくいっていない印象を持たれています。
そんな富士通が、なんと製造受託サービスをはじめるというものです。要約しますと、試作品や部品、完成品までエレクトロニクス関連の受託生産を手掛けるのです。
これには富士通の強みが隠されています。それは、富士通では2004年にトヨタ自動車のTPS(トヨタ生産方式)を導入し、これに情報技術を組み合わせてFJPS(富士通生産方式)と呼ぶ生産性の高いシステムを構築しているのです。
この強みを活かして、一瞬似合わないと思える製造受託サービスをはじめることにしたのです。
ここまでの流れを聞きますと、富士通が何かイノベーティブな新事業をはじめたな、とお感じになられませんでしょうか。
そもそも製造受託は、EMS(electronics manufacturing service)と言って、規模の大小に関わらず、自社では生産をせずに(ファブレス)、製品の設計・開発や宣伝・販売といった自らの得意分野に経営資源を集中するビジネスモデルがアメリカをはじめとして拡がりを見せている中で、急速に拡大している業界です。例えば、台湾のホンハイ(鴻海精密工業)、ここはシャープの経営再建で有名になりましたが、日本ではシークス(東証一部上場)という企業もあり、世界では24兆円という巨大な市場となっています。
こういう巨大な市場へ富士通が乗り出す、というとわくわくするイノベーティブな話なのですが、実はそうではありません。
富士通がはじめる新事業は、国内向けの高機能・高品質の製品、あるいは多品種少量製品を対象として、せいぜい300億円規模の市場を見ているのです。これは、ホンハイの売上1兆円と比較すれば30分の1以下という規模でしかありません。
とはいえ、富士通生産方式と呼ぶ生産性の高いシステムを強みとして、国内のさまざまな製造業とアライアンスを結ぶことには大きな可能性があるのではないでしょうか。
その意味では、小さな一歩ではあるが、富士通の自社抱え込みという体質を変えるイノベーションのはじまりかもしれないと思うのです。
C「減反見直し論に先を読む力を」
中小企業や小規模事業者で必要なことの一つに、「時代の先を読む」という能力があります。コンピテンシーで言えば“先見力(将来のニーズやチャンスを先立って考え、先取りしようと行動を起こす。第46話「コンピテンシー」参照)”です。これもコンピテンシーですから、意識して行動すれば伸ばすことができます。
今回は、「林芳正農相は25日、コメの生産量を絞る減反政策の見直しを表明。」という記事から、減反が見直されると何が起きるか、これを実際に予測してみましょう。英語で言えばシミュレーション(simulation、実際に行うことが困難な事象の結果を予測、分析する。)、イスラムで言えばキャース(理性による類推)です。
では、まず減反とは何かを調べてみましょう。
それは1970年、あふれかえるほどの在庫を抱えた米問題を解決しようと、政府が導入した生産調整のことです。当時は米を国が買い入れ、安い価格で消費者へ提供する仕組みでしたから、巨額な赤字が国に発生していたのです。
思い出しますと、筆者が1978年に地方公務員の採用試験を受けた際、面接で聞かれたことが「あなたは減反政策をどう思いますか」という質問でした。そのくらい、大変な政策だった訳です。何せ、それまでは作るだけ国が米を買い取ってくれたのが、そうはいかなくなったのですから。
それ以降、国が米を買い取る制度は無くなり(備蓄用は別)、米は基本的に自由に売買ができるようになる反面、価格の暴落を防ぐために年間の消費予測をもとに生産量そのものを絞るという仕組みになったのです。農家が生産量を絞ることに協力をしないと、国のさまざまな支援(例えば補助金)を受けられないという圧力を働かせ、仕組みを維持しています。
この結果、日本は1,200万トンくらいの米を生産できる能力があると思われますが、実際に生産しているのは800万トンくらい、しかもそれでもまだ消費しきれずに備蓄される米があるのです。しかも、かつては味は米の値段に影響がありませんでしたので、反(1,000㎡)あたり1トンも生産していましたが、今ではよくても600㎏(反あたり10俵)くらいしか生産していませんので、かつてのような多収性の品種を使えば、さらに生産が可能かもしれません。
その反面、農業年齢の高齢化(66歳)や長期にわたる減反の結果、40万haもの耕作放棄地がある、という現象も深刻化しています。
こうした日本の現状に減反政策の見直しはどういった影響を及ぼすでしょうか。今回はあまり精密に行うのではなく、思いつくままに考えてみましょう。皆さんもぜひお考えください。未来を読むことが新しいビジネスチャンスにつながり、中小企業や小規模事業者に新しい市場を拓いてくれるからです。
第一に、生産調整が無くなれば、生産過剰が生まれるでしょう。生産過剰は米の淘汰を産むでしょう。美味しい、安い、安全、そうした条件を満たさない米は生き残れないはずです。そうしますと、美味しい、安い、安全、そうした条件を満たす米へ向けたサービスには需要がありそうです。
第二に、逆に美味しい、安い、安全、そうした条件を満たさない米しか作れない農家や地域は生き残れないとなれば、そうした土地や地域をどうしたらよいのか、その方策が強く求められるでしょう。新しい地域再生モデルへ向けたサービスには需要がありそうです。
このように簡単に未来を読むだけでも、生き残れる米、生き残れない米、それぞれにビジネスチャンスがあるのはおわかりいただけると思うのですが、いかがでしょうか。